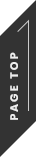《クロスエッジ》――ザ・シード上で展開される、一人の中学生によってデザイン・開発されたというVRMMORPG。とある噂を耳にして、それを確かめるために何度かログインしていたのだが……俺はそのゲームの中で目にした光景を、どうしても信じられずにいた。
そこにいたのは、ゴブリン――RPGに出てくる低レベルの敵モンスターではなく、アンダーワールドにいた、暗黒界の住人だった。
どうして……なぜこんなところに。
「キリト! 考えるのは後です!」
後ろから聞こえたアリスの声が、意識を現実に引き戻してくれた。
「ああ、すまなかった。まずはここを切り抜けないとな!」
数日前。
俺たちは久しぶりに、エギルが経営する《ダイシー・カフェ》に集合していた。
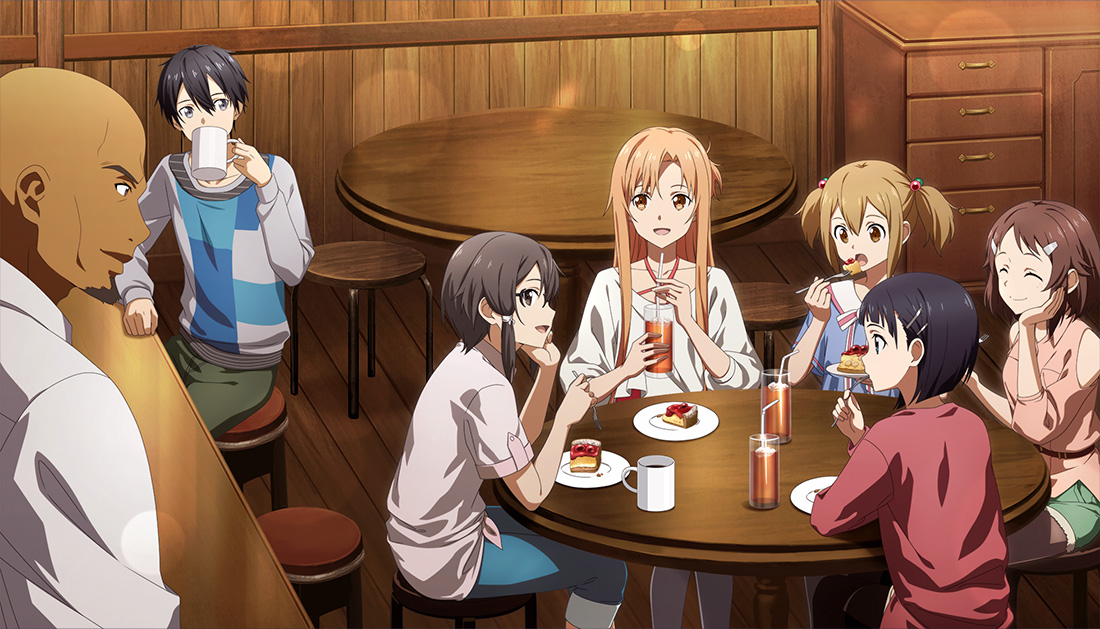
新作のケーキに、アスナやシノン、リズ、シリカたちが舌つづみを打っている。
「なにボーッとしてるの、お兄ちゃん」
「いや、なんでもないよスグ。コーヒーがうまいな、と思って」
久々に集まったみんなの姿に幸せを感じていた、なんて口には出せない。
「なら、おかわりはどうだ? もうカップが空だぞ」
「ありがとう、でも大丈夫だ。それよりエギル、そろそろ例の話とやらを聞かせてくれよ」
「わかった、わかった。じゃあその話に移ろう。」
「──《クロスエッジ》って知ってるか?」
「名前くらいは」
中学生がデザイン・開発したってことで話題になってるのを、ニュースで見たことがある。
「ああ、私も聞いたことあるわね」
シノンがコーヒーカップを持って、隣にやってきた。それをきっかけに、アスナやリズたちも集まってくる。どうやらケーキは食べ終わったようだ。
「クロスエッジ……学校でも、やっている人いますよね。ここにいるみんなは、やってないみたいですけど」
「まあ、みんな基本的にALOにログインしているもんね、最近は」
リズとシリカもクロスエッジを知っているようだが、プレイはしていないようだ。なかなかリアルで会えないアリスとは、ALOでよく会っているので、それもあるかもしれない。
「けっこう人気みたいなんだよね、色んなの世界が遊べるってことで」
「面白そうですね。あたしもやってみようかなあ」
シリカとリズは、クロスエッジに興味がありそうだ。
「それで、そのクロスエッジがどうしたんだ?」
「みんなが言うとおり、割と人気のゲームなんだが……妙な噂が流れはじめてな」
「噂? どんな噂だ?」
「なんでも、PvPで勝ち続けてトップランクまでいくと、えらく強い敵が現れるらしい」
「いや、普通じゃないの、それ?」
リズの言葉に、俺とアスナもうなずく。PvPのゲームは、同程度のランクのプレイヤーとマッチングするシステムになっていることが多い。自分のランクが上がれば、強敵と当たるのは普通のことだ。
「それだったら、確かに普通なんだけどな。でもそうじゃない」
エギルが急に声を潜めた。つられて、こっちも思わず息をのんでしまう。
「戦う相手は普通のプレイヤーじゃないんだ。そして、その相手に負けると……記憶の一部を喰われてしまうらしい」
「何だそりゃ……」
笑い飛ばそうとしたが、エギルの表情は真剣そのものだ。そして俺は……俺たちは、同じような事件に巻き込まれたことがある。
「……オーグマー事件と、同じ?」
「あっ……」
ぽつりとつぶやいたアスナの声に、シリカがビクッと体を震わせる。
オーグマー事件……現実世界を舞台としたARMMORPG《オーディナルスケール》で、アスナは本当に記憶を奪われてしまった。
「すまない、嫌なことを思い出させちまったな」
「ううん、大丈夫」
そう言って笑うアスナの顔も、少し辛そうだ。そっとアスナの手を握ると、ギュッと握り返してくる。
「まあ、ここまででも十分に奇妙なんだが、この話には続きがあってな」
「続きって、まだこんな物騒な話が続くのか」
「物騒かどうかは、微妙だが……クロスエッジでは、死者に出会えるそうだ」
「はあ?」
思わず、間抜けな声を出してしまった。
「だから、死んだ人間とゲームの中で再会し、一緒にプレイできるんだと」
「なにそれ……」
スグの声にも、疑問と不安が入り交じっている。それはそうだろう。死者と出会えるなんて、荒唐無稽な話だ。だが……さっきの「記憶を奪われる」という話と一緒に聞くと、言いようのない不安が襲ってくる。
「なによ、幽霊でも出るって言うの? ゲームの中に?」
「もう会えなくなった恋人に会いたくて、ゲームに入り浸ってる知り合いがいてな。ヤツの言い分を信じるなら、そういうことになる」
「それって、なんだか悲しいですね」
シリカが小さな声でつぶやく。それにシノンも同意する。
「そうね。会えなくても、もし会えたとしても、なんだが寂しい気がするわ」
死者にもう一度会えるなら。もしそれが本当なら、本当だと信じることができたら、俺は……。
「キリトくん……」
アスナが、もう一度強く俺の手を握る。そのぬくもりで、俺は思考の沼に落ちていかずに済んだ。
「しんみりしてるところ悪いが、話はこれで終わりじゃない。というか、ここからが本番だ」
「まだあるのか……」
「ああ。クロスエッジの中で、笑う棺桶のタトゥーをしているプレイヤーを見たって情報がある」
「なんだって!?」
思わず大きな声が出た。アスナも、驚きで目を見開いている。
「ラフィン・コフィン……。また、あいつらが現れたの?」
「あくまで噂だがな。だが、こうも妙な話が続くと、何かあるんじゃないかと思ってな」
「確かにそうだな……」
記憶や死者はともかく、ラフィン・コフィンが何か企んでいるなら、それは放っておけない。PoHはアンダーワールドで倒したと思うが、生き残りがいる可能性もある。
「ラフィン・コフィンっていうのは、あの死銃たちがいたところよね。」
「ああ、そうだ」
「何かあったら、あたしたちも手伝うから」
「あたしも、できることがあれば!」
「リズもシリカも、ありがとう。それじゃ、予定を合わせてクロスエッジに入ってみよう」
「でも、みんな気をつけてね。危ないと思ったら、すぐに逃げること」
アスナの言葉に、全員がうなずく。その危険性は、みな十分に知っているからだ。
「クラインのヤツには、オレから声をかけておこう。仲間外れにしたら怒るだろうからな」
「ああ、頼むよ」
「クラインさんも今日来ればよかったのに」
「無理を言うな、社会人はまだ働いてる時間だ」
エギルの言葉に、リズが「そうだっけ」とつぶやく。
「そういえば、クラインは働いてたのよねー。時々忘れちゃうわ」
リズの言葉にみんなが笑い、緊張していた空気がほどけた。リズのムードメーカーなところには、いつも助けられてるな。
翌日、俺はアスナとユイと一緒に、クロスエッジの世界へとログインした。最初は俺一人で偵察すると言ったのだが、二人が許してくれなかったのだ。
「さて、クロスエッジはどんなところかな」
最初のログイン画面で、過去にプレイしていたゲームのアバターが選べるようになっていた。《クロスエッジ》も《ザ・シード》を基幹システムとして作られたゲームだ。
《ザ・シード》によって構成された他ゲームのアバターをリスク無く使用できるのが特徴らしい。
「……ん?」
見慣れたアバターたちの中に並んでいたので、一瞬見過ごしそうになった。だが、本来これは、こんなところにあるべきものじゃない。
「ど、どうしてアンダーワールドのアバターが、ここに……?」
アンダーワールド。それは、《ラース》主導で行われたボトムアップ型AI創出計画《プロジェクト・アリシゼーション》によって作られた、電子の中の世界。俺はそこで、実に二年以上の時を――実際の時間は数日だったが――過ごした。そして、大切な親友に出会ったんだ。
だが、このプロジェクトは極秘に進められており、その機密性は国家機密のそれに匹敵するはず。一般企業が運営するゲームに存在するはずがないのだが……。
「よし……なるべく慎重に行こう」
俺は警戒レベルを一段上げ、ゲームをスタートした。
「うわあ、こんなスムーズに動くんだ。モーションも全然違和感がないわね」
「そうだな、これは人気が出るのもわかる」
クロスエッジのロビーで、アスナと二人体を動かしてみる。アスナの言うとおり、モーションもかなり作り込まれている。いろいろなゲームの世界観を楽しめるというだけではなく、ゲーム部分の出来も人気の理由の一つだろう。
「パパもママも、あの時の格好なんですね。ステキです!」
「ふふ、そうね。キリトくんも選んでくるなんて、ビックリしたけど」
ユイが俺たちのアバターを見て嬉しそうに声を上げる。そう、俺たち二人は今、SAOをクリアした時のアバターを使用しているのだ。ログインしてみたらアスナも同じくクリア時の姿で、一瞬アインクラッド時代にタイムスリップしたような感覚を覚えた。ユイはALOでのピクシー姿となっている。SAO時代の少女の姿より、この方がみんなの役に立てる、という理由らしい。
「さて、まずはどうするかな。とりあえずは情報収集か……」
「あ、ちょっと待ってキリトくん」
ロビーを出て街へ向かおうとする俺を、アスナが引き止める。
「たぶんもうすぐ来るから」
「もうすぐ来る? いったい誰が……」
「お待たせしました。こうしたゲームには、まだ慣れていないもので」
「あ、アリス!?」
振り向くと、そこにはかつて見慣れた――リアルの姿でも、ALOのケットシー姿でもなく――金色に輝く整合騎士の鎧を身にまとったアリスが立っていた。
「ううん、全然待ってない。わたしたちも、今来たところだから」
「そうですか。それならよかったです」
「ふふ、わたしが誘ったの。キリトくん、これからしばらくクロスエッジに入り浸る予定でしょう? わたしもリズたちもきっとそうなるし、だったらアリスも呼んじゃおうって」
「そうだったのか……」
「まったく、私を置いていくつもりだったのですか、キリト?」
アリスの眼光が鋭くなる。久しぶりに見たアンダーワールドの姿も相まって、一層迫力がある。
「いや、ホントは俺一人で来るつもりだったんだよ。クロスエッジのこと、何もわからないままじゃ危ないだろ」
そう答えると、アリスの眼光が柔らかくなった。
「水くさいですよ、キリト。そうした危険な場所なら、一人で行くべきではありません」
「そうよね。わたしもそう言ったの」
アリスとアスナが意気投合している。それにユイも同調した。
「皆さんがいれば安心ですね、パパ」
「ああ、そうだな」
実際、その高ランカー狙いのヤツに出会うにしても、あるいはラフコフを探す場合でも、その前にクロスエッジのバトルに慣れなきゃいけない。そういう意味では、実力のある二人と練習できるのは頼もしい。
「アリスはアンダーワールドの格好なんだな」
「ええ、最初のログイン画面……で、この姿を選べるようになっていたので」
「おお、ログインって単語は覚えたんだ」
「あれだけ使っていれば、誰でも覚えます」
アリスはそう言って笑うと、腰の剣を抜いて刀身を愛おしそうに撫でる。
「やはり、この姿の方がいい。本来の私でいられる気がします」
「ああ、やっぱりよく似合ってるよ、アリス」
「キリトも、アンダーワールドの姿になればよいではないですか。修剣学院の制服、似合っていましたよ」
「ありがとう……でも、まあ今回はこっちでいいかな」
さっきまでアスナと懐かしさに浸っていたのに、すぐ着替えるなんてできないからな。
「それじゃ、行こうか。高ランカーのプレイヤーに話を聞けるとベストなんだけど」
「私は、模擬戦をしたいですね。この姿での戦い方を思い出さないと」
「情報収集なら、このロビーの中でもできるかな」
それに……と俺は密かに気を引き締める。アリスが整合騎士の姿を選べたってことは、本格的にアンダーワールドのリソースが使われている可能性がある。用心してもしすぎるということはないだろう。
クロスエッジのロビーは、大勢のプレイヤーで賑わっていた。妖精姿、ミリタリールックなど、様々な世界観のプレイヤーがいる。中には見たことのないようなアバターもいた。基本的に、どのプレイヤーも何人かのグループになっており、ソロプレイヤーはなかなか見かけない。俺が言うのもおかしな話だが、やはりMMORPGはパーティーを組んだ方が有利に進められるし、なにより楽しい。クロスエッジの、様々なワールドが再現されているという特性上、元になったゲームからコンバートしてきたパーティーも多いだろう。
そんな中、一人の女性プレイヤーが気になった。フードを目深にかぶり、じっとロビーの壁にもたれかかっている。待ち合わせにしては、時間を気にしている様子がない。
「ねえキリトくん、あのフードの女の子だけど……」
「やっぱりアスナも気になったか。フード、イコールラフコフではないけど……」
あの視線の動かし方、たぶん何かを探している。それが何なのかはわからないけど。
「あのプレイヤー、ライラさんは現在ランク急上昇中のプレイヤーです」
「えっ、そうなの、ユイちゃん」
「はい。直近のプレイヤーランキングを確認していたのですが、ライラというプレイヤーが急激にランクを上げています」
「なるほどな」
見た目は小柄な女の子だが、実力者というわけか。どうりで身のこなしに隙がないわけだ。
「それと、これはライラさんとは関係がないのですが……」
「どうしたんだ、ユイ」
「ランキングの変動に、少し不自然なところがあります」
「不自然、ですか」
「はい。ランキングがトップクラスに上がった数日後、アカウントを削除するプレイヤーが見受けられます」
「アカウント削除? それは妙だな……」
「それと、同様にトップクラスに上がった後、長期間ログインしていないアカウントも複数あります。現在は後続プレイヤーに抜かれて、ランクダウンしていますが……」
ランキングがトップになった――つまりそのプレイヤーは、かなりクロスエッジをやり込んだことになる。努力を重ねてトップに上り詰めたすぐ後に、いきなり飽きてやめるとは考えにくい。
「いずれにせよ、彼女に話を聞いた方がよいでしょう。向こうもこちらに用がありそうです」
探るように動いていた視線が、いつの間にかこちらに固定されている。明らかに、俺たちを見ている。
「そうだな。向こうもこっちに用がありそうだし」
穏便な用件、とは限らないけどな。
「やあ、ちょっといいかな」
努めて穏やかに、にこやかに話しかけた。だが、相手の表情は少しもにこやかにならない。少し不自然だったかな。
「なんだ?」
「いや、俺たちのことを見ていた気がしてさ、声をかけたんだ」
「……騒いでいたから見ていただけ、ただそれだけだ」
とりつく島もない、という感じだ。だが、なぜか立ち去ろうとする気配はない。
「あのさ、ランキングに載ってる《ライラ》って君のことかな?」
「そうだが……それがなんだ?」
表情がいっそう険しくなる。
「いや、ランカーってことは、クロスエッジに詳しいだろうと思ってさ」
返事はない。ただ、俺の顔を射貫くような目で見つめてくる。
「そうそう、わたしたち今日始めたばっかりなの。それで、できれば話を聞きたいなって」
アスナが助け船を出してくれて、ライラの視線はそちらに向いた。
「自己紹介がまだだったわね。わたしはアスナ。こっちはキリトくん」
「私はアリスです」
そこにアリスも入ってくる。
「聞けば、かなりの腕前とのこと。よろしければ、戦い方を指南していただけませんか?」
アリスがそう言って、腰の剣に手を置く。挑発的とも取れるその言葉に、ライラは素っ気なくうなずいた。

ヒュンッ
ライラの短剣が、鋭く俺の喉元を狙う。両の手に逆手で持たれた彼女の短剣は、常にこちらの急所を狙ってくる。懐に入られると不利だ。バックステップでその斬撃をかわし、距離を取って逆に突きを放つ。
「フンッ!」
「……っ!」
渾身の力を込めた突きだったが、ライラはもう一方の短剣で俺の切っ先を滑らせるように弾いた。そのまま、俺の体が左に流れる。
「くっ……」
体勢が崩れたところにライラが踏み込み、俺の脇腹を切り裂こうと短剣を繰り出す。剣で止めようとしても間に合わない。なら――
「はああっ!」
無理に踏みとどまらず、流されるまま踏み込んで、ライラのかざした右手にタックルをかます。十分に力が乗っていない斬撃は、俺の肩に軽い切り傷を負わせた。
「そこまで!」
ジャッジを務めるアスナの声が上がり、俺たちは剣を納めた。
「さすがだな、ライラ」
「そうでもない。お前たちこそ、すごく凄いじゃないか」
ライラは少し興奮気味にそう言った。
「キリトだけじゃなく、アスナもアリスも、クロスエッジ初心者とは思えない。きっとランクだってすぐに上がると思う」
「ありがとう、ライラさん」
「ライラの剣筋も見事なものでした」
俺の前にはアスナ、アリスとも戦って、どちらもいい勝負だった。ライラの表情も、さっきまでよりずいぶん明るくなっている。これなら、聞いても大丈夫だろう。
「なあ、ライラくらいの高ランクプレイヤーなら知っていると思うんだけど」
「なんだ?」
「高ランクのプレイヤーを狙う奴がいて、そいつと戦うと記憶を奪われるって話、知らないか?」
俺の言葉を聞いた瞬間、明るかったライラの表情が一気にこわばった。
「……噂では聞いたことがある」
「どんな内容の……」
続けて聞こうとした俺の言葉を、ライラの硬く鋭い声が遮った。
「ただの都市伝説だ」
ライラの声には、拒絶の感情がこもっていた。
「天才中学生が開発したって話を聞いて、やっかむ奴が流したんじゃないか……。それ以上、何も知らない」
そこまで言うと、ライラは背を向けて歩き出した。その怒りに満ちた背中を、俺たちは追うことができなかった。
翌日、再びアスナとアリスと一緒に、クロスエッジにログインした。ライラとは気まずい別れ方をしたので、今日は俺たちだけで調べようと思っていたのだが、驚いたことにロビーでライラから声をかけられた。
「今日はどうするんだ?」
「あ、いや……」
昨日あんな別れ方をした以上、もうライラと話をするのは難しいと思っていた。そんな想いが顔に出ていたらしく、ライラは少し気まずそうに目をそらした。
「昨日は、すまなかった。あんな言い方をして」
「いいや、こっちが悪かったんだ。まだ会ったばかりなのに、変なことを聞いて、悪かった」
「いいんだ。わかってもらえれば」
「私は、ライラと共に行動できて嬉しいです。ありがとうございます、ライラ」
「……うん」
アリスの言葉に、ライラがほんの一瞬だけ顔をゆがめた気がする。そこには、申し訳なさのような感情が浮かんでいた。
「なら、今日はクロスエッジを案内しよう。すごく楽しいぞ、クロスエッジは」
だが次の瞬間には、ライラはにこやかにクロスエッジの説明を始めた。アスナもアリスも、さっきの表情には気づいていないようだ。それに、クロスエッジについて話すライラは楽しそうで、嘘をついているようには思えない。
たぶん、昨日のことが気にかかっただけなんだろう。そう結論づけて、街へ向かう三人を追いかけた。
それから数日間、俺たちはライラにクロスエッジのワールドを案内してもらい、イベントやクエストにも一緒に参加した。ライラはクロスエッジについての知識もかなり潤沢で、各ワールドの解説やバトルでのコツ、果てはゲームの設計思想まで教えてくれた。さすがに詳しすぎると思って尋ねると、どうやら知り合いに開発に関わっている人がいるらしい。とにかく、ライラの様子からはクロスエッジへの思い入れが伝わってくる。
その日は、ライラが案内してくれた効率のいい狩り場でひとしきり遊び、そろそろ解散という時間になった。
「……な、なあキリト。ちょっと聞いていいか」
少し言いよどんだ後、ライラが遠慮がちに声をかけてきた。ライラともずいぶん打ち解けたと思ったが、どうしたんだろう。
「なんだ?」
「その……ペインアブソーバー、というのを知っているか?」
「ペインアブソーバー……って、ゲームで使われているシステムの?」
VRMMOの中では、視覚や聴覚はもちろん、嗅覚・味覚・触覚のすべてを現実と同じように感じることができる。だが、100%忠実に再現してしまっては、剣での斬り合いや銃撃戦などできない。いくら死なないとは言っても、死ぬほど痛い思いをするのは誰だって嫌だろう。それを抑制し、肉体や精神に影響がないレベルの痛みを再現するための機能だ。
「そうだ。そのペインアブソーバーで、より強いものがあるって話を知らないか?」
「より強いもの? どんな風に?」
剣呑な雰囲気に眉をひそめながら、アスナが聞き返す。
「本人が本当に斬られた、と錯覚を覚えるほどリアルな痛み」
「本当に斬られた、って……」
アスナと俺は顔を見合わせる。そんなものはない、と言いたいところだが、俺はその痛みを味わったことがある。ALOで、世界樹の上に囚われたアスナを救いに行ったとき、システムコマンドを操るオベイロンによって。あの痛みは、今思い出しても体が震えてくる。
答えられない俺たち二人を、ライラは怪訝そうにうかがう。しばらくして、俺たちの表情から何を読み取ったのか、ふぅっと息を吐いた。
「あくまで噂の話だ、すまなかった。クロスエッジの中で、そんな話を聞いたことがあったんだ」
「そうだったのか。俺たちは、クロスエッジは始めたばかりだからなあ」
「そうね、それより前のことは、よくわからないかも」
「それはそうだよな」
「それで、ただの噂だったんだろ?」
「……運営の調整ミスで、一時的に受ける衝撃が強く設定されていたことはある。もちろん、すぐに修正されたけど」
「マジかよ……」
本来であれば、一番最初に調整しなければならない部分だ。
「そのときに、痛みで人をコントロールさせるとかどうとか、騒ぐ奴がいたんだよ」
「痛みでコントロールなんて、そんなこと……」
アスナの声にも、不安が滲んでいる。痛みによって人を操る……もし事実なら、ラフコフが絡んでいてもおかしくはない。
「つまらないことを聞いたな。それじゃ、今日はこれから人と会う予定があるんだ。すまないがここで」
そう言って足早に去って行くライラの背中を、俺たちは黙って見送るしかなかった。