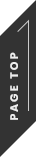キリトたちと別れたライラは、薄暗く入り組んだ路地裏に入ると、奥にある扉をノックする。
「私だ、ライラだ」
「ああ、見えてるぜぇ」
声はライラの後ろから聞こえてきた。慌てて振り返ろうとするが、声が静止する。
「おっと、振り返らなくていいぜ。そのまま話しな」
ライラは言われるがままに動きを止め、目の前の壊れかけた扉を見つめた。最初もこうだった。手がかりを求めて彷徨うライラの背後から、相手はいきなり声をかけてきたのだ。
「で、どうだった? オレの言ったとおりだっただろ?」
「……確かに、何かを知っているような様子だった」
「ほらな、あいつは知ってるんだよ。あの黒の剣士は」
「でもなんで!? ペインアブソーバーのことなんて、運営関係者でもないと絶対知らないはずなのに……」
「あの男は、SAO生還者だ。それに、政府の極秘プロジェクトにも関わってる。だから、知っていてもおかしくはねぇんだよ」
「なら、本当にキリトが……」
ライラは両の手のひらをギュッと握る。
「知ってるだろうな、お前の知りたいことは全部」
「信じられない。キリトもアスナも、そんな風には……」
「別にオレはいいんだぜ。信じなくても、オレは痛くも痒くもねェ」
「でも……それじゃ、キリトたちがやったって、そういう……」
ライラが絞り出した問いに、返ってきたのは悪意のこもった囁きだった。
「だとしたら、アイツを倒さなきゃならねぇな」
「倒せば、わかるのか」
「ああ、そうすればあいつの記憶を探って、アンタの知りたい情報を抜き出してやるよ」
「ほ、本当だろうな!」
「信じなくてもいいんだぜ」
「わ、わかった。もし私が確信できたら、そのときは……」
と決意を固めて振り向いたときには、もうそこには誰もいなかった。落胆と安堵が入り交じった溜め息を吐く。どう考えても、あの男はキリト以上に信用できない。だが……ライラにはそれにすがるしか、方法がなかった。
あれからしばらくの間、ライラとは一緒にならなかった。メッセージを送るのも、なんだかはばかられた。俺たちはランクを上げながら記憶奪取事件や笑う棺桶の目撃情報について調べたが、成果は上がらない。ジリジリと焦れる時間が続いた。
「やっぱり、ただの噂だったのかなあ」
「俺もそう思いたいが、ライラのあの時の様子がちょっと気になるんだ」
「確かに、なんか思い詰めたような表情をするときもあるし、何か知ってるのかな」
今日はアスナと二人で、街をさんざん歩き回った。今は疲れて、カフェで一服しているところだ。
「こうなったら、ひたすらランクを上げて、おびき出すしかないかなあ」
「でも、なかなか時間がかかりそうね。装備も整ってないし」
「そうなんだよなあ……」
事件がないのはいいことだし、これがただの噂だったら、それに越したことはない。ただ、「なにもない」ことを証明するのは難しい。悪魔の証明、というヤツだ。
「……今日のところは、出直すか。ここのところ、ずっとログインしっぱなしだから」
「なんだ、もう終わるのか?」
「うわあっ!? ら、ライラ?」
急に声をかけられて、間抜けな叫びが出てしまった。ライラはそんな俺の顔を見て笑みを浮かべる。
「なんだ、驚きすぎだぞ」
そう言って俺たちのテーブルに腰を下ろし、オレンジジュースを注文した。
「ライラさん、久しぶりね」
「最近、すこし忙しくてな。キリトたちは、ずっとクロスエッジをやってたのか」
「ああ、やっと慣れてきたところだし、バトルも楽しいからな」
これは本当だ。もちろん、ラフコフや記憶奪取関連のことも調べているが、クロスエッジはゲームとしてもよく作られていて、PvPもしっかり楽しめる。それを聞いたライラの顔が、パッと輝いた。
「そうか……それは嬉しいな。ありがとう」
ライラは、まるで自分が褒められたようににっこりと笑う。
「そういえば、ライラはクロスエッジの関係者と知り合いなんだっけ」
「……ああ、そうなんだ」
ライラの顔から笑顔が消え、目が伏せられる。
「知り合いというか……弟だ」
「お、弟?」
予想外の言葉に、俺とアスナは顔を見合わせる。
「えっ、もしかしてクロスエッジをデザインした天才中学生って……」
「ああ、私の弟……空だ」
「そうだったのか。どうりでクロスエッジに詳しいわけだよ」
まさか、ライラの弟がクロスエッジの開発者だったとは。ザ・シードというプラットフォームがあるとはいえ、これだけのゲームを中学生が作るとは本当に驚きだ。
「クロスエッジのプレイヤーは、みんな楽しそうだし。本当、ステキなゲームだと思うわ」
「うん……ありがとう」
さっきまでの喜びようはどこへ行ったのか、ライラはずっと暗い顔のままだ。もしかして、弟はもうクロスエッジの開発から離れてしまったのか? でも、さっきはあんなに喜んでいたし……。もしかして、俺たちが最初に変な噂のことを話したのが気に入らなかったのか?
「なあライラ……」
「まあ、それはもういいんだ。それより、まだクロスエッジ遊べるのか? だったら、今度はダンジョンに行ってみよう」
ライラは俺の問いを遮って、これまでの重い雰囲気を振り払うように明るい声を出した。そこには、これ以上追求してくれるなと言う拒絶も感じる。無理に問いただしても、ライラとの仲を損ねてしまうだけだろう。
「おお、ダンジョンはまだ行ったことがなかったな。よろしく頼む」
弟のことを聞く機会は、またいずれ来るだろう。そう思い、こちらも明るい声を出して立ち上がった。
「キリトは、これまでどんなゲームをやってたんだ?」
ダンジョン攻略をしながら、ライラが尋ねてきた。
「今はALOメインで、GGOもプレイしたことがある。あとは……SAO、かな」
「SAO……なら、キリトはそこから生きて帰ってきたんだ」
「ああ、アスナと俺は、SAOの生還者だよ」
俺の言葉に、ライラは得心がいったようにうなずいた。
「やっぱりそうなんだ」
「やっぱり? ライラさん、わたしたちのこと知ってたの?」
アスナが怪訝そうに問いかける。ライラは慌てて首を振った。
「いや、ふたりともすごく腕が立つから、きっと厳しいゲームをやってたんだろうって思っただけだ」
「そう……まあ、厳しいゲームであったことは、間違いないわね」
「ああ、本当に生きるか死ぬか、だったからな」
今でも、ふとした瞬間に思い出す。アインクラッドでの、文字通り生死を賭けた戦いのことを。俺とアスナが黙ったのを見て、ライラも目を伏せた。
「二人とも、無事でよかった」
「ああ、ありがとう」
それから、俺たちは黙々とダンジョンの攻略を進めた。最深部まで到達し、いくつかの報酬をゲットする。クリア後、次はライラもまだ行ったことのないエリアに向かうという約束をして、その日は別れた。
翌日、俺とライラとアスナ、それにアリスを加えて四人で例のエリアに向かった。そこは最近新しく拡張されたエリアで、まだ情報が少ないらしい。訪れたプレイヤーのほぼ全員が初見のマップで、さらにはあまり居心地がよくないため誰も深く探索していないとのことだ。
「着いたぞ、ここだ」
ライラに案内されて着いたのは、岩だらけの荒れ地だった。動くものは虫一匹見当たらない。植物も、すでに枯れた朽ち木が何本か立っているだけだった。確かに落ち着かない景色だが、RPGのフィールドとしては珍しいものではない。
だが……俺はこの景色に強烈な既視感を抱いていた。どこまでも続く、荒涼とした景色。土埃を含んだ重い風。生存に適さないよう、意図的にデザインされたその大地は――。
「ねえキリトくん……ここって」
「なぜ、この世界がここに……?」
アスナもアリスも、俺と同じことを考えているようだ。ゲームのフィールドとして存在するはずのない世界。
「ああ、ここはアンダーワールドだ」
「どうしたんだ、三人とも黙り込んで」
「……いや、ちょっと見たことがある風景にすごく似ていて、驚いたんだ」
予想すべきだった。アバター選択時に、俺とアリスはアンダーワールドの姿を選ぶことができたのだから。だが、まさかフィールドが再現されているとは。
「見たことがある風景? このフィールドは、誰も知らなかったんだぞ」
「ああ、そうだと思う。誰も知るはずがないんだ」
「………………」
俺の口から漏れたつぶやきに、ライラの眼光が鋭くなる。しまった、言い過ぎたか。ライラにはどうやって説明を……。
「キリト、後ろです!」
「なっ……!」
アリスの警告が聞こえ、とっさに前へステップする。同時に剣を抜き、振り返って戦闘態勢を取った。同じく、アスナとライラもすでに武器を構えている。
「グルルル……」
俺たちを襲った相手は、人間よりもやや小柄で、緑色の皮膚をしていた。錆びた剣を握り、こちらに向かってうなり声を上げている。
「これは……」
アンダーワールドに存在したゴブリン族。ユージオと共に、果ての山脈で戦った相手と同じ姿だ。まさか、こんなところまで……。
「キリト! 考えるのは後です!」
アリスの鋭い警告が飛び、意識が正常に戻る。ゴブリンの数は五体。油断していい相手じゃない。
「……どうしたんだ、何か気になることでもあったのか?」
ライラは何かを探るように尋ねてきた。
「いや、なんでもない、大丈夫だ。行くぞ!」
予想に反して、ゴブリンの強さはそれほどでもなかった。アンダーワールドのゴブリンはフラクトライトを持ち、各個体ごとに個性があった。さすがにそれは再現されていないようだったが、モンスターを倒すのとは違う罪悪感があった。
「………………」
「このエリアについて、何か知っているのか?」
最後のゴブリンを倒し、俺とアリスが立ち尽くしていると、ライラが硬い声で尋ねてきた。そこには、不審と疑念が混じっている。
「このエリアと、今のモンスターについて……お前は何か知っているんだな」
「あ、ああ……少し、見たことがあるんだ」
アンダーワールド事件は機密扱いで、うかつに口外しないよう言われている。俺自身も、あの世界で起きた色んな出来事を、軽々しく人に話すことはできない。
「そうか……やはり知っているんだな。他の誰も知らない事実を!」
ライラの声に、強い怒りがにじむ。俺をにらむ目は、まるで憎い仇を見ているようだ。
「ライラ、いったいどうした……」
「ミハエルを返せ! そして、このクロスエッジを元のゲームに戻せ!」
「うおっ……!」
ライラが振り回した短剣を、かろうじて受け止める。ぶつかっている刃同士がギギッとイヤな音を立て、ジリジリと押し込まれた。ライラにこんな力があるとは……。
「はっ!」
なんとか刃を受け流し、体勢を整えようとする。だがその隙も与えず、ライラは連続して短剣を繰り出してきた。そのひとつひとつが、受け損なえば致命傷になり得る。
「キリトくんっ!」
「やめるのです、ライラ!」
アスナが俺たちの間に割って入り、アリスは体をぶつけてライラを止めようとする。だが、クロスエッジのゲーム内ではライラの方が一枚上手だ。アリスの体当たりを紙一重でかわし、割り込んできたアスナの方へ押し出す。二人は衝突して、そのまま倒れた。
「アスナ! アリス!」
どうして、こんなことになってしまったのか。わからないことだらけで、頭が混乱している。だが、このままライラに斬られるわけにはいかない。ゲームの中とはいえ、クロスエッジには不穏な噂がある。俺自身、そしてアスナとアリスを守るためにも、ここは……。
「……戦うしかない」
腰の剣を抜き、ライラに対峙する。ライラの憎しみのこもった視線が、いっそう強くなった。
「ぜったい聞き出してやる。ミハエルを救うためにも」
どのくらい戦っていただろう。高ランカーであるライラに対して、手加減などできない。気がつけば、ライラが目の前に倒れていた。あちこち傷だらけで、ダメージも大きい。それはアスナとアリスも同じだった。
「……大丈夫か、二人とも」
「ええ、キリトも大丈夫ですか」
「俺は平気だ。だが、ライラは……」
「……気を失っているだけみたい」
アスナの声に安心したら、疲労感が一気に襲ってきた。肉体の疲れに加えて、ライラへの疑問、二人を巻き込んだ罪悪感、クロスエッジにまつわる不穏な話……思考がショートし、視界がぐらっと揺れる。倒れそうになったところを、誰かの手に支えられた。
「おっと、大丈夫かいキリト?」
「ああ、大丈夫だ。ちょっと疲れただけ……」
その声に、俺はひどく安心した。長い間、ずっと支えてくれた存在。こいつがいれば、俺はまだ戦える……。
アスナとアリスが、息をのむ音が聞こえた。その瞬間、うつろになっていた意識がクリアになる。
目を開けると、俺を見る濃いグリーンの瞳と、亜麻色の髪が目に入った。
「え……」
見間違えるはずもない。そこにいたのは……ユージオだった。
「ゆ、ユージオ……?」
「ああ、平気そうだね。安心したよキリト」
「……………」
驚きで声が出ない俺をおかしそうに見つめる。
「ユージオ、なのですか……本当に?」
「この人が、ユージオ……」
アスナとアリスも、驚きでそれ以上言葉が出ないようだ。だがユージオは、そんな俺たちを気にする様子もなく、倒れているライラの傍らにしゃがみこむ。
「目の前で倒れている子を放っておくなんて、キリトらしくないんじゃないかな」
「……ああ、そうだな。すまない」
クロスエッジに流れていたもう一つの噂……死者に再会できる。少なくとも、その噂は真実だったのだ。