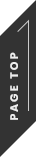なぜ、ユージオがクロスエッジに。死者に会えるという噂は本当だったのか。もちろん俺は信じていなかったが、目の前にいるのはまぎれもなくユージオだ。いつものように俺に笑いかけている。
「まったく、驚きすぎだよキリト」
「あ、ああ……すまない」
しゃべり方も、俺の記憶にあるユージオそのままだ。熱くなった目頭を悟られないよう伏せる。
「とにかく、落ち着ける場所にライラさんを運ばないと」
「そうですね。なぜ襲ってきたのか、理由を確かめないと」
アスナとアリスの声で、ようやく今の事態を思い出す。ユージオとの出会いで全てが頭から飛んでいたが、ライラに襲われたという事実も十分に衝撃的だった。
「その子を運ぶんだね。僕も手伝うよ」
「ありがとう、ユージオ」
こうやって普通にしゃべるのも久しぶりだな、などということを考えながら、俺たちはライラを街へ運んだ。

街外れにある、人の少ない広場へライラを運び、寝かせる。幸い、ライラはほどなくして目を覚ました。また襲ってくるのでは、と警戒したが、そんな様子はなかった。
「……ここは?」
「町外れの広場だよ。大丈夫、安全な場所だ」
「そうか……」
ライラは顔を伏せると、ギュッと拳を握りしめた。
「私を……助けたのか。お前たちを襲ったのに」
「まあ、大きな怪我もなかったしな。何か事情があったんだろ?」
あえて軽い口調で返事をする。それを聞いたライラは顔を上げて俺の目をじっと見つめた。やがて、ぷっと軽く吹き出す。
「お人好しだな、キリトは」
「それにかけては、人界一かもしれないね」
「お前だけには言われたくないな、ユージオ」
ユージオの言葉に、アスナとアリスも笑い出す。ライラは不思議そうにユージオを見つめた。
「ライラ、こいつはユージオ、俺の相棒だ」
「ユージオ……」
ユージオの姿をしばらく見つめていたが、やがてライラは自分を納得させるように、
「……いや、なんでもない」
とつぶやいた。
「では、話してもらいましょう。なぜ我々を襲ったのですか、ライラ」
「……私に弟がいる、という話はしたよな」
「ああ、確かクロスエッジを一人でデザインしたっていう……」
「なんと、この世界を一人で、ですか」
アリスが驚きの声を上げる。その一瞬、ライラの目が優しくなった。
「弟……空は、ずっとVRの可能性を追い求めて、研究していた。そして、あるシステムを考えついた」
「VRの可能性……?」
アスナのつぶやきに、ライラは自分の頭を指さす。
「キリトならたぶんわかると思うが、フルダイブ型のVRゲームは、脳にデジタルデータが送受信されることで成立している」
「ああ、それは知っているけど……」
システムが脳とダイレクトにつながることにより「フルダイブ」という体験が可能となる。これによって、視覚や聴覚だけでなく味覚や嗅覚、触覚までもVR内で感じることができるのだ。
「脳にデジタルデータを送り込めるということは、同時に脳の記憶データを引き出せる可能性がある」
「記憶が……引き出せる?」
まさか、俺の記憶も……?
思わずユージオに目向ける。ユージオは相変わらず、優しく微笑んでいる。
「もしかして、幽霊に会えるって……」
アスナの声には、少し震えが混じっていた。
「そう。失った大切な人やペットと、VR世界でなら再会できる。それが空の考案した《思い出システム》なんだ」
それほど大きくないライラの冷静な声が、轟音のように耳に響いた。
過去にも、AIとARを利用して亡くなった人を再現する試みは行われてきた。どれだけリアルに再現できるかは、亡くなった人のデータ量が肝要だ。もしフルダイブの技術を応用して、記憶から情報を引き出せるなら、これまでよりずっと正確な再現が可能だろう。

「私たち姉弟は、早くに両親を亡くしていて……家族と呼べるのは、お互いとずっと一緒にいてくれた子犬だけだ。その子も、もういなくなっちゃったけど。空は、その子犬ともう一度会いたくて、このゲームを造り上げたんだ」
「そうだったのか……」
失われてしまった大切な存在に、もう一度会いたい……と言う気持ちは、俺にも痛いほど理解できる。
「完成に目処がついたころ、注目した会社がもっと大きなサーバーで実行しようと誘ってくれて、クロスエッジは今の大規模な形でリリースすることができた。でも、その会社がエプシロンという会社に買収されて、状況が一変した」
ライラの声に怒りがこもる。エプシロンは、現在のクロスエッジの開発会社だ。ログインする前に少し調べたが、VR関連の事業を幅広く展開していた。
「クロスエッジの運営は、エプシロン日本支社長の江利川という男が指揮を執っていた。江利川は空に、記憶をもっと正確に読み取れるようにしろ、と何度も言っていた。そしてある日、空は江利川に呼び出されて……そこで何かが起こったんだ」
「何か……というのは?」
アリスが尋ねるが、ライラは首を振った。
「わからない。ただ、空が入院したという連絡が来て、病院に行ったら……空は意識不明になっていた。脳波は正常なのに、いつ目を覚ますかわからないって……」
「脳波は正常? それってSAOの……!?」
アスナが驚いて俺を見る。俺も、アスナと同じことを考えていた。
「もしかして空は、ゲームに……」
「うん。空はミハエル、というプレイヤーネームでクロスエッジをプレイしているんだけど、調べてみたら、江利川と会っている時間にクロスエッジへアクセスした履歴があった。しかも、ログアウトしていない……空は、ゲームに囚われているとしか思えないんだ……!」
「それで、俺たちを……」
「そうだ。キリトはSAOに閉じ込められ、帰還した生還者。だから、戻る方法を知っているはずだ……そう、あの男が教えてくれたんだ」
「あの男? そいつは……」
もしかしてラフィン・コフィンと関係が……と思ったが、そこまで言うとライラは泣き崩れてしまった。
「キリト……お願い……弟を……空を助けて……」
その日はライラが落ち着くまでなだめ、詳しい話はまた後日ということになった。俺自身、ユージオとの再会の衝撃で動揺があり、冷静に聞くために時間が欲しかったところだ。ユージオとは、普通に「それじゃまた明日ね」と別れたが、あのゲームの中でユージオはどういう存在なのだろうか。
翌日、ダイシーカフェでエギルに会い、例の亡くなった恋人を探しているプレイヤーに連絡を取ってもらうことになった。それと、ユイにもクロスエッジについての調査をお願いした。人間の脳にアクセスして記憶情報を抜き出すために、アミュスフィアのセーフティ機能をいじっている可能性がある。SAO事件のようなことは、二度と繰り返してはいけない。
「おはよう」
アスナとアリスと待ち合わせて、クロスエッジにログインする。入ってみると、ライラはもうロビーサーバーに来ていた。疲れた様子はあったが、先日よりもずいぶん落ち着いたようだ。
「おはよう。この間は……すまなかったな」
「気にするなって」
「そうよ、もう友だちなんだから」
アスナの言葉に、ライラが一瞬きょとんとした表情を見せる。これまでの張り詰めた様子より、ずいぶん子どもっぽく感じた。いや、それが本来のライラなのかもしれない。
「そ、そうか……友だち、か」
ライラが照れたように笑う。釣られてこちらも笑顔になる。
「ところで、キリト。ユージオは今日も来ているのですか」
「ここにいるよ、アリス」
背後からユージオの声。まるで、アリスの言葉に反応して現れたかのように。ライラは、そんなユージオを見て何かを悟ったような表情をしていた。
「……今日は、この前詳しく話せなかったことを話そうと思う。具体的には、MRSのこと」
「MRS?」
「正式名称は、Memory Reading System。空が考案した、思い出システムのことだ」
記憶を読み、思い出を再現する。それを中学生が設計・開発したというのは、やはり驚くべきことだ。
「MRSはフルダイブ型のMMOが信号を脳に直接働きかけるシステムを使って、記憶領域にアクセスする。それを元に、クロスエッジ上に記憶を再現するのが思い出システムだ。詳しい内容は、弟やエプシロンの技術者じゃないとわからないけど」
「なるほどな……」
なんとなく、オーグマーを開発した重村ラボの研究に似ているな。あちらも、ゲームプレイヤーたちの記憶からデータを集めて、あるプレイヤーを再現……いや、再生しようとしていた。
「それで、他のゲームのアバターやフィールドが、とても高いクオリティで再現されているのね」
アスナは驚いた様子だったが、ライラは不満げに首を振る。
「それは、エプシロンが手を加えた思い出システムの副次効果だ。表向きは、ザ・シードのデータ共有の応用だとなっているけど……でも、今のクロスエッジは私たちが思い描いていた思い出システムの規模を遙かに超えている。これじゃ、生きている相手であっても、その人の意志と関係なく会えてしまう。それが、空の望んだクロスエッジとは思えないんだ……」
ライラの声には、悲しみと悔しさがこもっている。それだけ、弟が作ったクロスエッジを大事に思っているということだろう。
だが、そのおかげで、俺はユージオと再会できた。どんな形であれ、それが嬉しかったのは間違いない
「まあ、あながち悪いことばかりでもないさ。君の弟が考案したシステムのおかげで、大切な人に会える人だっているんだから」
不器用な慰めになってしまったが、俺の言葉に実感がこもっていたのを悟ったのか、ライラは少し笑顔になって「ありがとう」と言ってくれた。
「それでこのMRSなんだけど、エプシロンは自分たちが元々持っていたシステムを、MRSと融合させるという計画を持っていた。空は乗り気じゃなかったけど」
ここで、昨日から気になっていたことをライラに尋ねた。
「そういえば、どうして開発がエプシロンに変わったんだ?」
「前の会社……マシバの社長が、突然通知してきたんだ。資金繰りの問題で、エプシロンに全てを委譲するって。空は何も聞いていないって言っていた」
「いきなり、開発者の確認もなく……か」
「そのときのマシバの社長は、なんというか……ちょっとおかしかった。いつもは冷静なのに、あの日は妙に高圧的で。こちらの言うことなんて聞かずに、決まったことだからって」
「うーん、それもなんだか妙な話だな。それまではうまくいってたんだろ、マシバとは」
「大きなトラブルはなかった。私たちもマシバのことは信頼していたし……今考えると、あの社長の変化も、おかしかったな」
もしかして、空の失踪と社長の変貌は、関係があるのかもしれない。
「空さんが呼び出されたのは、その話について?」
アスナの言葉に、ライラは頷く。
「協力を断りに行ったはずだ。でも、クロスエッジにログインして、そのままログアウトしてこない。私が一緒に行っていれば……」
「あなたのせいではありません、ライラ」
アリスがそっとライラの肩に手を置く。ライラはあふれそうになる涙を拭って、アリスに笑い返した。
「エプシロンからは、会議中にログインしたまま、行方がわからないと連絡があった。だから、ゲームの中を探し回って……でも見つからなくて。そうしたら、フードをかぶった男が話しかけてきたんだ。弟を救う方法を、教えてやるって」
「フードの男……か」
「キリトはSAO生還者だから、弟を救う方法も知ってるはずだ、それを聞き出せって」
「そうだったのか」
そいつがラフィン・コフィンと決まったわけじゃないが、フード姿というのはあの男――PoHを連想させる。それに、俺がクロスエッジにログインしたことをなぜ知っているのか、気になるところだ。
「一つ、気になることがあります。ライラは、探し人の似顔絵を配ったりしたのですか?」
「いや、そんなことはしていない。事件かもしれないから、空のことはあんまり話してないし……」
「ならば、なぜその男はライラの弟を知っていたのでしょう」
「えっ……」
ライラがハッとしてアリスを見る。
「そうか、確かに……空を探すのに必死で、そんなことにも気がつかなかった……。私、そんなことでキリトたちを……」
「仕方ないわ。それくらい弟さんが心配だったってことだもの。わたしだって、大切な人がそうなったら、ライラさんと同じようになると思うわ」
謝ろうとするライラをアスナがなだめる。アリスも頷くと、さらに言葉を続けた。
「今までのライラの話から推測すると、空の失踪にはエプシロンが関わっている。そして失踪のことを知っているのも……」
「エプシロン……つまり運営元ってことか。フード男も、運営側の人間かもしれないな」
「それじゃ、運営側がキリトくんを狙わせたってこと? 大丈夫なの、キリトくん……」
アスナが心配そうに俺を見る。
「ああ、十分気をつける。みんなも油断しないようにな」
ライラの弟を失踪させ、さらに俺のことを狙う。相手の意図はわからないが、危険であることは間違いない。それに、ライラが言う「エプシロンが持っていたもう一つのシステム」とは、なんだろう。わからないことだらけだが、注意するに越したことはない。引き続きライラの弟を探す手伝いをしつつ、クロスエッジの運営についても調べるという方向で、ライラとは話をまとめた。
「ところでキリト、僕は途中から話を聞いていたから、よくわからないんだけど……あの女の子は、弟さんを探しているんだよね」
話が一段落したところで、それまで黙って聞いていたユージオが口を開いた。
「ああ、空っていう名前だ。この世界のどこかにいる可能性が高いらしい」
「それなら、僕も手伝うよ。姉弟の行方がわからないなんて、心配だもんね」
「助かるよ、ユージオ」
こういう、優しいところも変わらないな。そう思ってユージオを見ていると、ユージオが赤くなって顔をそらす。
「どうしたんだよ、キリト。この間から僕の顔をよく見てるけど」
「いや、悪い悪い。久しぶりでも、ユージオは変わらないなって」
「まったく、ちょっと変だよキリトは。そんなんじゃ、剣の腕もなまってるんじゃないのか?」
「そんなことはないって。だったら手合わせしてみるか」
「望むところだよ、キリト」
そんな俺とユージオの会話を、アリスが微笑ましそうに見ている。手合わせならアリスも挑んでくるかと思ったが、その様子もないようだ。
「よし、それじゃ場所を変えるか!」
ユージオと連れだってロビーを出る。向かう先は、街にある試合場だ。対人戦を推奨しているクロスエッジには、こういう模擬戦用の試合場がいくつもある。
当然と言えば当然だが、アスナとアリス、ライラも一緒についてきた。ユージオとはいつも二人だったから、こうしてみんなで行動するとちょっと変な感じがするな。
「使うのは、練習用の剣じゃなくていいよな?」
「もちろん。この剣の方が、使い慣れているからね」
ユージオは青薔薇の剣を抜く。その輝きは、アンダーワールドで見たのと変わらない。
「そうこなくっちゃな。よし、始めるか」
「いつでも」
試合場の中央で、お互いに剣を構える。開始の合図をする審判はいない。だが、高まる緊張感の中で、お互いの呼吸がそろう。
「おおおっ!」
「――っ!」
完璧に同じタイミングで、右上からの上段切りを繰り出す。はげしく激突して刃が弾き返される。もう一度、今度は正面から振り下ろすが、これもユージオの剣に阻まれた。続くユージオの喉を狙った突きを剣の鍔元でそらし、体勢の崩れたところを横からなぎ払う。だが、ユージオはバックステップして攻撃をかわした。
「剣の腕は鈍ってないようだね、キリト」
「そっちもな」
短く言葉を交わすと、再び俺たちは気合いと共に剣を繰り出した。
何合、剣を合わせただろう。お互いに効果的な攻撃はヒットしていない。だが、少しこちらが押され始めた。
――強くなっている。
ユージオと本気で刃を合わせたことはそれほど多くない。それでも、ユージオの動きの鋭さ、重さは体が覚えている。しかし、今のユージオは、過去のそれを上回る強さだと感じる。劇的に何かがかわったわけではないのだが、攻撃の精度や力強さ、動きの俊敏さが一段パワーアップしている感覚だ。
長期戦は不利だな。
ユージオの攻撃は激しく、すでにこちらの余裕が失われ始めている。このまま行けば、どこかで致命的な一撃を食らってしまうだろう。覚悟を決めて、早期決着を狙う。
「はああっ!」
ユージオが上段から重い一撃を繰り出してきた。それをガードし、そのままつばぜり合いに持って行く。刃が押し合う、こすれるような音が響く。足を踏ん張り、渾身の力を込めて剣を押すと、反発して、ユージオが押し返してきた。それに合わせて剣を引き、ユージオから距離を取る。
「さすがだな、ユージオ」
「君もね、キリト」
「だけど、今回は俺が勝たせてもらう!」
ユージオが距離を詰めてくる前に、俺は左手にもう一本の剣を装備した。アンダーワールドではユージオに見せたことのない、《二刀流》スキル。それなら、ユージオに勝てるかもしれない。
「両手に剣だって!?」
驚いて声を上げるユージオに、頭を下げて突進する。ユージオは当然防御姿勢に入るが、かまわず両手の剣で連撃を放つ。
「うおおおおっ!」
「くっ……は、早い……!」
俺の連撃がガードを崩し、ユージオの体がよろめいた。そこに左手の剣がヒットする。
「ぐっ……」
続いて右手の剣が攻撃モーションに入ったとき、ユージオが両手を挙げた。
「参った。僕の負けだよ、キリト」
荒い息を吐く俺とは対照的に、ユージオにはまだ余裕があるように見えた。
「やっぱりキリトには敵わなかったね」
「いや、最後は危なかった。修剣学院のときみたいに、剣一本で勝負していたら負けてただろうな」
「でも驚いたよ。《アインクラッド流》には、両手に武器を持つ型もあるんだね」
「ああ、前には見せるタイミングがなかったけどな」
自分でも言ったとおり、二刀流のスキルがなかったらユージオには負けていただろう。さらに、これはユージオが二刀流のことをまったく知らなかったから効果的だったのだ。次に戦ったら、どうなるかわからない。
「二人ともお疲れ様。いい勝負だったわね」
「ええ、見事な戦いでした」
「強いんだな、キリトもユージオも」
アスナたちがねぎらいの言葉をかけてくれる。
「アリスは、ユージオと戦ったことがあるのよね?」
「剣を交えたのは数回ですが。でもカセドラル最上階では共に戦いました。そのときのユージオの強さは、今でも私の記憶にはっきりと残っています」
アリスの記憶、か。
もしかしたら、その記憶がユージオの強さの原因かもしれない。ライラの話によれば、クロスエッジにいるユージオは俺たちの記憶を元に存在している。俺は、ユージオがもしこのまま成長したら、俺を超える剣士になっていただろうと思っていた。そしてアリスは、カセドラルでの壮絶なユージオの戦いを見ている。それが相まって、当時の力を超えた強さを持っているのかもしれない。
「どうしたんだい、キリト。ニヤニヤして」
「え、笑ってたか?」
「うん」
そうか、俺はユージオが強いことが嬉しいんだな。
「よーし、次も負けないからな!」
「それはこっちの台詞だよ。今度こそ一本取ってみせる」
「本当に仲がいいですね、二人は」
アリスが、こちらも少し嬉しそうにつぶやく。アスナはそんな俺たちを微笑ましそうに見ていた。
クロスエッジをログアウトした後、ダイシーカフェに向かう。エギルから、集めた情報の報告をしたいと連絡があったのだ。ちょうどユイからも話したいことがあるとのことなので、一緒に確認することにする。
「入院って……例の亡くなった恋人を探していたプレイヤーが?」
「ああ、精神的に参ってしまったらしくてな。会える状態じゃないそうだ」
「そうか……恋人に会えたかどうかは、わかったのか?」
「いや、それもわからん」
「そうか……」
そのプレイヤーが、なぜ入院したのかは気になる。俺たちも、実際にユージオに会っているからな……。
「それと、気になる情報があった。運営がエプシロンに変わったとき、新システムのベータテストがあって、それがひどかったらしい。すぐ終わったんで、参加したプレイヤーは少ないみたいだが」
「ひどかったって、どういうことだ?」
「敵に攻撃されると、ゲームとは思えない強烈な痛みを感じたらしいんだ。中には、激痛で気を失ってそのままログアウトしたプレイヤーもいたらしい」
「強烈な痛み……ペインアブソーバー、か」
ライラが探っていたのは、このことか。
「痛みのショックでリアルの生活にも支障が出るほどだったそうだ。医者に診せても、異常はなかったらしいが」
「しかし、なんでそんなことを……」
そんな痛みがあってはゲームとして成立しない。そんなことは、テストをするまでもなくわかることだ。
「私の方もいいですか、パパ」
「ああ、頼むよ、ユイ」
「アミュスフィアについては、通常の故障以外の異常報告は見つかりませんでした」
「そうか……なら何かあるにしてもソフト側ってことだな」
「それと、エギルさんのお話にも関係あるかもしれないんですが……アミュスフィアによる体調不良者を調べていたとき、クロスエッジからかなり多くの体調不良報告が上がっているのがわかりました。ある一定の時期に、20人以上が集中して体調不良に陥っています」
「ある時期って、もしかして……」
「先ほどエギルさんのお話を聞いて、時期を調べてみたんですが、ベータテストのタイミングと一致します。いずれも強い痛みを訴えており、入院措置が必要なプレイヤーも4人いたとのことです」
「そんなにいたのか……」
エギルもショックを受けて頭を振る。ダイシーカフェの常連にもクロスエッジプレイヤーがいると聞いていたし、心配だろう。
「キリト、俺から振った話だが……手を引くという選択肢もある。ユイの話を聞いた限り、かなり危険だ」
「そうだな。だが、フードの男のこともわかっていないし、何よりライラの弟も心配だ。もう少し調査を進めたい」
「それなら、私もパパのお手伝いします!」
「ありがとう、ユイ」
「仕方ない、オレもできる限り情報を集める。くれぐれも用心しろよ」
「ああ、エギルにも頼らせてもらうよ」
ペインアブソーバーのことは、明日にでもライラに話してみよう。