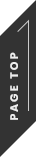クレハが指定してきた《ドーム》というのは、オールドサウスシティの西の端に存在する、巨大なスタジアムめいた建築物だ。ファストトラベル・ポイントに設定されているのに、なぜか中に入ることはできない。
ぼくとアファシスがワープしたのは、ドーム東側の広場だった。巨人を見物しにきたプレイヤーがひしめいているだろうと思ったが、周囲に人の姿はない。視界内で動くものは、すぐ前の幹線道路をうろつく球形の浮遊砲台型エネミーだけ。いまのぼくたちの敵ではないものの、戦う意味もないのでターゲット範囲に入らないよう気をつけつつドームを南側から回り込み、裏手に出る。
途端――。
「わあ……いっぱいいるのです!」
とアファシスが控えめな声で叫んだ。
その言葉どおり、ドームの西側には、千人を軽く超えるであろうプレイヤーたちが密集している。そのわりに静かなのは、ほぼ全員が唖然とした表情で西の空を見上げているからだ。
ぼくも同じ方向に目を向ける。まず視界に飛び込んできたのは、丘陵地帯の奥にそびえ立つ二本の柱――金色の鎧に包まれた巨人の両脚だ。そのまま見上げていくと、太ももから腰周りまではどうにか視認できるが、そこから上は灰色の空に紛れて見分けられない。何せ、本当に身長が千メートルもあるなら、東京スカイツリーの一・五倍以上にもなる計算だ。
改めて、信じられないほど大きい。立っている場所はマップ外のはずなのに、まるでぼくらの頭上にのし掛かってくるかのようだ。いったいあのおじさん、いや巨人は何者なのか。
そんなことを考えながら立ち尽くすぼくの左腕を、誰かが軽くつついた。
見ると、立っていたのは髪とコスチュームの色をピンク系で統一した女性プレイヤーだった。ぼくをここに呼び出した幼馴染のクレハだ。
「この人数の中からよく見つけたね」
小声で話しかけると、クレハは何度か瞬きしてから答えた。
「あんたじゃなくてレイちゃんを見つけたのよ」
「なるほど……」
確かに、アファシスの銀色の髪はGGO世界の弱々しい陽光の下でもよく目立つ。戦場ではフード系のアクセサリーで隠していることが多いのでいっそ色を変えてしまえば……と思うが、本人はこの髪色が気に入っているようだ。
そのアファシスは、目と口をぽかんと開けて黄金の巨人を見上げている。ぼくは再びクレハに視線を移し、訊ねた。
「それで、何の用なの?」
「何の用って……決まってるでしょ、アレよ」
左手の親指で巨人を示したクレハは、音量を限界まで落とした囁き声でまくし立てた。
「あのでっかいの、どう考えてもゲリラレイドイベントのボスエネミーでしょ。あたしたち、SBCフリューゲルもホワイトフロンティアも攻略一番手だったんだから、今回も狙っていくわよ」
「ええー……」
思わず上体を引いてしまう。どうやらクレハは、HPが何十億、へたをすると何百億あるか解らないあの巨人を倒すつもりらしい。
倒すと言っても、もちろん他のプレイヤーたちが黙って見ているはずもないので、ぼくたちのパーティーで最大ダメージを与えるという意味だろうけど、それだって容易なことではない。いままでいくつかのクエストを一番手でクリアしてきたのは確かだが、それは攻略を手伝ってくれたキリトチームの圧倒的な火力があったからだ。でもキリトたちはしばらく前から古巣の《アルヴヘイム・オンライン》に戻っていて、いまはこの世界にはいない。
という弱気な考えを見抜かれたのか、クレハはもう一度ぼくの左肘のあたりを、少し強めに小突いた。
「あのねえ、あんただってもうれっきとしたGGOのトッププレイヤーなのよ? キリトさんたちがいなくてもやる時はやるんだってこと、ごちゃごちゃ言ってる連中に見せつけてやらなきゃ」
「えーっと……」
クレハが言う《連中》というのは、ぼくのことを「しょせんキリトの腰巾着」などと腐している一部のプレイヤーのことだろう。実際、キリトやアスナの手助けがなければ倒せなかったボスエネミーはたくさんいるのでぼくは気にしていないが、代わりにクレハが腹を立ててくれていたらしい。
その気持ちはありがたいけど……と思いながら、ぼくは小声で言い返した。
「まず、あれが本当にレイドボスかどうかもまだ解らないし、たとえそうでもぼくとクレハ、アファシスの三人じゃ、与ダメレースで一位になるのは無理だよ……」
「それくらいのこと、あたしが考えてないと思ってんの?」
不敵な笑みを浮かべ、クレハはいっそう声を低めて続けた。
「もちろん、助っ人を呼んでるわよ」
「え……誰を?」
「それは来てのお楽しみ。ともかく、いまのうちに最大ダメが出せる装備にチェンジしておいて」
「はいはい……」
観念し、ぼくはウインドウを開いた。少し考えてから、メインアームを最近入手したばかりの対物スナイパーライフル《AMRブレイクスルー4》に、サブアームを実弾系ハンドガンの《ロングストロークType-Z》に交換する。二箇所装備できるアクセサリーは、どちらもスキルのリチャージ時間短縮効果がついたものを選ぶ。
続いてアファシスの装備も、火力重視のセットに変更させようとした、その時。
いままで無言で金色の巨人を見上げていたアファシスが、一度瞬きしてからぼくに顔を向け、言った。
「おかしいのです、マスター」
「おかしいって、何が?」
「いま、お母さんと話していたのですが……」
それを聞き、ぼくはクレハと顔を見合わせた。
アファシスが言う《お母さん》とは、忘却の森エリアに停泊している巨大宇宙戦艦《SBCフリューゲル》のマザーコンピュータ、その名も《マザー・クラヴィーア》のことだ。メインシナリオが一段落して以来、クエストに絡んでくることはほとんどなかったのに、なぜいま、このタイミングで――。
「レイちゃん、お母さんがどうかしたの?」
クレハに促され、アファシスはもう一度巨人を見てから囁いた。
「わたし、お母さんに頼んであのおじさんの正確な大きさを計測してもらおうとしたのですが……SBCフリューゲルの三次元イメージングレーダーでは、おじさんを観測できないようなのです」
「え……?」
クレハと同時に首を傾げる。
ずっとダイブしていると忘れそうになってしまうが、ここは現実世界ではなく仮想空間――ゲームの中だ。だからレーダーと言っても、実際にSBCフリューゲルのアンテナから電波が発射されているわけではなく、マザー・クラヴィーアのリクエストに応じてゲームシステムがオブジェクトの位置や形状のデータを返しているに過ぎない。
つまり、フリューゲルに観測できないなら、あの巨人はただの立体映像で実際には存在していないか、もしくはシステムに不具合が発生しているということになる。
似たようなことを考えたのか、クレハが呆然とした顔で巨人を見上げながら呟いた。
「……あんなにはっきり見えるのに、実在してないなんてことある……?」
「うーん……」
身も蓋もないことを言えば、仮想世界なのだからなんでもあり、ではある。現実世界には、あそこまで巨大かつ精細な立体映像を真っ昼間の青空に投影する技術はたぶん存在しないが、この世界ならゲーム管理者の匙加減ひとつで……。
「……あ」
そこまで考えたぼくは、小さく声を漏らした。
あの巨人が何なのかを調べる方法が、あると言えばある。フレンドプレイヤーのツェリスカに訊くのだ。GGOを運営している企業、《ザスカー》日本支部の社員である彼女なら、これがシステムの異常なのか、それとも正規のイベントなのか知っているはず。
普段のツェリスカは仕事と遊びをきっちり線引きしていて、よほどのことが起きないかぎり社員としての権限をゲームプレイ中に行使することはないが、今回のこれはよほどのことだと判断していい気もする。何せこのGGOでは、《死銃事件》や《リエーブル事件》といった、ゲームの枠を逸脱した騒動が何度も起きてきたのだ。
「ねえ、何か思いついたの?」
もどかしそうな顔のクレハにそう訊かれ、ぼくはツェリスカの名前を口にしようとした。
しかし、その寸前――。
「マスター!!」
悲鳴のようなアファシスの声に、大勢のどよめきが重なった。
反射的に振り向いた、ぼくの視線の先で。
出現してからいままでずっと静止していた黄金の巨人が、重々しい動作で右足を持ち上げていく。
間違いなく、GGO世界に存在するありとあらゆる物体の中で最大の動的オブジェクトだ。身動きするだけで厚雲が千切れ飛び、大気が震える。
ゆっくりと前に出された右足は、一分ほどもかけて再び地面を踏み締めた。しばらくして、ずずーん……という重低音とともに、地震のような衝撃が伝わってくる。
「実体……あったみたいね」
クレハが言ったのと同時に、巨人の右側に奇妙なものが音もなく出現した。水色に透き通る、細長い柱。巨人の膝のあたりから頭の上まで一直線に伸びるそれは、よくよく目を凝らすと、何本もの細長い横線が縦に積み重なっているらしい。物理的なオブジェクトではなく、何らかのUIのように見えるあれは……。
「え……あれ、HPバー?」
再びクレハが掠れ声を響かせた。ぼくは半信半疑だったが、アファシスがこくりと頷く。
「そのようなのです。全部で百本あります!」
「百本……」
鸚鵡返しに呟く。
いままで戦ったボスエネミーは、HPの総量にかかわらずHPバーは三本で固定されていた。あの巨人だって同じ方式で表示できるはずなのに、百本という無茶な数に設定されているのは、何か理由があるのかないのか。
そんなことを考えるぼくの背中を、クレハが勢いよく叩いた。
「百本だろうが千本だろうが、HPバーがあるなら倒せるってことよね! ほら、あたしたちも行くわよ!」
その言葉に周囲を見回すと、ドーム付近に集まっていたプレイヤーの半数以上が、巨人めがけて走りだすところだった。どうやらあれを倒そうという剛の者は、クレハ一人ではなかったらしい。
「さっき言ってた助っ人を待たなくていいの?」
「現地で合流できるでしょ。ほらほら急いで!」
ぐいぐい背中を押されれば、これ以上踏ん張っているわけにもいかない。それにぼくだって、あの巨人からどんなアイテムがドロップするのか、興味がないと言えば嘘になる。
「わかったよ。でも無茶はしないでね、クレハ」
正面から顔を覗き込みつつそう釘を刺すと、幼馴染はぱちぱち瞬きしてから、「わかってるわよ!」と叫び、先に立って走り始めた。ぼくはアファシスと顔を見合わせ、勢いよく揺れるサイドテールを追いかけた。