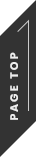カッコいいにもほどがある登場シーンを披露した《黒の剣士》キリトは、ぼく、アファシス、ツェリスカ、イツキ、クレハ、デイジーを素早く見回すと続けた。
「バザルト・ジョーやダインたちは?」
「見かけてないよ、たぶん前線でボスを攻撃してるんだと思う」
「そうか……時間がないな」
キリトは表情を引き締め、ユウキとレインの間をすり抜けて最前列に立つ。十メートル先に陣取るアスカ組の気配が変わったのは、HPバーに表示された《Kirito》の名前を見たからか。
「提案がある!」
キリトが頭の芯まで響くような大声で叫ぶと、アスカ組の前列に並ぶ侍たちが、気圧されたようにじりっと下がる。やがて、方陣の奥から長い烏帽子を被った男性プレイヤー――恐らく職業は陰陽師だろう――が進み出てきて、負けず劣らずよく通る声で叫び返す。
「聞くだけ聞こう!」
するとキリトは、右手で彼方の巨人を指差しながら、ぼくも驚くようなことを言った。
「こっちには、あのボスを制限時間内に攻略するための作戦がある! もし協力してくれたら、報酬は公平に分配する!」
「えっ!?」
と隣のクレハが、アスカ組には聞こえない音量の声を漏らした。いっそう声を潜め――。
「でかおじのHPバー、あと九十本以上も残ってるのよ。残り二十分で、どうやって削るつもりなのかしら」
「まあ……キリトだからね」
ぼくが答えになっていない答えを返すと、クレハは「……そうね」と頷く。ぼくたちもこのGGOであれこれピンチを乗り越えてきたけれど、キリトの無茶はもう伝説の域と言っていい。
濃紺の狩衣をまとった陰陽師は、鋭い視線でキリトを見据えた。HPバーに表示されているプレイヤーネームは【蘆屋道捺】。平安時代の陰陽師、蘆屋道満をもじった名前だろうけれど、後半の読み方はさっぱり……いや、ひょっとすると「道捺」だろうか。だとしたら千代惟任のイトコか何かかもしれない。
甘そうな名前の陰陽師は右手に黒い扇子を持っていて、畳んだそれを口許にあてがいながら三秒ほど考え――。
「よし、乗ろう」
――そんな簡単に決めていいの!?
と突っ込みたい衝動に駆られたが、なんとか抑える。むしろぼくらに仲間を何人も殺されたアスカ組の面々が納得しないのではと思ったが、道捺はよほど信頼されているらしく、文句を言う者は一人もいない。
「決まりだ」
キリトは即座に応じると、赤い空を見上げた。それが合図だったかのように、新たなプレイヤーが舞い降りてくる。
プレミアよりも小柄な体を青基調のフレアドレスに包み、虹色を帯びた銀髪に黒のベレー帽を載せている。右手には、背丈ほどもありそうな黄金のロングスタッフ。かつてGGOにコンバートしてきた時は、可憐な歌声と超火力のガトリングガンで強烈な印象を残した、こちらも伝説級のプレイヤーだ。名前はセブン。
レインの前に着地したセブンは、笑顔で「プリヴィエート、お姉ちゃん!」と叫びながら抱きついた。しばしハグを交わしてから一歩離れ、フカ次郎にも手を振ってから、こっちに歩いてくる。
「お久しぶり。あなたのアファシスは元気?」
その言葉に、ぼくより先に本人が答えた。
「とっても元気なのです!」
「よかった。あなたたち二人が、この作戦の要だからね」
「ぼくたちが……? いったいどんな作戦なの?」
「説明は彼がするわ」
そう言ったセブンが、キリトに視線を向ける。
進み出てきたキリトは、アスカ組も近くに呼び寄せると、おもむろに口を開いた。
「もう気付いてる人もいるだろうけど、このフィールドでは、エンブレムが違う……つまり別のゲームから来たプレイヤー同士で戦うと、与えるダメージが倍になる」
「ああ……」
ぼくは小さく声を漏らした。クイックショットで縞々左近を迎撃した時、HPが予想よりも減ったのはそういう理由だったらしい。イツキも影の中の忍者を撃った時に同じことを感じたのか、肩をすくめて言う。
「つまりこのイベントは、ボスへの攻撃だけじゃなく、他陣営のプレイヤーをいかに減らすかも重視されている……ということかい?」
「与ダメボーナスの存在を知ると、そう思えるよな。でも増えるのはダメージだけじゃないんだ」
「もしや、支援の効果も増えるのか?」
そう発言したのは、アスカ組の蘆屋道捺だ。キリトはイケメン陰陽師にニヤッと笑いかけ、頷いた。
「いいカンしてるな。そのとおり……陣営が違うプレイヤーにバフを掛けると、効果も継続時間も二倍になる。で、もっと重要なのは、同じ効果のバフでも重複掛けできるってことだ」
「ん、んん……? どういうこと?」
首を傾げるクレハに、アスナが解説した。青いロングヘアに白いワンピースと、GGOとはまったく異なる姿なのに穏やかさと凜々しさが同居した雰囲気はそのままだ。
「たとえば、GGOだと《パワーフォーム弾》を何回当てても攻撃力の上昇量は変わらないでしょ? でもこの空間だと、パワーフォーム弾とALOの《シャープネス》の魔法が両方とも効果を発揮するの」
「えっ……なら、そこにアスカ・エンパイアとかソードアート・オリジンとかルナスケープのATKバフを掛ければ、それも全部乗るんですか?」
「そうよ、しかも倍掛けでね。残念ながら乗算じゃなくて加算だけど」
「うっそ……」
唖然とするクレハの横で、ぼくもぱちくりと瞬きする。「乗算ではなく加算」というのは、たとえば素の攻撃力が一〇〇だとして、そこに三十パーセント上昇のバフを三つ掛けた時に、攻撃力が一・三の三乗倍の二一九・七ではなく、一・九倍の一九〇になるという意味だ。でもザ・シード連結体に加わっているVRMMOは百タイトルを超えるのだから、もしも全陣営のプレイヤーが集まってバフを掛けることができれば、攻撃力は一〇〇の三百倍――すなわち三万にもなってしまう。
「なるほどね……。現状で、協力を取り付けられた陣営の数はどれくらいなのかしら~?」
ツェリスカにそう問われたキリトは、まずセブンと短く言葉を交わし、ちらりと蘆屋道捺を見やってから答えた。
「アスカ・エンパイアでちょうど三十だ」
「う~ん、十五分でその数なら立派なものだと思うけど……でも、あのボスのHPを削り切るにはまだ足りない気がするわね~」
「ああ、俺もそう思う」
頷くと、キリトはまっすぐぼくを見て――。
「そこで、きみとアファシスの出番だ」
「え……?」
「マスターだけじゃなくて、わたしもですか?」
再びきょとんとしてしまう。セブンも先ほどそんなことを言っていたけれど、ここにいる全員に多重バフをかけて総攻撃しても火力が足りないのに、たった二人でどうにかできるとは思えない。
すると、まるでぼくの思考を読んだかのように、アルゴが砂色のフードの下でニンマリと笑った。
「真正面からぶっ叩くだけが攻略じゃないサ。実はナ、ALOには弱点看破の魔法があるんダ。それであのオッサンを調べたら、頭の冠に二箇所だけ弱点があることが解ってサ」
「冠に……?」
ぼくは体を九十度回転させ、西の空を見上げた。
黄金の鎧をまとった巨人は、両足に数千人の猛攻を浴びながらも、SBCグロッケンがある真東へと着実に進み続けている。HPバーはもうすぐ四段目が終わりそうだけれど、正攻法で残り九十六段を削り切るのは難しいだろう。
巨人の頭は一千メートルもの高さにあるので、かぶっている冠は空を埋める六角形の赤色に紛れてしまってよく見えない。凄腕情報屋のアルゴが言うなら弱点は本当にあるのだろうが、そもそもあの高さにあるものにどうやって攻撃を当てるのか。
「……ぼくにはキリトたちみたいな翅はないし、UFGもあんなところまでは届かないよ」
視線を戻してそう言うと、アルゴは小さく肩をすくめた。
「残念ながら、このフィールドじゃ飛翔力が制限されてて、オイラたちもせいぜい百メートルくらいしか飛べないんだヨ」
「え……じゃあ、どうやって……」
すると、ぴょんと前に出てきたリーファが、左手でぽんと胸を叩いて言った。
「そこはあたしたちに任せといて! ちゃんと射程圏内まで届けてあげるから!」
キリトたちが立てた作戦は、いかにも歴戦のVRMMOプレイヤーらしい、単純かつ豪快な代物だった。
まずエギル、ストレア、リズベット、クラインが横一列に並んで立ち、その肩にリーファ、キリト、アスナが乗る。さらにその肩に、ぼくとアファシスが乗る。現実世界なら三秒ともたずに倒壊してしまうだろうが、仮想世界にはもっと過激な離れ業を要求されるアスレチックステージなどいくらでもある。
三段のピラミッドを作ったぼくたちに、フィールド全体からキリトたちの呼びかけに応じて集まってきた数多のVRMMOプレイヤーたちが次々とバフを掛ける。攻撃力上昇、防御力上昇、敏捷力上昇、エトセトラエトセトラ……HPバーの下にたちまち無数のアイコンが並んでいき、三十を超えたところで数えるのを諦める。
最後に、クレハ、イツキ、ツェリスカ、デイジーがありったけのバフ弾を撃ち、四人揃って銃を高く掲げてみせた。ぼくとアファシスは仲間たちにサムズアップを返すと、正面から近づく巨人を見上げた。
全ての準備が整うのに十分を要したので、残り時間はもう五分を切っている。GGO世界では、巨人はもうオールドサウスエリアをほぼ踏破し、SBCグロッケンのすぐ近くまで迫っているはずだ。
空が真っ赤に染まった直後に、巨人は『もしも我が歩みがそなたらの都に達すれば、全ては無に還るであろう』と宣言した。協力者の集合を待っている時にキリトたちに訊いたところ、巨人はALO世界の首都である央都アルンの南方九キロメートルのところに出現し、アスカ・エンパイアでは首都キヨミハラの東方九キロメートルに現れたのだという。他の世界でも方角以外は同様らしいので、五分後には全てのVRMMOの首都に巨人が到達し……その時実際に何が起きるのかは解らないけれど、最悪の場合はザ・シード連結体そのものが消滅してしまうことだって有り得る。
正直、この状況でも「ぼくが世界を救うんだ!」みたいな切迫した闘志は湧いてこないけれど、GGOで仲間たちと過ごす時間はぼくにとって大切なものだし、何よりザ・シード世界で生まれたたくさんのAIたち……ストレア、プレミア、ティア、ユイ、リエーブル、デイジー、そしてアファシス――いやレイが消えてしまうのは絶対に嫌だ。
「よし……離陸、十秒前!」
巨人との間合いを計っていたキリトが、僕の左下で叫んだ。作戦に協力してくれた全員が、声を揃えてカウントダウンする。
「……三……二……一……ゼロ!」
一段目の四人が、完璧に同期したタイミングで翅を振動させる。どうっ! と空気が震え、ぼくたちは本物のロケットめいた勢いで空中に飛び出す。飛翔力が制限されているとはとても思えない凄まじい加速力が、アバターをみしみしと軋ませる。
キリトたちは、巨人の託宣を聞いてから三分で金冠の弱点を発見し、二分でこの作戦を立て、十分で他陣営の協力者を確保したらしい。しかもその陣営に、レアな《空を飛べるゲーム》が八つも含まれているのだから彼らの人脈と交渉力、そして《黒の剣士》の声望は凄まじいものがある。たぶんアスカ組の蘆屋道捺も、協力を呼びかけたのがキリトでなければああも簡単に承諾はしなかっただろう。
キリトチームの頑張りのおかげで、一段目の四人と二段目の三人には飛翔力上昇バフが八種類も重ね掛けされている。でもこの加速なら、ロケットは一段だけでも事足りたのでは……と思ったけれど、さすがにそこまで甘くはなかった。巨人の膝の高さを超えて、太ももの中ほどに差し掛かったあたりで、急激に速度が鈍っていく。
「キリの字、そろそろ限界だ!」
クラインがそう叫ぶと、キリトが「OK、切り替え五秒前!」と答え、リーファとアスナも「了解!」と応じた。再びカウントダウンが始まり、ゼロと同時に二段目の三人が一段目の四人の肩を思い切り蹴る。
どんっ! という衝撃とともにロケットが分離し、飛翔力を使い果たしたエギル、クライン、ストレア、リズベットは自由落下で遠ざかっていく。滑空はできると聞いたので死にはしないだろうが、巨人の足許の激戦エリアに落ちたらどうなるか解らない。
しかし四人は悲愴さなどまったくない表情で、ぼくたちに手を振ったりサムズアップしたりしている。ストレアが両手を大きく振り回しながら、「あとは任せたよ~!!」と叫ぶ。
アファシスが「ありがとうなのです!!」と叫び返したが、たぶん声は届かなかっただろう。慣性飛行の頂点に達したキリトたち三人が、フル加速を開始したのだ。
一段目よりブースター役の人数は減ったが、一人あたりの荷重もほぼ半分になった計算だ。体感的には一段目の二倍もありそうな加速Gが全身にのし掛かり、ぼくは思わずアファシスの体を右腕で抱きかかえた。アファシスも、左腕でぼくの腰あたりをしっかりホールドする。
圧縮された空気が耳元で唸り、ボスの巨体がみるみる近づく。横方向には三百メートル近く離れているはずなのに、黄金の鎧をまとった胴体があまりにも巨大すぎて、全容が視界に入りきらない。
ぼくは歯を食い縛り、ボスの頭を見上げた。岩壁めいた胸当ての上に長い顎髭が垂れ下がり、その奥に尖った鼻先がかろうじて見える。頭の上の金冠までは、あと五百――いや四百メートル。
「キリト、行けそう!?」
思わずそう訊ねると、キリトは絞り出すような声で答えた。
「絶対に……届かせてみせる!」
すかさずリーファが「あったりまえじゃん!」と叫び、アスナも「わたしたちを信じて!」と声を張る。三人の翅から灰色、黄緑、水色の光が飛び散り、さらにスピードが一段上がる。
ロケットは巨人の腹を通り過ぎ、胸当てめがけて突き進む。一瞬だけ視線を下に向けると、遥か離れた地面ではプレイヤーたちの攻撃エフェクトがちかちかと絶え間なく瞬いている。
ぼくはふと、この巨人は攻撃しないのかな、と考えた。HPの総量こそとんでもないけれど、取り囲んで殴ってもまったく反撃してこないなら、この規模のイベントボスとしては歯ごたえがなさ過ぎるような気がしなくもない……。
というぼくの思考が、トリガーになったわけでもないだろうが。
突然巨人が、顎髭に囲まれた口を大きく開き、雷鳴じみた雄叫びを轟かせた。
「ぬうううううん!!」
ごごご……と音を立てて巨体が揺れる。再び下を見ると、塔のような右脚がゆっくりと持ち上げられていく。
逃げろ、と叫びたかったがそんなことは地上のプレイヤーたちも解っているだろうし、そもそも声が届かない。
巨人は、高々と掲げた右脚をほんの一瞬だけ静止させると、轟然と振り下ろした。差し渡し七十メートルはありそうな踵が地面を踏んだ瞬間、まるで巨大隕石の衝突めいた爆発が発生し、衝撃波が全方位に広がる。その中でぱぱぱっ……と小さな輝点が立て続けに閃き、そこから金色の光が幾つも上昇してくる。
いまの踏みつけ一発で、何十人のプレイヤーが死んだのかは見当もつかない。さすがに各陣営の上位勢は即死しなかっただろうが、これで脚への攻撃がしづらくなったのは確実だ。
巨人のHPバーは、まだ九十本以上も残っている。どうやら、SBCグロッケンへの到達を阻止できるかどうかは、ぼくたちの弱点攻撃の成否如何ということになってしまったらしい。
顔の向きを戻す。もう巨人の頭はほんの百メートル先にある。でも、まだ冠は輪郭しか見分けられない。
「大丈夫……届く!!」
キリトが叫び、三人の飛翔スピードがもう一段上がった。
その時――。
まっすぐ前方に向けられていた巨人の瞳がぐるりと動き、ぼくたちを捉えた。
顎髭の中の口がすぼまり、まるで小虫を追い払おうとするかのように、ふっと息を吐いた。
一秒後、凄まじい突風が襲いかかってきて、ロケットはひとたまりもなく分解した。錐揉み状態に陥りながらも、ぼくは右腕でアファシスをしっかりと抱き寄せ、左手で超小型の銃――UFGを構えた。
アバターの回転軸と回転速度を計算し、トリガーを引く。緑色の光線が発射され、波打ちながら伸びて巨人の眉間に命中する。
光線――正確には光索とでも呼ぶべき未知のエネルギーワイヤーは、急激に収縮してぼくとアファシスを引っ張り上げる。引きっぱなしだったトリガーを離すとワイヤーも消え、ぼくたちは巨人の鼻先を掠めてなおも上昇する。
「アファシス、いくよ!」
「はい、マスター!」
刹那のアイコンタクト。ぼくたちは互いを抱えていた手を離し、右手でハンドガンを握る。
アファシスの銃も、ぼくと同じロングストロークType-Zに変更してある。メモリーチップの種類が少しだけ違うけれど、火力はほとんど同じはずだ。
慣性飛行の勢いが徐々に緩む。チャンスは、頂点で静止した一瞬だけ。
広々とした額が目の前を通り過ぎ、ついに金冠が視界に入る。アルゴが言っていたとおり、中央部に縦横一メートルほどの紋章が彫り込まれている。直径八十メートルはありそうな全体の大きさからしたら、見つけさせる気がないだろうと言いたくなるサイズだ。
紋章は、正円の中に二つの細長い十字というシンプルな形だった。十字の横線は中心よりもかなり下側にあるので、表しているのは剣……いや、木……?
どちらにせよ、弱点は十字の交差部に埋め込まれた白と黒の宝石だ。
アファシスと同時にロングストロークを構え、サムフリッカーで《クイックショット4》を選択。視界に着弾予測円が出現し、激しく拡縮する。飛翔速度が低下するにつれ、サークルも収縮していく。
放物線の頂点に到達し、ぼくたちが空中で静止した瞬間、予測円も最小になる。
息を止め、トリガーを引く。