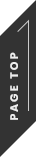あまりにも時代がかった言い回しに、ぼくは一瞬、目の前の八人はNPCなのではないかと疑った。
でも、頭の上に浮かぶHPバーは色も形もイツキやツェリスカのものとまったく同じだし、表示されている名前もNPCらしくない。名乗りを上げた真ん中の侍は漢字で【千代惟任】……せんだいこれとう、だろうか。その右側の侍は【ぽたぽた斎】、左側の侍は【縞々左近】、どう見てもプレイヤーのセンスだ。
と思ったところで、ようやく気付く。いつの間にか、イツキたちのものも含めてHPバーのデザインが少しだけ変化している。GGOのHPバーはもともと横棒が一本表示されるだけのシンプルな形で、それはそのまま変わっていないけれど、そのすぐ下に短い横棒が追加され、左側にはエンブレムのようなものがくっついている。アルファベットのG、G、Oが三角形に配置されたそれは、ガンゲイル・オンラインのロゴマークだ。
侍たちのHPバーもデザインは同じで、下に謎のバーが表示されているのも一緒――でも、ぼくたちのバーよりもさらに短く見える。左のエンブレムは交差する二本の刀と翼を広げた鳥、これはアスカ・エンパイアのロゴだろう。
アスカ・エンパイアは、国内トップクラスの同時接続ユーザー数を維持している和風VRMMO-RPGだ。GGOと同じくザ・シード連結体に所属しているので、相互にキャラクターをコンバートできる。だからぼくは、目の前の侍たちはアスカからのコンバート組なのだろうと反射的に考え、すぐさま打ち消した。
コンバートシステムで他のタイトルに転換できるのはアバターとスキル、ステータスだけでアイテムやお金は一切持ち込めない。なのに、目の前の八人はGGO世界に存在しない日本刀や甲冑、巫女服を装備している。
数分前の、アファシスの言葉が脳裏に蘇る。
――このマップは、GGOサーバーとは異なるシステム上に存在しているようなのです。
きっと、本当にそうなのだ。この、金色の六角形タイルが並ぶ半径一キロの円形マップは、もうガンゲイル・オンラインでもアルヴヘイム・オンラインでもアスカ・エンパイアでもない独立した空間で、恐らくザ・シード連結体に所属する全てのVRMMOと、一方通行の光壁を介して繋がっている。
つまり、身長一千メートルの巨人が出現したのは、GGOだけではない。イツキはさっき、まったく同じゲリライベントがGGO以外のVRMMOでも同時に始まったと言ったけれど、同じなのはイベントの形式ではなく、イベントボスとマップそのもの。つまりこれは、異なるゲームのプレイヤーが協力して一体の巨大ボスに挑む、もしかしたら日本のゲーム史上最大のレイドイベント……のはずなのに、どうして目の前の侍たちはこちらを攻撃してきたのか。
ぼくと同じ疑問を抱いたのだろう、クレハが巨大な光学ランチャーを油断なく構えながら、肘でマップの中央方向を示して叫んだ。
「ちょっと! ターゲットはあのでっかいおじさんでしょ! なんであたしたちを攻撃してくるのよ!」
すると、右側の侍――ぽたぽた斎が、やたらと細長い刀の切っ先をクレハに向けて叫び返した。
「戦場に問答は無用なり! その大筒は見かけ倒しか!?」
「あのねえ、ロールプレイするなら名前にもこだわんなさいよ! 惟任と左近はいいとして、何なのよぽたぽた斎って!」
「斬り伏せた数多の敵の血が、妖刀・長過丸からぽたりぽたりと垂れやまぬゆえに献ぜられた斎号よ!」
「刀の名前も適当すぎるでしょ! だいたい、血なんか一滴も垂れてないし!」
二人のやり取りを聞きながら、妙だな……と内心首を傾げる。
お命頂戴、と威勢のいいことを言っていたわりに、ぽたぽた斎も他の侍たちも斬りかかってくる様子はない。後方の忍者と巫女と山伏も、それぞれの武器を構えたままだ。睨み合っているうちにイツキの麻痺が解けたら、不意打ちした意味がないだろうに。
つまりアスカ組は、こちらが攻撃するのを待っている……?
ぼくは体の前で構えたスナイパーライフルを左手と右肩だけで支え、右手をそっとグリップから外して背後のツェリスカとアファシスにハンドサインで指示を出した。《三秒後》、《攻撃》、《デバフ弾》。ライフルが大柄なお陰で右手の動きは侍たちには見えなかったと思うが、見られても構わない。
――ワン、ツー、スリー。
頭の中で三つ数えてから、元の位置に戻した右手の親指で、グリップの背部分をぐっと押す。もちろんそんなところに物理スイッチはないが、親指の上下左右に六角形の半透過アイコンが浮かび上がる。これがGGOのスキル選択・発動システム、通称《サムフリッカー》だ。
四つのアイコンには武器ごとに任意のスキルを設定できて、親指をその方向に弾くことで選択、トリガーを引くと発動する。ぼくは、スナイパーライフルに攻撃スキルの《炸裂弾3》と《炸裂弾4》、阻害スキルの《電磁スタン弾4》と《アーマーブレイク弾4》を入れていて、選択したのは四つ目。
親指を真下にフリックすると、きゅいいいんというチャージ音とともにライフル全体が淡い黄色の光に包まれる。背後でも同じ音が二つ、重なって響く。
こちらの挙動に、ようやくアスカ組が反応した。といっても、動いたのは中衛の山伏二人だけ。素早く右足を持ち上げ、どんとその場に踏み下ろすと、足の周囲に十数個のアイコンが展開する。
直接目の当たりにするのは初めてだが、動画では何回か見たことがある。あれは、アスカ・エンパイアのスキル選択システム、《グラウンド・サークル》だ。山伏二人は完全に同期した動きで右前方のアイコンを踏み、右手に持った錫杖を地面に突き立てた。
二本の錫杖の先端から、銀色に光る何枚もの呪符が回転しながら広がり、八人を包み込む。直後、ぼくはライフルのトリガーを引いた。銃口から黄色い光弾が発射され、中央の侍めがけて飛ぶ。後方からも、ツェリスカとアファシスが放ったデバフ系のスキル弾が、左右の侍に襲いかかる。
しかし三発の光弾は、二重に張られた呪符の結界に弾かれ、あらぬ方向へと飛んでいった。ぼくがスキルを発動してから、ここまで約二秒。
ぽたぽた斎との言い合いを中断させられたクレハが、振り向いて叫んだ。
「ちょっと、やるならやるって言ってよ!」
光学ランチャーを構えようとする幼馴染の左腕を、ぐいっと引っ張る。
「やらない! いったん下がるよ!」
「え……はあ?」
怪訝そうに眉を寄せながらも、クレハは銃口を下げた。ぼくは素早く振り向くと、麻痺したままのイツキに「失礼!」と声を掛け、胴体を抱えて左肩に担ぎ上げた。右手に持った重量級スナイパーライフル《AMRブレイクスルー4》と、さらにイツキが背負っているスナイパーライフル《ドラゴンキラー2》の重みが加わり、アバターの関節が軋むような感覚に襲われる。もしも地面が砂漠や湿地だったら腰まで埋まったかもしれないが、六角形タイルは破壊不能っぽい踏み応えだし、アクセサリー厳選周回の副次的効果でレベルがカンストしているおかげか重量制限を超えることもなかった。
「よいしょっ……!」
自分に気合いを入れ、一直線に走る。クレハ、ツェリスカ、デイジー、アファシスの四人もすぐ後ろからついてくる。
二十メートルほど移動してから振り向くと、アスカ組は八人とも、まだ呪符結界の中に留まったままだった。それを見たツェリスカが、得心したように言った。
「なるほど~、私たちを挑発して、先に撃たせる作戦だったのね~」
「ど……どういうことですか?」
まだ怪訝な顔をしているクレハに、ぼくはイツキを肩に抱えたまま説明した。
「たぶんあの結界は、飛び道具を完全に遮断するんだ。彼らはこのマップじゃ消耗アイテムを補充できないことを知ってて、こっちの弾を撃ち尽くさせようとしたんだよ」
「すっごくコスい連中なのです!」
アファシスが憤慨した様子で言い放つ。
狡い、なんていう言葉をどこで仕入れてきたのか気になるけれど、追及している暇はない。作戦を看破されたいま、アスカ組が取りそうな選択肢は二つ。張ったばかりの結界を捨てて接近戦を挑んでくるか、侍三人が遊兵になるのを覚悟して結界内から遠距離戦を仕掛けてくるか。前者なら、人数差もあるしイツキを見捨てるわけにはいかないので逃げるしかない。でも後者だったら、戦う手段はある。
ぼくは右手だけでライフルを構えながら、「出てくるな!」と念じた。それが伝わったわけではないだろうが、二秒後、結界の中で忍者と二人の巫女がグラウンド・サークルを出し、スキルを発動させた。
結界の後ろ側で赤と青の光が渦巻き、そこから二匹のドラゴンが躍り出る。両方とも和風の龍だが、左のやつは細長い胴体に火炎を、右のやつは水流をまとわりつかせている。たぶん、あの《月華隊》を名乗る八人もぼくたちと同じくレベルキャップに到達していて、最強クラスの攻撃スキルを習得しているのだ。
赤と青の龍は、大きな弧を描いて上空から襲いかかってくる。どうしてもそちらに引き寄せられそうになる視線を、ぼくは結界の正面へと引き戻した。
直後、前列に立つぽたぽた斎と千代惟任の隙間で、小さな銀色の光が立て続けに煌めいた。すかさずライフルのグリップを親指でダブルタップし、スキルパレットをガジェットパレットに切り替えて真下にフリック。ライフルが光に包まれて消滅し、代わりに小さな棒状の装置が手中に出現する。
それを足許の地面に置くと、ぶうん……という振動音とともに、緑色に透き通る光の盾が投影される。スキルと同じく四つまで登録できる支援装置の一つ、《カバー・ヴィジョン》だ。三十秒しか持続しないが、山伏の呪符結界と同じく、ほぼ全ての遠隔攻撃を防いでくれる。
コンマ一秒後、カカカカッ! と乾いた音を立てて、盾の表面に十字形の刃物――いわゆる手裏剣が立て続けに突き刺さった。巫女の龍召喚で注意を引いたところに忍者がスキルを撃ち込んでくる作戦だろうが、だからと言って龍も見かけ倒しというわけではない……というか、威力は手裏剣より上だろう。しかも曲射弾道で飛んでくるので、カバー・ヴィジョンでは防げない。
ガジェットと入れ替わりに再実体化したスナイパーライフルを握りながら、ぼくは叫んだ。
「クレハ、青いドラゴンをお願い!」
「簡単に言ってくれるわね……!」
光学ロケットランチャー、《デネブカイトスType-Z》を構えるクレハの隣で、ぼくもライフルを持ち上げようとした。しかし寸前、聞き慣れた声が響く。
「赤いほうはお任せください、マスター!」
振り向くと、アファシスが装備をサブマシンガンからずんぐりした擲弾銃に変更したところだった。実弾系グレネードランチャー、《アバドン3+》。小柄なアファシスが持つと片手で支えていられるのが不思議なほどだが、これでもGGOのランチャー系では最もコンパクトな部類だ。
クレハとアファシスは、スキルパレットを瞬時に操作し、同時にトリガーを引いた。発射されたのは、金色の電光を帯びた黒いエネルギー弾。それらは飛来する龍の目の前で炸裂し、直径二メートルほどのマイクロブラックホールを作り出す。周囲のエネミーを吸引しつつダメージを与える攻撃スキル、《重力場発生弾4》だ。
赤と青の龍はエネミーではなく敵の攻撃スキルなので、すり抜けてしまう可能性を一瞬危惧したが、龍たちはブラックホールに吸い込まれると激しく身もだえた。どうやら見た目だけのビジュアルエフェクトではなく、実体のあるモンスターを召喚するスキルだったらしい。
大技を使った巫女二人はクールタイム中だろうし、山伏二人は呪符結界を維持したままで、侍三人にはこの距離まで届く技はないようだ。忍者がちょっと不気味だけれど、反撃するタイミングはいましかない。
「みんな、攻撃するよ! 通常射撃なし、スキルだけで!」
ぼくの指示に、肩の上のイツキを除く全員が「了解!」と答えた。
再びスキルパレットを操作し、《炸裂弾3》を選択。スコープを使わずに、前列中央の惟任を狙う。片手持ちの腰撓めなので着弾予測円はかなり大きいが、どうせ呪符結界に阻まれるのだから狙いは大雑把で構わない。
トリガーを引くと、深紅の光弾が目の前のカバー・ヴィジョンをすり抜けて飛翔し、結界に当たって派手な爆発を引き起こした。クレハ、アファシス、ツェリスカもそれぞれスキル弾を放ち、発生した重力球やプラズマ球、火炎球がフィールドを眩く照らし出す。
どれもGGOで最強クラスの攻撃スキルだが、山伏の呪符結界はその全てを防いでのけた。どうやらカバー・ヴィジョンと違って時間制限もなさそうだし、とんでもなく優秀な防御技であることは確かだが、だからといって効果が無限に継続するわけではないだろう……たぶん。
メイン武器のスキルを撃ち尽くすと、すかさずサブ武器に持ち替える。実弾系ハンドガンの《ロングストロークType-Z》に登録してあるスキルは、防御用の《ハイパーセンス》と、攻撃用の《クイックショット2》、《3》、《4》。こんなに偏ったパレットを組んでいるのは、マガジン内の弾丸を一瞬で全て撃ち尽くすハンドガン専用スキルの《クイックショット》が、あまりにも強力すぎるからだ。
いつまでも下方修正されないのがGGO七不思議の一つとさえ言われているこのスキルを、まず《2》から発動させる。トリガーを引くと、バラララララッ! と小気味の良い連射音が響き、強烈な反動が右手を襲う。充分な筋力値と技量値、そしてプレイヤースキルがないと反動に負けて弾が散ってしまうけれど、そこはだてにレベルをカンストさせていない。連射された弾は全て結界に命中し、六桁の与ダメージ数値がいくつも重なって表示される。アファシスたちも、持ち替えたサブ武器の攻撃スキルを惜しみなく発動させて呪符結界に叩き込む。
はたから見ればぼくたちが一方的に攻撃しているように思えるだろうが、これはアスカ組が最初に狙ったとおりの展開だ。でも、彼らはたぶん知らない。GGOのあらゆるスキル攻撃は、マガジンやエネルギーパックを消費しないのだ。つまり、通常攻撃を行わずにスキルだけを使っていれば、ぼくたちは弾切れを気にすることなく無限に射撃を続けられる。
もちろん、いつかはアスカ組もそのからくりに気付くだろう。その前に結界を破壊できればぼくたちの勝ち、できなければたぶん負け。
「かっ……たいわね!」
クレハが苛立ちも露わに叫び、サブ武器の実弾系サブマシンガン《ドラケLハブーブ+》をガジェットに切り替えた。右手の中に、小ぶりなメロンほどもある黒いボールが実体化する。ぽこんと突き出たボタンを押し込んでから、見事なワインドアップ・ポジションで振りかぶり、結界めがけて投擲する。
現実世界のクレハなら――もちろんぼくも――十メートル飛ばせるかも怪しいところだけれど、三桁のSTRを注ぎ込んだボールはほとんどお辞儀もせずに唸りを上げて飛翔し、結界に触れた途端に巨大なプラズマ爆発を引き起こした。GGOのガジェット類で最大の威力を持つ大型グレネード、その名も《デカネード》だ。
システム的なダメージ数値もさることながら、クレハの気合いが通じたのか――。
二重の結界を生み出している無数の呪符が、オレンジ色の炎を噴いて次々と爆発した。術を破られた反動だろう、二人の山伏が後方に吹っ飛び、巫女たちを巻き込んで倒れる。
この展開は、アスカ組も予想していなかったはずだ。しかし敵もさるもので、わずか一秒後には前列の侍三人がこちらに向けて走り始める。
ここが勝負の分かれ目だ。全力攻撃――と指示するまでもなくぼく以外の全員がサブ武器をメインに切り替える。驚いたことに、普段は戦闘に参加しないデイジーまでもがコンパクトな光学ハンドガン、《プロキオンSL4+》を握っている。
ぼくは装備したままのハンドガンで《クイックショット3》を発動させ、左側の縞々左近を狙ってトリガーを引いた。再び銃口から巨大な発射炎が迸り、左近の全身を着弾エフェクトの閃光が包み込む。
GGOの雑魚エネミーなら、最新の深淵ダンジョンに出てくるやつらでも確殺できる威力のスキルだけれど、アスカ・エンパイアのカンスト勢ならHPを三割減らせれば上等……というぼくの推測は、反対方向に裏切られた。左近のHPバーは恐ろしい勢いで減少し、半分を割り込んだのだ。
ぼくが驚いた以上に左近は肝を冷やしただろうが、動揺の気配すら見せないのはさすが侍と言うべきか。しかも仰け反り無効系スキルを使っているらしく、ダッシュのスピードがまるで鈍らない。
ならば、もはや情けは無用。
スキルパレットを出して、《クイックショット4》を選択。威力が《3》とほとんど変わらないうえにリチャージタイムが長いので、パレットに組み込んでいるプレイヤーは少ないものの、こういうコンマ一秒を争う状況では命綱になる――こともある。
残り二人の侍は仲間たちがなんとかしてくれると信じて、左近に照準を合わせる。間合いはもう十メートルを切っているけれど、落ち着いてバレット・サークルの収縮を待ち、トリガー。愛銃が猛々しく咆哮し、連射された十数発の弾丸は、左近が装備している赤糸威の胴鎧に全弾ヒットした。
HPがガリガリと削られ、呆気なくゼロになる。左近は刀を振りかぶった格好のまま静止し、次の瞬間、金色の光に包まれて凄い勢いで上空へ飛んでいった。死んだ……のだろうけれど、青い破片になって飛び散るGGOの死亡エフェクトとはまったく違う。
一秒後、右側のぽたぽた斎もクレハたちの集中射撃でHPを全損し、光になって飛び去った。けれど最後の一人、千代惟任は残り五パーセントで踏みとどまり、ぼくの目の前でグラウンドサークルを出した。地面の六角形タイルが砕けそうな勢いで左足を踏み込み、スキルを発動。青白い電光を宿した太刀を、高々と振りかぶり――。
「千代惟任、参るッッ!!」
――《せんだい》じゃなくて《ちよ》だったの?
――あ、もしかして、チョコレートの駄洒落?
頭の隅でそんなことを考えながら、ぼくはハンドガンで惟任の眉間を狙おうとした。
でも一瞬早く、右斜め後ろでキュキュキュキュキューン! という光学銃の連射音が響いた。デイジーが、プロキオンでクイックショットを使ったのだ。エネルギー弾の奔流がツヤのある茶色い甲冑を貫いて、残りわずかな惟任のHPを消し飛ばす。
「……見事なり」
と言い残し、最後の侍も赤い空へと飛んでいった。ひとまず敵の一斉突撃は凌いだけれど、まだ山伏と巫女、それに忍者が――。
ダァーン!
突然、大口径実弾銃の発射音が左耳のすぐ近くで轟いて、ぼくは軽く跳び上がった。
横を見ると、肩に担がれたままのイツキが、ライフルを真下に向けている。ようやく麻痺から回復したようだが、いったい何を撃ったのか……と思いながら地面を見下ろし、またしてもびっくりする。
六角形タイルに黒々と伸びるぼくとイツキの影から、人間の上半身が突き出している。
濃い灰色の覆面と装束、額には鉢金。間違いなく、アスカ組の真ん中にいたはずの忍者だ。どうやら、影から影へと移動する能力を持っているらしい。
忍者は、細身の忍刀を逆手に構えた姿勢で硬直している。体の表面を走り回る黄色い電光は、スタンのエフェクトだ。影からの奇襲にいち早く気付いたイツキが、《電磁スタン弾》を撃ち込んだのだろう。ぼくはまたしても助けられてしまったらしい。
とりあえず、クールタイムが終わったクイックショット2を選択し、忍者に撃ち込む。距離が二メートルもないので全弾ヘッドショットになり、侍よりは少ないであろうHPを全て削り切る。
忍者が金色の光になって飛び去るのを見送ってから、ぼくは視線を前方に戻した。ちょうど山伏と巫女が立ち上がったところだ。戦力的にはこれでやっと四対四――ではない。こちらはデイジーが参戦したし、イツキも復帰したので六人。いまならゴリ押しでも勝てそうだ。
ぼくがそう考えた瞬間、山伏たちがくるりと身を翻し、もと来たほうへと走り始めた。向こうも勝ち目なしと判断したのだろう。
「あっ、逃げるな!」
クレハが叫び、デネブカイトスを構える。その銃口の前に右手を突き出し、ぼくは言った。
「いや、深追いはやめよう」
「えー、どうしてよ」
「あいつらがぼくたちを襲ってきたのは、たぶん……」
そこまで答えた時、左肩の上でイツキが言った。
「すまないけど、話の前に僕を下ろしてくれるかい」
「あ……そうだった」
戦闘中も抱えたままだったイツキを地面に下ろし、改めてお礼を言う。
「ありがとうイツキ、二度も助けてくれて」
「いや、それはこっちのセリフさ。あの状況だったら置いていくよ、普通はね」
ぼくが、麻痺したイツキを抱え上げて後退したことを言っているのだろう。確かにそうかもしれないが、咄嗟に体が動いてしまったのだから仕方ない。どう答えたものか迷っていると、アファシスが誇らしげに言った。
「マスターは、ぜんぜん普通じゃないのです!」
褒め言葉と受け取っていいのかどうか微妙な言い回しに、ぼくは思わず苦笑してから話題を戻した。
「それで、アスカ組が攻撃してきた理由だけどね……みんな、自分のHPバーを見てみて」
全員の視線が右下に動く。真っ先に反応したのはツェリスカだ。
「あら……HPの下の短いバー、さっきよりほんの少し伸びてるわね。これ、何を表示してるのかしら……」
「確証はないけど、このマップにいるGGOプレイヤーがでっかいおじさんに与えたダメージの総量だと思う」
ぼくがそう言った途端、仲間たちは顔を上げてマップの西側を見やった。
いつの間にか前進を再開した巨人の両足は、色とりどりの光芒に包まれている。ザ・シード連結体から転移してきた何百、いや千を超える数のプレイヤーたちが、剣や魔法や銃や拳足で猛攻を浴びせているのだ。しかし、脅威の百段HPバーは、三段目がやっと尽きるかどうかというところ。三十分から始まったカウントダウンは早くも七分が経過し、あと二十三分で残りの九十七段を削り切るのは、いまのペースでは絶対に不可能だ。
同じことを考えたらしいクレハが、焦りを呑み込むように深呼吸してから言った。
「でも確かあのでかおじ、《我が金冠を砕くこと能えば》……って言ってたよね。てことは、勝利条件は頭の冠の破壊なんでしょ? 与ダメのカウントに何の意味があるの? しかも個人じゃなくて、タイトルごとの累計なんて……」
「ああ、そういうことか」
イツキが、ぱちんと右手の指を鳴らす。
「クレハ君、よく見てごらん。巨人の百段HPバー、てっぺんのラインが冠の下端にぴったり揃っているだろう?」
「え……ええ、それが……?」
「つまりあの冠はプレイヤーの直接攻撃じゃなくて、HPバーの最後の一段を削り切ることで破壊されるんだよ、きっと。で、その時点で最大のダメージを与えていた陣営が勝者になる……ってことじゃないかな」
イツキの言葉は、ぼくの推測とほとんど一致していた。でも、まだ謎はたくさん残っている。その一つを、アファシスが投げかけた。
「でもイツキ、おじさんはこうも言ってましたよ。《その者は全てを手にするであろう》……この言い回しは、特定のプレイヤー一人を想定していると解釈するべきなのです」
「うーん、確かにそうだね……。冠を破壊した陣営の中で、さらに最大のダメージを記録したプレイヤーが最終的な勝者になる……? いや、もしそうなら追加ゲージは陣営全体じゃなく、自分一人が与えたダメージを示していないとおかしいな……」
考え込むイツキの隣で、ツェリスカが軽く両手を持ち上げる。
「この追加ゲージがGGO組の戦績を表示していることはわかったけれど、それとアスカ組が私たちを襲ってきたことと、どう関係するのかしら~?」
「単純に、GGO組の邪魔をしたかったんだと思う」
そう答えると、ぼくは千代惟任の口上を思い出しながら続けた。
「あいつら、名乗りを上げる前に、《ガンゲイル・オンライン組の総大将と見受けたり》って言ってたでしょ。ぼくたちがここからGGO組全体に指示を出してると判断して、指揮系統を潰しにきたんじゃないかな……勘違いもいいとこだけどね」
「なるほど、オッカムの剃刀だね」
得心したように頷くイツキの横で、ツェリスカがすらっとした顎先に人差し指を当てた。
「だとすると、ちょっと面倒なことになりそうね~」
「なぜですか、マスター」
真顔で訊ねるデイジーに、ツェリスカは懇々と説明した。
「私たち、さっきアスカ組の八人パーティーを損害なしで撃退したでしょ? それはもちろん喜ばしいことだけど、向こうの勘違いが加速しちゃう気がするのよね。もしもさっきの攻撃がアスカ組のリーダーの指示なら一度の失敗で諦めるとは思えないし、次の攻撃はもっと大規模になるんじゃないかしら~」
「…………確かに」
呟くと、ぼくは《月華隊》の四人が撤退していった方向を眺めた。六角形タイルに覆われたマップは真っ平らで障害物もないのに、霧のような砂埃のようなエフェクトがたなびいていて遠くまで見通せない。しかしマップは差し渡し二キロメートルしかないのだから、アスカ組の本陣も案外近くにあるのかも……。
と、思ったその時。
「うげっ!」
とクレハが叫び、デネブカイトスを持ち上げた。一瞬遅れて、ぼくとイツキ、ツェリスカ、デイジー、そしてアファシスもそれぞれの武器を構える。霧の奥から、二十……いや三十人は下らない人影が現れ、こちらに突進してきたのだ。
先頭の一人に照準を合わせたものの、全員が《月華隊》レベルの手練れなら、どう考えても勝ち目はない。ぼくは「逃げよう!」と叫んで振り向き――再び硬直した。
反対側、つまりマップの北側からも二十人規模の集団がぼくたちめがけて突っ込んでくる。シルエットしか見えないけれど、持っているのは銃ではなく剣や斧(おの)のようだ。つまり、GGOプレイヤーではない。
アスカ・エンパイア組が鉄床戦術を仕掛けてきたのか、他の勢力が偶然同じタイミングで襲ってきたのかは解らないけれど、これはさすがにチェックメイトかもしれない。
「どどど、どうしましょうマスター!」
悲鳴を上げるアファシスと左右の仲間たちに、ぼくは気力を振り絞って指示した。
「北からくる敵の中央を突破するしかない! タイミングを合わせて全力斉射、空いた隙間に突っ込むよ! カウント、四、三、二、一……」
トリガーにあと一グラム荷重をかけたら《クイックショット》が発動する――というその時、集団の先頭を走るプレイヤーのHPバーが表示された。瞬間、人差し指をトリガーから離して叫ぶ。
「ストップ、ストップ!!」
全員がさすがの反応で銃を跳ね上げる。直後、集団先頭の小柄なプレイヤーが地面を蹴り、高々とジャンプした。そのまま、信じがたい速度と飛距離でぼくらの頭上を飛び越していく。よく見ると、背中から半透明の薄翅が四枚伸びているようだ。
妖精めいた姿のプレイヤーは、南から迫るアスカ組の前面に着地するや、右手の長剣を引き絞った。
「同郷だけど、手加減しないよ!」
そう叫びながら、怒濤の如く突き技を連発する。
右上から左下に五発。左上から右下に五発。紫色の閃光が煌めくたび、重装の侍たちが地に伏し、あるいは宙に舞う。
剣士は十発の突きで宙に巨大な十字を描くと、再び全身を弓のように反らせて剣を限界まで引いた。
「やああっ!」
裂帛の気合いが空気を震わせ、豪壮な踏み込みが大地を揺らす。十一発目の突きは、紫電をまとう長大な槍となって敵陣を貫き、中列、後列のプレイヤーたちをも放射状に打ち倒した。
ぼくはこの剣技を知っている。直接見たのはこれが初めてだけれど、SNSや動画サイトに上がっているクリップ映像を何回再生したか解らない。かのアルヴヘイム・オンラインに勇名を轟かす《絶剣》ユウキのオリジナル・ソードスキル、《マザーズ・ロザリオ》――。
細身の長剣一本で、ロケットランチャー二丁持ちを優に超える火力を叩き出したユウキは、代償として剣を突き出した姿勢のまま硬直した。そこに、直撃を免れた侍や忍者が、お返しとばかりに攻撃スキルを浴びせようとする。
ぼくは急いでユウキを援護しようとしたが、その必要はなかった。
頭上で何やらキラキラする音が鳴り響き、鮮やかなコメットブルーの輝きが周囲を照らした。見上げると、十メートル上空に人影がホバリングし、そのまわりに巨大な剣の幻影が数十本も浮かんでいる。
人影が両手に握った長剣を振り下ろすと、青い幻影剣が立て続けに射出され、ユウキを攻撃しようとしていたアスカ組に突き刺さった。そこでまず物理ダメージが入り、光属性の爆発でさらなる大ダメージを与える。吹き飛ばされた侍たちの何人かは、HPが全損したのか白い球体に包まれて空へと還っていく。
マザーズ・ロザリオに勝るとも劣らない攻撃力と美しさを兼ね備えたこの技も、動画でなら観たことがある。ALOで唯一、魔法と剣技の融合に成功したというOSS、《サウザンド・レイン》。使い手の名前も同じレインで、GGOではサブマシンガンとショットガンを使っているが、ホームのALOでは希少な二刀剣士だと聞いている。つまりレインも、ユウキと同様にGGOではなくALOのキャラクターでこの戦場にダイブしてきたのだ。
伝説級の大技を二連続で叩き込まれたアスカ組は、完全に足が止まった。しかし生き残った二十数人は逃げ戻らずに踏みとどまり、密集方陣を作る。あのフォーメーションのアスカ組が端倪すべからざる相手であることは、《月華隊》との戦闘で思い知さられた。
硬直から回復したユウキが大きくバックジャンプし、その右横にレインが舞い降りる。油断なく剣を構える二人の左右に、追いついてきたプレイヤーたちが次々と並ぶ。
ほぼ全員がGGOアバターではないのに、後ろ姿を見ただけで誰なのかすぐに解る。無骨な両手剣を担いでいる、薄紫色のロングヘアの女性はストレア。片刃が櫛状に加工された短剣、いわゆるソードブレイカーを構えた、金髪ショートヘアの女性はフィリア。刀身が針のように細いレイピア――いやエストックを携える藍色ショートの少女はプレミア。その隣の、白銀の髪を輪っか状に結い、ひときわ巨大な両手剣を掲げる女性はプレミアの妹のティアだろう。
最前列の六人の左右を、さらに五人ずつのプレイヤーが固める。左にはエギル、クライン、リーファ、リズベット、シリカ。右にはアルゴ、アスナ、シノン、レン、フカ次郎。どうやらGGO組は最後の三人だけ……いや、それ以前に、この面々なら当然いるはずの《彼》の姿がない。
と思ったその瞬間、ぼくとクレハの目の前に、真っ黒な人影が凄まじい勢いで降ってきた。灰色の翅で最低限のブレーキを掛け、ドカン! と派手な音を立てて着地する。
背中で交差する二本の直剣を見た途端、ぼくは口を開いていた。
「キリト! なんでここに!?」
人影は少しだけ振り向くと、口の端をニッと持ち上げて答えた。
「そりゃもちろん、助太刀に来たんだ」