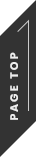西暦二〇二六年現在の日本でいちばん高い建築物である東京スカイツリーは、都心部の少し高い建物からなら容易にその姿を見つけられるが、近づくほどに全体像を視界に収めることは難しくなる。ぼくも何年か前に一回だけ訪れたことがあるけれど、真下から見えるのはトラス構造の支柱群だけで、タワー上部は灰色の空に紛れていた。
スカイツリーの一・五倍もの身の丈がある巨人も、近づくほどに上半身が雲に覆い隠されて、ほんの五分足らず走った時点で、見えるのは円筒形のビルディングめいた二本の脚だけになってしまった。
厚雲を押しのけながら動く足はまだ、切り立った底なしの峡谷――ワールドマップ境界線の向こう側にある。でもあのペースで前進を続ければ、あと五……いや四歩で境界線を越えて、GGO世界に侵入してくるだろう。
すでに境界線の手前では、数百人のプレイヤーたちがそれぞれの愛銃の射程距離ぎりぎりの場所に陣取り、攻撃開始の時を待っている。気の早いプレイヤーがライフル系の銃を発射する音も散発的に響くが、もちろん弾は不可視の壁に吸い込まれ、消えてしまう。
こちらから発射された弾は届かないのに、向こうの音は聞こえてくる。巨人が足を動かすと、ゴオオオオ……という台風のような風音が鳴り響き、地面を踏んだ一秒後、ズズ――ン! と爆発めいた重低音が轟く。境界線の奥――ワールドマップ外にはのっぺりとした灰色の平面が広がっているだけで、土も岩もないはずなのに、巨人に踏まれた場所からは土埃がもうもうと湧き上がる。
「……あと三歩で境界線に到達するのです」
アファシスの囁き声に、クレハが光学ランチャー《デネブカイトスType-Z》のセーフティを解除する。
この距離まで近づくと、巨人の脚を包み込むアーマーのディティールもはっきり視認できる。GGO世界に跋扈する巨大ロボット系エネミーの、サイファイ感溢れるメカニカルな装甲とは明らかに異なる壮麗な装飾は、まるでゴシック建築のようだ。
その脚が、厚雲を引き裂き、大地を震わせながら一歩、また一歩と近づき――アファシスの予測どおり、三歩めでワールドマップ境界線の峡谷をまたいだ。
サッカーグラウンドほどもありそうな足裏がフィールドに触れた瞬間、これまでに数倍する衝撃音が轟き渡り、ぼくたちは反射的に腰を落とした。でも、巨人の右足が生み出したのは、単なる振動ではなかった。
虹色に輝く光の壁がふわりと立ち上り、凄まじい勢いで円形に広がり始める。それはほんの数秒でぼくたちの目の前まで到達し、数百人ものプレイヤーをひと息に呑み込んだ。
視界がオーロラのような輝きに塗りつぶされ、左右に立っていたクレハとアファシスの姿がかき消える。
「きゃあっ!!」「マスター!!」
抱えていたライフルから両手を離し、悲鳴を上げるクレハとアファシスの腕を当てずっぽうで掴む。虹色の光を追いかけてきた衝撃波がぼくたちを吹き飛ばし、HPを派手に削り取る――という展開を予想したのだが、しかし一秒、二秒と経過しても、衝撃はおろかそよ風すらも届いてこない。
やがて、眩い光が少しずつ薄れ始める。ぼくは二人の腕を掴んだまま懸命に両目を見開き、まず自分のHPバーを確認した。ダメージがないなら何かとんでもない阻害効果を喰らったのでは、と思ったのだ。でも、デバフアイコンは一つも点灯していない。
だったら、さっきの光はいったい……と思いながら視線を正面に戻した、その瞬間。
「……へっ?」
自分の口から間の抜けた音が漏れたことにも気付かず、ぼくは両目を見開いた。
眼前の光景が、一変している。
オールドサウスエリア特有の丘陵地帯は、いまや跡形もない。一ミリの起伏さえもないほど平らなフィールドには、石とも金属ともつかないくすんだ金色の六角形タイルが整然と並び、陽光を鈍く反射している。約一キロ前方に屹立する巨人のアーマーと、よく似た色合い。
「これ……どうなって……」
ぼくに左腕を掴まれていることを気にする様子もなく、クレハが掠れ声で呟いた。
それを受けて、アファシスがぼくらだけに聞こえる音量で囁く。
「クレハ、マスター、ここはもう、オールドサウスではありません」
「え……? レイちゃん、それ、どういう……」
「SBCグロッケンを含むあらゆるエリアと接続していない、まったく未知のマップ……いえ、待って下さい」
そう言うと、アファシスは一秒ほど瞼を閉じ、勢いよく顔を上げた。
「そんな……有り得ません」
「ど、どうしたの?」
ぼくは反射的に、アファシスの右腕を掴む手に力を込めた。
こちらを見たアファシスの顔には、AIであることが信じられなくなるほど生々しい驚愕と、恐怖の表情が刻まれている。
「……マスター、この空間は、GGO世界ではなく……」
その言葉を最後まで聞くことはできなかった。
一分近く静止していた巨人が、前進を再開したのだ。相変わらず上半身は分厚い雲の中だが、そびえ立つ二本の足の片方が高々とせり上がり、百メートルにも及ぶ弧を描いてから真鍮色のタイル面を踏み締める。これまでの鈍い足音とは異なる硬質な衝撃音が轟き、地面がぐらぐらと揺れる。
「ワケわかんねーけど……とにかく撃ちまくれ!!」
前のほうで、誰かがやけっぱちのような叫び声を上げた。
それをきっかけに、数百人のプレイヤーたちの半分がライフルやランチャーを構え、残りの半分はサブマシンガンやハンドガンを握ったまま前方へと走り始めた。
直後、実体弾とエネルギー弾の発射音が盛大に鳴り響き、無数の弾道が空へと伸び上がる。それらは巨人の両足に突き刺さり、色とりどりの閃光を瞬かせるが、百段あるHPバーが削れている様子はない。
当然だ、相手があまりにも大きすぎるせいで距離感が狂うけれど、巨人はまだ一キロ近くも離れているのだから。現実世界の対物ライフルは二キロ以上もの有効射程距離があるらしいが、GGO世界では、最長の射程を持つ《AMRティアマト》系列のスナイパーライフルでさえ、一キロは到底届かない。
そう言えば、さっきアファシスが何かびっくりするようなことを……と思ったその時、ぼくに左腕を掴まれたままのクレハが叫んだ。
「あたしたちも前に出よう!」
くるりと腕を反転させ、こちらの右手首を握り返す。そのまま走り出そうとするクレハを、ぼくは慌てて引き留めた。
「ちょ、ちょっと待って。アファシス、さっき言いかけた、GGO世界がどうこうって話は何だったの?」
問いかけると、放心していた様子のアファシスが両目を何度か瞬かせ、銀色の髪を揺らしてこちらを見た。
「……お母さんとのリンクが切断されてしまったので断定はできませんが……このマップは、GGOサーバーとは異なるシステム上に存在しているようなのです、マスター」
「GGOとは違うシステム……?」
鸚鵡返しに呟くと、ぼくは視界のあちこちに視線を向けてみた。
シンプルなHPバーも、その両側の武器アイコンとスキルアイコンも、円形のミニマップも以前のままだ。二人の腕から離した手を握ったり開いたりしてみても、体感覚フィードバックに違和感はない。
同じようにあちこち見回していたクレハが、右手を横に振ってメニュー・ウインドウを呼び出した。たぶんこれも以前のままだろう、と思いながら横から覗き込んだぼくは、またしても「へっ?」と声を漏らしてしまった。
四角いウインドウの真ん中には、シンプルな書体の数字が四つ。存在するのはそれだけ――トップ画面に表示されるはずの装備フィギュアも、画面を切り替えるためのタブも、ログアウトボタンさえも消え失せている。
コロンで区切られた四つの数字は、左側の二つが27で、右側の二つは33、32、31……と一秒ごとに減っていく。
「三十分のカウントダウン……?」
ぼくが呟くと、クレハも頷いた。
「そうみたいね。カウントが始まったのは、さっきの光の壁に接触した時だと思う」
「ゼロになったら、何が起きるんだろう」
「それは解らないけど……メニュー・ウインドウがこの有様じゃ、ここがGGOじゃないっていうレイちゃんの話も、かなり真実味が増してきたわね」
そう言うとクレハはウインドウを消し、前方に目を向けた。
金色の巨人は、ゆっくりと、しかし着実に前進を続けている。一歩進むのに五秒かかり、次の一歩を踏み出す前に十五秒も静止するが、何せ歩幅が百メートルもある。つまり分速三百メートル……ということは十分で三キロ、カウントダウンが終わる三十分後には九キロ移動している計算だ。
周囲でライフルやランチャーを撃ちまくっていた遠距離型のプレイヤーたちも、有効射程外であることにやっと気付いたのか、武器を下ろして走り始めた。先行した近距離型プレイヤーたちはすでに五百メートル以内まで近づいていて、あと一分もしないうちにお祭り騒ぎが勃発するだろう。
クレハも、合流した直後は最大ダメージ賞を狙うと息巻いていたのだから、いてもたってもいられないのでは……と思いながらちらりと横顔を見ると、こちらの考えを瞬時に察したのか、軽く肩をすくめて言った。
「最ダメ狙いは諦めてないわよ。でもこの状況じゃ、焦っても意味ないわ」
「え……どうして?」
首を傾げるぼくの右側で、アファシスが咳払いする。
「えへん……わたしは解りましたよ! メニュー・ウインドウが機能していないということは、この空間では武器の交換も、弾の補充も不可能なのです!」
「あ……」
言われてみれば、確かにそのとおりだ。
GGOでは弾薬を、《銃に装着した弾倉》、《実体化した予備弾倉》、《ストレージ内の弾薬》の三段階で管理している。大口径拳銃弾を使用するロングストローク系のハンドガンならワンマガジンに十一発、予備弾倉が(ぼくの場合は)ベルトに三本、そしてストレージ内に最大で千二百八十発もの弾薬を所持できる。弾倉四本ぶん、四十四発を撃ち尽くしても、ストレージを開いて補充すれば一回のボス戦で弾切れを起こす可能性はゼロに近い。
でも、メニュー・ウインドウが機能していないこのマップでは当然ストレージにもアクセスできないのだから、ぼくが撃てる弾はロングストロークType-Zの大口径拳銃弾が四十四発と、AMRブレイクスルー4の対物ライフル弾がわずか十二発……景気よくばらまいたら、二分もかからず弾切れになってしまう。
クレハのデネブカイトスは弾倉ではなくエネルギーパックを用いる光学系ランチャーだが、確かワンパックで撃てるのは三発だけ、予備パックも五、六本しか持っていなかったはずだ。アファシスの実弾系サブマシンガン《SPBパタシアムType-Z》は弾倉に五十発入るが、予備は一本。
こんなことなら、所持重量の限界ぎりぎりまで弾を実体化しておくんだったと思ってしまうけれど、メニュー画面が使えなくなるなどという展開は、闇風たちベテラン勢にも予測できないだろう。
その闇風は「もう少し情報が集まってから参加する」と余裕を見せていたが、この状況ではイベントの情報が出揃う前にプレイヤーの大半が弾切れになってしまいかねない。そう考えたぼくは、幼馴染に顔を寄せて囁いた。
「ねえクレハ、他の人たちにも、メニューが操作できないって教えてあげたほうがいいんじゃないかな」
「最初に弾切れした人が気付いて周りに教えるでしょ」
素っ気なくそう答えると、クレハは左手のグローブに内蔵された時計をちらりと見てから、サイドテールを揺らして振り向いた。ぼくとアファシスもつられて後ろを見る。
するとそこには、奇妙な光景が広がっていた。
数分前にぼくたちを通り抜けていった光の壁が、およそ三十メートル先で停滞し、蜃気楼のごとく揺れている。壁は左右にごく緩やかな弧を描いていて、どうやら黄金巨人を中心とした半径一キロ程度の真円を成しているらしい。
六角形タイル張りの地面は光の壁の手前まで続いているが、壁の向こうにはごくうっすらと、大型ドームと高層ビル群のシルエットが見て取れる。つまりこの空間はGGO世界のオールドサウスエリアを円形に切り抜いている……いや、侵食しているわけだ。
「……あの壁、外から入ってこられるのかな……」
そう呟いた直後、まるでぼくの言葉が聞こえたかのように光壁の一箇所が同心円状に震え、三つの人影を次々と生み出した。
先頭に立っているのは、わずかに紫がかった銀色の巻き毛を左肩に垂らした女性プレイヤー。巨人が前進を始める直前に、ぼくが連絡を取ろうか迷ったフレンドのツェリスカだ。右手に、ポリマーフレームの光学ショットガンを携えている。
その斜め後ろにいるのは、ミルク色の髪をハーフツインに結い、右目を大きな眼帯で隠した小柄な女の子。武器を一つも持っていないのは、ツェリスカが所有するアファシスだからだ。名前はデイジー。
そして三人目は、長身を白と黒のコートに包んだ、アッシュグレーの髪の男性プレイヤーだった。クラシカルな意匠のスナイパーライフルを右肩に掛けた彼もフレンドではあるけれど、友達のひと言では片付けられない、込み入った因縁のある相手だ。名前はイツキ。
「クレハが呼んだ助っ人って……」
そう言いかけたぼくを無視して、クレハは三人に向けて大きく右手を振り回した。
「みなさーん、こっちこっち――!」
ツェリスカたちは視線を上向けたまま二秒ほど立ち尽くしていたが、こちらに気付くと手を振り返し、小走りに駆け寄ってきた。
「近くから見ると想像以上に大きいわね~。やたらとハイポリだし、あれ一体でどれくらいのデータ量があるのかしら~」
というツェリスカの第一声を聞き、ぼくは口にしかけていた挨拶を引っ込めた。代わりに、親指で後方を指差しつつ訊ねる。
「どれくらいも何も、あのおじさんを実装したのはツェリスカじゃないの?」
そう――現実 のツェリスカは、ガンゲイル・オンラインの運営企業《ザスカー》の日本支部に所属する凄腕のプログラマーなのだ。だからと言ってゲームマスター権限を持っているわけではなく、あくまで一般プレイヤーとしてログインしているだけだが、少なくともこのゲリラレイドイベントについては一から十まで知っているはず。
そのツェリスカを助っ人に召喚するなんて、クレハも大胆というか図々しいというか……と思いながらぼくは答えを待った。でも、ツェリスカが困り顔で口にしたのは予想を裏切る言葉だった。
「それが、私はまったく関わってないのよね……」
「え……?」
ぱちくりと瞬きするぼくの前に、クレハがずいっと進み出る。
「そ……それって、ツェリスカさんが知らないところでこのイベントの企画が進んでたってことですか!?」
「だったらショックだけど、それもちょっと考えづらいわね~。例の事件のせいで、ザスカージャパンはいま運営体制の立て直しに汲々としてて、とてもこんな大規模イベントを開催する余裕はないから……」
そう応じると、ツェリスカは小さくため息をついた。
例の事件という言葉が、同時期に起きた二つの事件を指していることをぼくたちは知っている。
一つは、日本中のアミュスフィアユーザーを震撼させた《死銃事件》。ステルベンと名乗るプレイヤーが、仲間と共謀してGGOの有名プレイヤー二人を毒殺するという凄惨な出来事だったが、実はその裏でもう一つ、別の事件が起きていたのだ。
死銃を名乗ってナーヴギアをぼくとクレハ、ツェリスカの自宅に送りつけ、それを装着した状態で強化されたボスエネミーと戦わせて、命の選択を突きつけようとした……その、いわば《裏死銃事件》の立役者こそが、ツェリスカの背後に立つイツキ。そしてあれこれお膳立てをしたのが、イツキのスコードロン《アルファルド》でサブリーダーをしていたパイソンという男だ。驚いたことにパイソンは、現実ではザスカージャパンの管理職――つまりツェリスカの上司でもあったのだが、他のプレイヤーへの干渉を極力控えていたツェリスカと違って、パイソンは以前から目障りなプレイヤーを管理者権限でBANしたり、スコードロンの運営資金を増殖したりとやりたい放題だったらしい。
事件後、パイソンは背任罪や脅迫罪で逮捕されたが、二人の犠牲者を出した死銃事件に隠れて大きくは報道されなかった。それでもツェリスカの言うとおり、ザスカージャパン内部は大混乱に陥っただろうし、最近実装された高難度コンテンツ《深淵ダンジョン》に加えて、ここまで大がかりなゲリライベントを行う余力があるとは確かに思えない。
「でも……だとすると、このイベントを企画したのは……」
呟いたクレハが、ちらりとツェリスカの背後を見やった。ぼくとアファシスも、その視線をなぞる。
三人にじっと見つめられたイツキは、一度瞬きしてから仄かな苦笑を浮かべた。
「僕のしわざ……と思われても仕方のないところだけど、さすがにこれだけ大規模なイベントを一人で仕掛けるのは無理だよ。というか……そもそもこれを、イベントと呼んでいいのかどうか……」
「どういう意味ですか、イツキさん?」
クレハの詰問にすぐには答えず、イツキは視線を上向けた。
ぼくも再度振り向き、彼方の黄金巨人を見上げる。我先にと走っていったプレイヤーたちの先頭集団は、そろそろ巨人の足許に到達する頃だろう。じっと目を凝らすと、六角形タイルの上を疾駆する無数の人影を視認できる――が、その彼方で悠然と上下する巨人の足があまりにも大きすぎて、眺めているだけで平衡感覚がおかしくなってくる。
あんな代物はGGOが使っているザ・シード・プログラムの素材には存在しないだろうし、そもそもイツキが裏死銃事件を仕掛けることができたのは、ザスカージャパンに協力者がいたからだ。実際、違法と認定される行為のほぼ全てはパイソンが実行していたため、イツキは起訴どころか逮捕もされなかったと聞いている。でも事件後はふっつり姿を消してしまい、ようやく再会できたのは深淵ダンジョンの攻略中だったので、ぼくも彼がいまどういう状況に置かれているのかはよく知らない。
深淵ダンジョンで危ないところを助けてもらった恩義もあるし、近々ちゃんと話をしないと……と思っていた矢先に、予想外の形で顔を合わせることになったわけだ。どう声を掛けたものか迷いながら、前進を続ける巨人の威容を見上げていると――。
「……これはまだ未確認の情報なんだけどね」
という声が背後から聞こえた。三たび体の向きを変え、イツキを見る。
「まったく同じゲリライベントが、GGO以外のVRMMOゲームでも起きているという噂があるんだ」
「え……GGO以外って、《ALO》とか、《ソードアート・オリジン》とかですか?」
クレハの質問に、イツキはゆっくり頷く。隣のツェリスカが眉をひそめ、疑わしそうな声を出す。
「そんな噂、私はぜんぜん聞いてないわよ~?」
「きみはしばらく前からダイブしてたんだろ? 僕はクレハ君に呼び出された時、まだ現実にいたからね。SNSで、複数のVRMMOで同時にゲリライベントが始まったらしいっていう書き込みを見て、そんなことがあるかなって思ったんだけど……自分の目で確かめようとGGOにダイブしてみたら、コレさ」
イツキの説明を聞いたツェリスカは、傍らのデイジーに目を向けた。
「デイジーちゃん、主要なSNSを検索してみてくれる?」
しかしデイジーは、ハーフツインの髪を揺らしてかぶりを振る。
「申し訳ありません、マスター。現在、外部ネットワークへのアクセス経路は全て遮断されています」
「遮断……? Type-Xアファシスには、ゲーム内で最上位の権限が与えられているのに……。レイちゃんも、外部にアクセスできないの?」
ツェリスカにそう問われたぼくのアファシスも、悄然と頷いた。
「はい……。それどころか、お母さんとも通信できません」
「それは有り得ないわ。マザー・クラヴィーアとType-Xは、論理的にも物理的にも同一のサーバー上に……何なら同一のストレージドライブに存在するのよ。その接続を切るには、GGOの基幹システムそのものに介入する必要があるわ。そんな権限を持っているのは、ザスカー内部でも数えるほどの……」
「そうとは限らないんじゃないかな」
割り込んだイツキを、ツェリスカが怪訝そうに見やる。
「……どういう意味かしら?」
「別に、ザスカーの運営体制に問題があると言ってるわけじゃないよ。GGOには……いや、ほとんど全てのVRMMOゲームは、宿命的なセキュリティリスクを抱えているんだ」
「それは……ザ・シード・プログラムに含まれたブラックボックスのこと?」
「そうさ。ザ・シードは《ライセンスフィーもロイヤリティも存在しない超高性能フルダイブゲームエンジン》という、ゲーム企業にとっては夢のような代物だけど、代償としていくつかの制約が存在する。ザ・シード連結体への強制接続、キャラクター・コンバートの受け入れ、それに……中核部に存在する、解析不能、使途不明なコンポーネント」
「…………」
ツェリスカが黙ってしまったので、ぼくは一歩前に出てイツキに問いかけた。
「つまりイツキは、このゲリライベントはザスカーが企画したものじゃなくて、ザ・シード・プログラムそのものが引き起こしたって言いたいの?」
「もちろん、何の根拠もない当てずっぽうだけど……」
そう前置きすると、イツキはぼくをまっすぐ見て続けた。
「そう仮定すれば、複数のVRMMOで同時に同じイベントが起きてるっていう噂にも説明がつくだろう? あの巨人は単なるイベントボスじゃなくて、ザ・シード連結体全体に何らかの変化を……もしかしたら巨大な破滅をもたらす破壊神…………なーんてね」
冗談めかすようにいつものフレーズを付け加えたものの、イツキが半分以上本気でそう考えていることはぼくにも解った。
謎めいたペールレッドの瞳から目を離せず、ぼくが立ち尽くしていると――。
無機質なフィールドを吹き渡る乾いた風に乗って、いくつもの射撃音が届いてきた。
見ると、黄金巨人の手前で横に広く並んだプレイヤーたちが、斜め上に向けて構えた銃から色とりどりの発射炎を閃かせている。狙っているのは、いくらかでも防御が薄そうな足首部分。誰かが《イーグルアイビーコン》スキルで装甲の継ぎ目にロックオンマーカーを付着させたのだろう、数百本の射線がわずか二、三箇所に集中して眩いほどの火花を生んでいるが、巨人は立ち止まるどころかよろめく様子もなく歩き続ける。
「……ゲージ、減ってる?」
クレハの呟き声に、ぼくは巨人の右側に浮かぶ水色の柱――百段にも及ぶ体力ゲージに目を凝らした。てっぺんはそもそも雲に隠れているので、恐らく下の段から減っていくのだろうが、そこも集中砲火が生み出す塵煙に紛れてしまってこの距離からではよく見えない。
「少しずつですが減っています、クレハさん」
と答えたのは、左目をいっぱいに見開いたデイジーだった。システムと接続できなくても、アンドロイドならではの視力や聴力は健在のようだ。
「じゃあ、少なくとも無敵エネミーじゃないってことね」
クレハがほっとしたように言うので、ぼくは懸案事項を再び口にした。
「でも、いまのペースだと、絶対に弾切れのほうが早いよ。やっぱりみんなに警告したほうがいいんじゃないの?」
「弾切れ……?」
ツェリスカが再び怪訝そうな声を出す。
「あんな大物に挑むんだから、みんな限界ぎりぎりまで弾薬やエネルギーパックを持ってきてるんじゃないかしら~?」
「それがねツェリスカ、この空間では……」
メニュー・ウインドウが使えないんだよ、と続けようとしたその時、フィールドを伝わってきた強烈な震動と爆音がぼくの言葉を遮った。
遠距離型のプレイヤーも射程圏内に到達し、いっせいに射撃を始めたのだ。ガトリングガンやロケットランチャー、グレネードランチャーが猛々しく咆哮し、巨人の足首に無数の火球を咲かせる。
今度こそ、巨体がわずかながらよろめいた。もちろん倒れはしなかったが、爆炎に包まれた右足が空中で左右に蛇行し、激しく地面を踏みつける。ブーツのすね当て部分に細長い亀裂が走り、金色の破片がきらきら光りながら落下する。
「もうすぐ一段目のHPバーが終了します」
デイジーの報告に、ぼくは「案外早かったな」と思ったけれど、よく考えればバーはあと九十九段もあるのだ。もしも三十分のカウントダウンが巨人討伐のタイムリミットなら、時間内に全て削り切るのは至難だし、その前にほとんどのプレイヤーが弾切れになってしまう気がする。
たぶん、この空間から出ればメニュー・ウインドウも復活するだろうが、光の壁が一方通行だという可能性もある。いったん光の壁のところまで戻って、外に出られるかどうかをチェックするべきか――。
「一段目、終わります」
再びデイジーが声を発し、ぼくは巨人をじっと見つめた。
大きく踏み込んだまま静止している右足が、ひときわ巨大な爆発に呑み込まれる。ブーツの分厚い装甲に新たな亀裂が何本も走り、ここまで聞こえる硬質な破壊音とともに呆気なく砕け散る。
落下していく破片の中から現れたのは、筋骨隆々としたすねとふくらはぎ。まるでギリシャ彫刻の如き肉体美だが、脳裏に妙な心配もよぎってしまう。
「……ねえ、もしかしてあのおじさん、鎧が全部壊れたら……」
同種の懸念を感じたらしいクレハが、小声でそう呟いた――その時。
戦場の空をくまなく覆い、巨人の上半身を隠していた灰色の厚雲が、激しく渦を巻きながら急速に晴れ始めた。
その奥から現れたのは、GGO世界の見慣れた黄色い空――ではない。まるで鮮血のように真っ赤な夕焼け……いや、赤い空をよくよく見ると、地面と同じく六角形のパターンが規則正しく刻まれている。
突然、その六角形ひとつひとつに、白く光る二種類の文字列が浮かび上がった。交互に記されたアルファベットは、【Warning】と【System Announcement】。
なおも巨人の足を撃ちまくっていたプレイヤーたちが、徐々に射撃を中断していく。やがて、戦場に静寂が訪れる。
この機に弾薬を補充しようとしたのだろう、集団のあちこちでメニュー・ウインドウが淡く光る。これで彼らも、ストレージにアクセスできないことに気付いたはずだ。
不意に、静止していた巨人が動いた。
と言っても、前進を再開したわけではない。俯けていた上体をぐぐっと反らし、両足を大きく開いて仁王立ちになる。
黒々とした影に沈む顔が、戦場全体を睥睨するかのように左から右へと巡らされた。髭に覆われた口許が動き、朗々とした声が響き渡った。
『種は芽吹き、枝葉を広げ、環となって門を作る。祝福なき軍場に打ち集いし戦士たちよ、我を止めるべく足掻いてみせよ。もしも我が歩みがそなたらの都に達すれば、全ては無に還るであろう。もしも我が金冠を砕くこと能えば、その者は全てを手にするであろう』
声はそこで途切れ、殷々と反響しながら消えた。
やたらと芝居がかった言い回しを即座には噛み砕けず、ぼくは脳内で必死に口語訳しようとした。前半はいいとして、問題は後半だ。「我が歩みがそなたらの都に達すれば」というのは、巨人がこのまま前進して「都」――SBCグロッケンに到達すれば、という意味か。しかし、「全ては無に還る」というフレーズはあまりに抽象的すぎる。
その後の、「我が金冠を砕くこと能えば」は巨人がかぶっている冠を破壊できれば、という意味だろう。それを成し遂げたプレイヤーは、「全てを手にする」……?
どうにかそこまで読み解くと、ぼくはツェリスカに話しかけようとした。
しかしまたしても、予測不能な現象に妨げられた。
真っ平らなフィールドのあちこちに、小さな光の柱が伸び上がる。中心部に近づくほど数が増えるが、ぼくたちからさほど遠くない場所にも五本、十本と固まって生えている。
光の柱はいったん二メートル近くも伸びてから、すぐに縮み始める。その中から現れたのは――人。プレイヤーだ。でも、シルエットに違和感がある。GGOプレイヤーのSFチックな戦闘服ではなく、なんだかやたらと古めかしい……。
「マスター!!」
いきなり、近くでアファシスが叫んだ。
ほぼ同時に、ぼくの左の耳許で、ガツッ! という鈍い音が響いた。
弾かれたようにそちらを見ると、いつの間にか近くに来ていたイツキが、ぼくに向けて左手を伸ばしている。広げた手の甲から、何か黒いものが生えて……いや、違う。鋭利な刃物が、手を貫通しているのだ。
「イツキ!」
呼びかけた瞬間、イツキががくっと地面に膝を突いた。頭上のHPバーはほとんど減っていないが、麻痺のデバフアイコンが点灯している。
刃物に毒が塗られていた? でも、GGOに存在するのはダメージ毒だけで、麻痺毒なんて見たことも聞いたこともない。
一つだけ明らかなのは、黒い刃物はぼくを狙って飛んできたもので、それをイツキが自分の手で防いでくれたということだ。つまりぼくは、深淵ダンジョンに続いて、またしてもイツキに守られてしまったらしい。
自分の不甲斐なさに歯噛みしながら、ぼくはイツキの前に飛び出し、右肩に掛けていたスナイパーライフルを構えた。
二十メートルほど離れた場所に、いつの間にか八人ものプレイヤーが立っている。彼らも、光の柱から出現したに違いない。
クレハとアファシスも銃を構え、ツェリスカは背後にデイジーをかばう。イツキが麻痺してしまったので、こちらで戦えるのは四人。敵の数はその倍。でも、この状況でいきなり攻撃してくるなんて、対人スコードロンにしても好戦的すぎる――――
「…………えっ」
敵集団の姿をはっきり視認した瞬間、ぼくの口から喘ぎ声が零れた。
どう見ても、GGOプレイヤーではない。前面に並ぶ三人は、和風の甲冑を着込み、両手で打ち刀を構えた侍。その後方には、白衣と緋袴をまとった巫女が二人と、修験者の装束を着込んだ山伏が二人。
そして集団の中央には、濃い灰色の忍び装束に身を固めた――忍者が一人。
ぼくたちに銃口を向けられても動じることなく、侍の一人が野太い声で叫んだ。
「ガンゲイル・オンライン組の総大将と見受けたり! 我ら、アスカ・エンパイア《月華隊》――お命頂戴いたす!!」