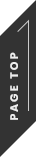反乱討伐軍の野営地を抜け出したシルヴィーは、昼間両軍が激突した戦場跡を急ぎ足で歩いていた。昼間見た両親のことを確かめたくて、誰にも言わずに軍を抜け出したのだ。もしばれれば、叱責程度では済まないだろう。だが、シルヴィーにはどうしても我慢することが出来なかった。もし両親が本当に生きていて、前のように一緒に暮らすことが出来たら――シルヴィーの頭の中は、そのことでいっぱいだった。
一時間ほど歩いただろうか。折れた武器や鎧の残骸が散乱する戦場を抜けて、シルヴィーは敵の野営場所に辿り着いた。遠目に見た限りでは、自陣と同じく天幕はひっそりと静まり返っており、動くものの気配はない。おそらく、昼間の激戦で兵士たちも熟睡しているのだろう。
「今なら間に合うけど……」
これ以上進んだら、きっと引き返せなくなる。そんな考えが頭をよぎり、シルヴィーは足を止めた。ここで引き返せば、またシャーリーとも肩を並べて戦えるだろう。キリトたち人界人に思うところはあるが、同じ暗黒界人であるシャーリーとは、もう友人と呼べる仲だ。彼女に何も告げずに来てしまった後悔はある。
「……ごめん、シャーリー。私はどうしても、父さまと母さまに会いたいの」
小さな声で謝ると、シルヴィーは意を決して歩き出した。
反乱軍の天幕には動くものの気配はなく、不気味なほどに静まり返っていた。夜襲を恐れてだろうか、灯りやたき火も、一つも見えない。折り悪くルナリアも黒い雲に隠されてしまい、周囲は真っ暗となってしまった。人界人と異なり、暗黒界人は暗闇をそれほど恐れない。それでもここの闇は冷たく暗く、シルヴィーの恐怖を掻き立てる。もし誰かに遭遇しても、暗黒騎士の格好をしていればごまかせる――そう自分に言い聞かせながら、シルヴィーは早足で敵陣の奥へと進んでいった。
「……ここは、食料置き場かな」
どれほど歩いだだろうか。シルヴィーは木箱や麻袋がうず高く積まれた場所に出た。ここを焼き討ちすれば、敵軍は困るだろうな、と思いながら、さらに歩を進める。
「誰だ?」
突然、横から声をかけられた。なんとなく、この場所には誰もいないと思い込んでいたシルヴィーは、文字通り飛び上がって驚いた。しかし、頭の片隅には、どこか泣きたくなるような、懐かしい感情が浮かんだ。
――まさか。でも、この声は……
「父さま!! 父さまなの!?」
ここが敵地であることも忘れ、シルヴィーは叫んだ。その声が合図であったかのように雲が晴れ、月明かりが声の主を照らす。そこに立っていたのは、暗黒騎士の鎧に身を包んだ、シルヴィーの父親だった。
「……父さま!」
昼間見たときには、「見間違えるはずがない」と思いつつも、どうしても確信を持つことが出来なかった。だが、目の前にいるのは紛れもなく父親だ。やっと会えたという気持ちと、なぜ生きているのかという疑問、そのほか無数の気持ちがぐるぐると渦を巻き、涙となってシルヴィーの両目から流れ出した。しかし、父親の方は、むせび泣くシルヴィーを見て首を傾げた。
「誰だ? なぜここにいる」
「え……?」
シルヴィーは愕然となった。目の前にいるのは確かに父親なのに、まさか「誰だ」と聞かれるなんて。それに、シルヴィーを見る目が、明らかに不審者を見るそれとなっている。本当は、父さまじゃないのかもしれない。でも……。
「父さま、私だよ! シルヴィー!」
必死に訴えると、父親の目に当惑の色が浮かんだ。そして、こわばった表情が徐々に柔らかくなり、シルヴィーを見る目にも慈愛が宿る。
「……シルヴィー、なのか?」
「そうだよ、父さま! シルヴィーだよ!」
父親が自分を呼ぶ声。あの日、最後の戦闘の前に聞いた声を、何度も何度も頭の中で再生した。でも、やはり本物の声は全然違う。シルヴィーはこらえきれなくなって、父親の胸に飛び込んだ。
「父さま……父さま!! 父さまー!」
縋りついて泣くシルヴィーの背中に、戸惑いながらも父親はそっと手を回す。懐かしい父の手の感触に、シルヴィーの迷いは吹き飛んでしまった。
しばらく、シルヴィーは父の胸の中で泣きじゃくった。その間ずっと、父はシルヴィーの背中や髪を撫でてくれていた。まるで子どもの頃に戻ったみたい、とシルヴィーは幸せな気持ちでいっぱいになった。
やがてシルヴィーが泣き止むと、父親は優しくシルヴィーの体を離した。
「向こうに母さんもいる。今母さんを呼んでくるから、ここで待っているんだよ」
父親の言葉に、シルヴィーは素直に頷く。そのシルヴィーの頭を優しく撫でて、父親はその場を離れていった。
だが、父親と出会えた興奮が落ち着いてくると、代わりにさっきまでかき消えていた疑問が湧き上がってくる。なぜ、出会った時に父親はシルヴィーのことをわからなかったのか。いくら暗闇の中だからといって、自分の子どもをわからないことなんてあるだろうか。事実、シルヴィーの方は遠目からでも父親だと認識できたのだ。
疑問はほかにもある。なぜ敵軍にいるのか。死んだと思っていたのに、どうやって生き延びたのか。なぜ、シルヴィーに生きていると知らせてくれなかったのか。暗闇の中にひとりぼっちということもあり、いくら振り払っても疑問と不安は消えてはくれなかった。
不安な気持ちと戦いながら父親を待っていると、前方に人影が現れた。両親かと思い、シルヴィーは一瞬喜びの表情を浮かべる。だが現れたのは黒いフードを被った立派なヒゲを蓄えた巨漢の男と、黒い外套を被った男だった。ここが敵地であることを思いだし、シルヴィーは慌てて剣を抜く。
「だ、誰だ!?」
「皇帝に対し、あまりに不遜な態度だな、小娘」
ヒゲの男がズシリと響く声で答えた。特に大きくはないのだが、聞く者に圧を与える声だ。人を従わせることに慣れている者の立ち居振る舞いだった。
「だが、貴様が暗黒界人ということで、一度は許してやろう。これよりは、この皇帝トルガシュ・サザークロイスに忠誠を誓え」
「だ、誰が忠誠なんて誓うか!」
突然皇帝と名乗る男が現れたことに混乱しながらも、シルヴィーは必死に自分を保つ。そして、どうやってここから脱出するかをめまぐるしく考えた。出来れば、両親を連れて逃げたいが、ふたりがどこにいるのかはわからない。一度は離脱して、その後に戻って……。
「お前の両親がどこにいるのか、教えてやろうか?」
皇帝の脇に控えていた外套の男が、ぼそりとつぶやく。シルヴィーは驚愕した。最初は、自分の考えを見抜かれたことに。そして――
「ど、どうして父さまと母さまのことを……」
驚きのあまり、持っていた剣を取り落としそうになる。その姿を見て、外套の男は楽しそうに笑った。
「もちろん知っているとも。あのふたりを甦らせたのは、この私なのだからな」
「よ、よみがえ……」
「そう。お前の両親は死んだ。そして、我が秘術により蘇ったのだ。ミニオンとして……な」
「ミニオンだと? 嘘をつくな! ミニオンは怪物の姿をしているはずだ!」
「ククク……そうか、信じられぬか」
「当たり前だ! 父さまと母さまが、ミニオンだなんて……」
シルヴィーは必死に言いつのる。半分は自分自身に言い聞かせるためだ。せっかく生きていた両親の正体がミニオンだったなんて、そんな悪夢のような事実を信じたくない。だが、目の前で両親が整合騎士に倒されたのも事実だ。死者を蘇らせる方法など、この世に存在するのだろうか……そんな思いを必死に否定する。
「信じられぬと言うなら仕方がない。あのふたりを泥に戻してみせよう。そうすれば、いくら頑固な人間でも信じざるをえまい」
「ど、泥に……?」
「無論、泥に戻ってしまえばあの姿には戻れぬ。だが、お主が信じないというならば仕方がないな」
「くっ……」
シルヴィーは言葉に詰まり、唇を噛み締めた。両親が泥から出来たミニオンだとは信じたくない。だが、万が一相手の言うことが本当だとしたら、シルヴィーはもう一度両親を失うことになる。それだけは絶対に避けたい。シルヴィーは憎悪をこめて男を睨んだが、相手はひるんだ様子もなく、楽しげにシルヴィーを眺めている。
「……わかった。だから父さまと母さまに何かするのは止めてくれ」
「いいだろう。その代わり、トルガシュ陛下に忠誠を誓い、我が軍のために戦うのだ」
「それは……」
ここで頷けば、シャーリーやキリトたちを裏切ることになる。だが、拒否すれば両親がどうなるのか、聞かなくてもわかった。
「お前たちのために戦う」
「ならば跪け、小娘。忠誠の証にな」
シルヴィーはトルガシュに言われるがまま、黙って膝をついた。屈辱と憎悪、シャーリーたちを裏切った後悔、両親を救いたいという思いなど、さまざまな気持ちが入り交じり、トルガシュの高笑いも、外套の男の嘲りも、耳に入ってこなかった。だが、去り際に男が放った言葉だけは、嫌でも耳に残った。
「お前の両親は、自分がミニオンであるということを知らぬ。もしそのことを伝えれば、自我が崩壊して泥に帰ってしまうかもしれん。気をつけるのだぞ」
皇帝と男が立ち去り、シルヴィーはのろのろと立ち上がった。これからどうしていいかわからない。しかし、キリトたちの元へ戻ることが出来ないことだけはわかった。
「シルヴィー? そこにいるのか?」
後ろから聞こえた声に、シルヴィーはビクッと体を震わせる。これは、ミニオンの声なのだろうか。だが、何度聞いても聞き慣れた父親の声にしか聞こえなかった。
「母さんを連れてきたぞ。ほらシルヴィー、こっちにおいで」
言いようのない感情にさいなまれながら振り向くと、そこには懐かしい母の顔があった。父親と同じように、シルヴィーの顔を見ても当惑した表情を浮かべている。だが父親がシルヴィーのことを説明すると、みるみるうちに感情を取り戻していった。
「シルヴィー、会いたかったわ!」
そう言って母親はシルヴィーを抱きしめる。頭を撫でてくれる手は、前と同じように暖かい。
「……母さま! 母さまー!」

両親と抱擁を交わしながら、シルヴィーは決意した。ふたりがミニオンでも構わない。家族を失うくらいなら、シャーリーたちとの絆も捨てる。裏切り者と罵られてもいい。両親に真実を伝えられない罪悪感を抱えて生きていくのも覚悟する。ただ、このまま……家族で生きていけるなら。
その様子を、遠くから見ていた彫刻術師が、興奮のあまり声にならない声で叫んだ。
「なんと、ミニオンたちの記憶や人格が補完されていく……近しい人間と接することで、復元されるのか」
興奮のあまり、ろれつが回っていない。ミニオンに記憶が戻ると言うことは、それほどまでに衝撃的な事実だった。
「あの娘を引き入れたことで、思った以上の成果を得られましたぞ、陛下!」
「でかしたぞ、彫刻術師。それに、あの娘が相手であれば、代表剣士の小僧も少しは剣が鈍るであろう。その隙を突けば……ククク、あの小僧の命もそこまでだ」