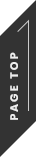――セントラル・カセドラル 屋外修練場――
「やあああっ!」
シルヴィーが木剣を構えて突進する。対峙するデュソルバートの剣をかいくぐって懐に踏み込み、下から喉に鋭い突きを放つ。
「はっ!」
だが、デュソルバートが左腕で剣の腹を叩き、シルヴィーは吹っ飛ばされてしまう。かろうじて転倒せず踏みとどまったが、シルヴィーの手は衝撃でしびれていた。
「うむ……踏み込みはよくなったな。だが、剣が軽い。意識が下半身に集中して、剣の振りがおろそかになっている」
「くっ……」
「意識せずとも全身の力を連動させよ。そのためには、何度も反復することである」
デュソルバートの言葉に、シルヴィーはうつむいた。だが、すぐに顔を上げて、剣を握り直す。
「よろしい。さあ、かかって参れ!」
――セントラル・カセドラル 神聖術授業教室――
「違います、シルヴィーさん」
「えっ?」
必死に式句を唱えていたシルヴィーに、神聖術の教師であるソネスが声を掛けた。
「複雑な詠唱になると、悪いクセが出てしまいますね。神聖語の順番、抑揚……すべてに意味があると先日教えました。その意味をきちんと理解できていないと、今回のような詠唱になってしまいます」
「……っ」
「うまく唱えようとしないでください。詠唱の意味を考え、理解してください」
抑揚のない声にたたみかけられ、シルヴィーは唇を噛み締める。それを見かねたシャーリーが、後ろから声を掛けた。
「シルヴィー、がんばれ! ずいぶんうまくなってるぞ!」
「シャーリーさんも、昨日はできたところが今日できなくなっています。怠慢の現れです」
「うっ、ごめん」
シャーリーも、シルヴィーと同じように縮こまる。ソネスの授業は、あのアスナ副代表でも音を上げるという評判の厳しさだ。だが、留学生ふたりは挫けることなく、必死に授業についていった。
「はあ……今日も疲れたな、シルヴィー」
「……くそっ、今日も暗黒術は全然出来なかった。注意されてばっかりで」
ようやく長い一日が終わり、ふたりは食堂へ向かって歩いていた。今まではロニエやティーゼ、イーディスなど誰かが一緒だったが、今日はふたりきりだ。
「そんなことないよ。シルヴィー、うまくなってると思う! それに、剣の使い方はうまいよなー。さすが暗黒騎士!」
「暗黒騎士って言っても、まだ見習いだし……まだまだ強くならないと。辛いなんて言ってられないから」
「シルヴィーは偉いな! その調子なら、どんどん強くなれるよ!」
シャーリーは屈託のない笑顔を浮かべる。初日こそ人界人への接し方で意見が食い違ったが、翌日からシャーリーはシルヴィーにどんどん話しかけ、シルヴィーも心を開いていった。
「シャーリーもすごいよ。あのソネスって人の授業、全然平気そうだし」
「あはは、ありがと。大変だけど、リピア様の稽古に比べたら全然優しいよ!」
「そうなんだ。リピア様から直接稽古をつけてもらってたなんて、いいな。私は父さまと母さまからは教わったけど……」
「あっ……」
シルヴィーは、昨晩シャーリーが言った「孤児院」という言葉を思い出した。すなわち、シャーリーには両親がいないということだ。
「ご、ごめん。シャーリーは、その……」
「あ、孤児院にいたことは気にしなくていいぞ。わたしはそこで弟と妹がたくさん出来たから、全然平気なんだ」
「……そっか」
シャーリーは、両親を失った悲しみをもう乗り越えて、前を向いているんだ。その強さに、シルヴィーは感心すると共に、自分がとても偏屈に感じてしまった。しばらく、黙ったまま並んで廊下を歩く。そこに、後ろから陽気な声が掛けられた。
「よう、ふたりとも。今日の授業は終わったのか?」
「あっ、キリト! うん、これからシルヴィーとご飯を食べに行くんだ」
シャーリーは明るく返事をするが、シルヴィーは身を固くする。キリトとは、セントラル・カセドラルに来たときに挨拶を交わしている。だが、人界の最高権力者であるキリトに対して、そう簡単に心を開く気にはなれなかった。
「今日はハナさんの新しい献立だからな。きっとおいしいぞ」
「ほんとか!? ……って、なんでキリトが食堂の献立を知ってるんだ? キリトが考えたのか?」
「違うけど、代表剣士としてカセドラルの食事事情を知っておくのも大切な仕事だからな」
「キリトって、ホントに偉く見えないなー、偉いはずなのに。な、シルヴィー?」
「……っ!」
シャーリーの言葉で、キリトの視線がシルヴィーに向く。それに耐えられず、シルヴィーはその場から走り去ってしまった。
「……シャーリーに、悪いことをしちゃったな」
自分がどこにいるかもわからないまま、早足で廊下を歩き続ける。せっかくシャーリーと仲良くなれたのに、また自分から距離を作ってしまった。
「でも私は、やっぱり人界人と仲良くなんて……」
両親のことを思えば、その仇である人界人と馴れ合うことは出来ない。たとえキリトが、人界で最も偉い人だとしても、それは……
ドンッ
「きゃっ!?」
いつの間にか、無意識に目をつぶっていたまま歩いていたようだ。シルヴィーは誰かにぶつかって、尻餅をついてしまった。
「あっ、ごめん。大丈夫?」
そう声を掛けてきたのは、優しい表情をした、緑の髪の男性だ。まだ少年と言ってもいい年齢かもしれない。この男も、人界人……それも、装いからして騎士か、それに準ずる身分だろう。
「大丈夫だ」
差し出された手を無視して、シルヴィーは立ち上がった。相手はそのことを気にする様子もなく、にこやかに話しかけてくる。
「ええと、暗黒界から来た留学生の子だよね。もう人界には慣れたかな?」
「……随分立派な鎧を着ているけど、もしかして整合騎士か?」
相手の質問には答えず、不躾に尋ね返す。さすがに少し困った表情で、男は頭をかいた。
「うん。僕はレンリ・シンセシス・トゥエニセブン。よろしくね」
「やっぱり整合騎士……じゃ、異界戦争で暗黒騎士と戦ったのか?」
シルヴィーの言葉に、レンリの顔から笑みが消えて沈痛な表情になる。
「……うん。君たちには申し訳ないけど」
シルヴィーの表情が厳しくなる。
「どこで戦った!?」
「大きな峡谷を渡ってきた戦士や拳闘士たちと戦ったよ。相手は、無理な命令を下されてしょうがなく渡ってきたみたい……」
「なんだとっ! それは本当か!?」
シルヴィーが、いまにも掴みかかりそうな勢いでレンリに食ってかかる。
「ならば、大きな剣を持った整合騎士……あいつと一緒に、父さまたちの部隊を襲ったのか!?」
「父さま……あそこには、君のお父様が。でも、あの時は戦争中だったんだ。戦わなければいけなかった」
レンリの脳裏に、その時のベルクーリの言葉が浮かぶ。
「こいつは戦争だ。オレたちが暗黒界人に情をかけてる場合じゃねえ」
あの時、光景を見ていたレンリもアリスも、相手を憐れに思ったはずだ。戦場で敵と戦うならともかく、谷にかけられた綱を渡っている相手を攻撃するなんて、騎士道にもとる。だが、ベルクーリはその迷いを見抜いたかのように、そう声を掛けたのだ。
だが、シルヴィーはレンリの悲痛な想いには気付いていないようだった。ますます激高して、レンリに詰め寄る。
「その大きな剣を持った整合騎士はどこにいる! そいつはここにはいないのか!?」
レンリは、ハッとしてシルヴィーを見つめる。ベルクーリがシルヴィーの父親の仇だと、気付いてしまったのだ。
「……ベルクーリ閣下は、異界戦争の最中に命を落とされた」
それを聞いたシルヴィーの表情が、今度は絶望に染まる。
「死んだ……? 父さまと母さまを殺した、あの男が……」
ずっと追い求めていた何かが、ガラガラと崩れていくような、そんな感覚をシルヴィーは覚えた。その男がいないなら、私は……私は、これから何を目標に生きていけばいいのか。
目の前が真っ暗になり、全身から力が抜けるようだった。
「廊下で何を騒いでいるんだ」
向かい合って沈黙しているふたりの元に、ベルチェを抱いたファナティオが通りかかった。救われた、と言った表情で「ファナティオ騎士長!」とレンリが駆け寄り、状況を説明する。
「そうか。異界戦争で、ベルクーリ閣下に……。レンリ、ベルチェをお願い」
そう言ってベルチェをレンリに預けたファナティオは、未だ自失しているシルヴィーの肩を掴んだ。いきなり赤ん坊を渡されて、レンリはおっかなびっくり抱きかかえる。
「シルヴィー。こっちを向いて」
「………………」
「私は整合騎士団長を務めるファナティオ・シンセシス・ツーよ。そして、そなたが仇と狙うベルクーリ閣下は、私の夫である」
「なっ……」
放心していたシルヴィーの目がガッと見開いた。
「レンリが話したように、ベルクーリ閣下はすでにこの世にない。だから、そなたが仇を討ちたいというならば、このファナティオが相手になろう」

「ふぁ、ファナティオ様!?」
シルヴィーが反応する前に、レンリが悲鳴のような声を上げる。
「ほ、本当だな!? もし私がお前を殺しても、文句は言わないんだな!?」
ファナティオの手を振り払い、シルヴィーが剣の柄に手をかける。そこでようやく、帯剣しているのが練習用の木剣だと気付いたが、だからといって諦めるわけにはいかない。
「整合騎士団長の名に懸けて誓おう」
ファナティオは静かにそう告げると、スッと半身になって剣に手を添える。その瞬間、シルヴィーの背中に寒気が走った。とてつもない実力差。たとえシルヴィーが全力を出したとしても、一瞬さえ持ちこたえることが出来ず、自分は命を落とすだろう。だが、それでも――ここで頭を垂れるわけにはいかなかった。
「こ、こんなことまずいよ……代表剣士殿に……」
慌てふためくレンリの気配を察したのか、腕に抱かれたベルチェがふええ、ふええと泣き始めた。
「えっ……」
極限まで張り詰めいてた緊張感が、その泣き声で一気に弛緩する。厳しい生存環境で育った暗黒人にとって、赤ん坊は何よりも大切にしなければいけない存在だ。そして同時に、戦おうとしている相手が、赤ん坊の母親だと理解させられてしまった。
「くっ……」
シルヴィーは、いたたまれなくなってその場から逃げ出した。
「確かに、赤子が泣く前で決闘などできないわね。申し訳ないことをしたわ」
構えを解いたファナティオが、心から申し訳なさそうに謝罪した。
「ファナティオ様、無茶です! いきなりこんな……」
「すまなかったわね、レンリ。よしよし、ベルチェ、こっちにおいで」
ファナティオの腕に抱かれてあやされ、鳴き声を上げていたベルチェがすうすうと寝息を立て始める。その寝顔を愛おしそうに見つめながら、ファナティオは小さな声でつぶやいた。
「だが……家族を奪われた者の気持ちは、そう簡単には救われないわ。まして、父と母を同時に奪われたのではね……」
翌日、シルヴィーはシャーリーの誘いを断って、全ての授業を休んだ。シャーリーには申し訳ないと思ったが、今人界人に会って、平静でいられるとはとても思えなかった。
両親の仇は死んだ。でも、だからといってその妻であるファナティオを仇として討っていいのか。それをして、両親の無念は晴らされるのか。
「それに……あの赤ん坊……」
シルヴィーがファナティオを討てば、ベルチェと呼ばれていたあの赤ん坊は両親を失うことになる。シルヴィーと同じように。
「父さま……母さま……私は、どうしたらよいのですか」
コンコン
「ん……?」
悩んでいる間に、いつの間にか寝てしまったようだ。人界に来てから、夜はなかなか眠れていない。昨日は特に寝付きが悪かった。
コンコン
「……ロニエか、ティーゼかな」
シルヴィーが授業を欠席したので、心配して見に来たのだろう。無視しようかとも思ったが、人界人たちはみなお節介だ。シルヴィーが顔を見せるまで、しつこく来るかもしれない。
「誰だ?」
「ファナティオだ」
「えっ!?」
一瞬聞き違えたのかと思った。だが、扉の向こうから聞こえてくる声は、確かに昨日会ったファナティオの声だった。
「な、何の用だ!? 私を追い出しに来たのか!?」
「まさか。話がしたいだけよ。ここをあけてもらえないかしら」
「そ、そんなこと……」
できるわけがない、と言い掛けて思いとどまった。怯えていると思われたくない。相手は両親の仇……に近しい人間だ。それに、ファナティオがなぜ来たのか知りたいという気持ちもあった。
「待ってろ!」
おそるおそる扉を開けると、ファナティオが部屋に入ってきた。昨日と違い、鎧も剣も身につけていない。侮られているのか、と頭に血が上りかけたが、昨日感じたファナティオの実力であれば、剣がなくてもシルヴィーを倒すことは容易だろう。
「突然押しかけてごめんなさいね」
「いいから、何の用で来たのか言え」
平静を装って強気に言葉を発するが、語尾が震えるのは抑えることが出来なかった。
「いくつかあるけど……まずは、昨日のことを謝罪させてちょうだい」
「謝罪!? え、でも……」
「騎士たる者が、赤子を連れた相手と決闘なんでできるはずがないわよね。それなのに、考えもなくあんなことを言って申し訳なかったわ」
「……別に」
いきなりの謝罪にシルヴィーは面食らった。ファナティオが真剣に謝っていることは、シルヴィーにもわかる。だが、その言葉を素直に受け入れることは出来なかった。
「それで、改めて伝えに来たの。仇討ちなら、いつでも受けるわ」
「……本気、なのか? でもどうせ、ほかの整合騎士と協力して……」
「シルヴィー」
ファナティオはシルヴィーの目をじっと見つめた。シルヴィーは目を逸らそうとするが、どうしても視線を外すこと出来ない。
「こう見えても、私は整合騎士団長よ。そんな卑怯な真似は決してしない」
ファナティオの迫力に、シルヴィーは思わず頷いてしまった。
「それと、ベルチェのことも案じなくていい。もし私が倒れても、このカセドラルでなら立派に育ててくれるから」
「な、なんでだ! だって、お前が父さまたちを殺したわけじゃないのに、どうして……」
「そうね……なぜか、と聞かれると説明が難しいけれど……」
ファナティオは困ったように笑った。
「私もベルチェを授かって、家族の大切さがわかったから、かしらね。家族を失ったあなたの気持ち、全てわかるとは言わないけど、共感は出来るつもりよ」
ファナティオも、もしベルクーリを殺した相手が目の前にいれば、仇を討とうとするだろう。騎士として生きてきた者であれば、なおさらその思いは強い。
「……本気、なんだな」
「ええ」
「わかった。でも、今はいい。今の私じゃ、お前に勝てない」
「そう。自分のことも、よくわかっているようね」
じっとファナティオを見つめていたシルヴィーの体から、ふっと力が抜ける。ファナティオの方は、相変わらずの自然体だ。
「……聞いてもいいか? その……ベルクーリ、のことを」
「ええ、何を聞きたいの?」
「あの男……ベルクーリは、父さまと母さまじゃ太刀打ちできないくらい強かった。そんな騎士が、どうして死んだんだ?」
ファナティオの目に、悲しみの色が浮かぶ。
「暗黒皇帝ベクタとの戦いで、命を落としたと聞いているわ。残念ながら、その戦いにも、最後の瞬間にも、私は立ち会えなかったけど」
「皇帝が……」
「皇帝ベクタは、自分自身の欲求のために神を騙った、異界からの侵略者よ。ベルクーリ閣下は、一度はベクタを倒したけれど、異界にいる本体にトドメを刺すことはできなかった。でも、その時の働きがあったからこそ、人界と暗黒界は今のように平和を維持できる」
ファナティオの言葉には、ベルクーリへの誇りと愛情が感じられる。
「私は、キリトのその言葉を信じている」
「……騎士として、戦って死んだんだな」
「ええ、きっとあの人らしく戦って、そして……最期を迎えたと思うわ」
戦って、最期を迎えた。それは、シルヴィーの両親にも言えることだ。綱から落ちて死んでいった者たちも多い中、奇襲を受けたとはいえ、最期は剣を握って騎士として戦うことができた。迎え撃つ体制が不十分だったのは、皇帝が綱で峡谷を越えるという無理難題を命じたからだ。だとしたら……ベルクーリを恨むのは、筋が違うのではないか。
そんな疑問が、ぐるぐるとシルヴィーの頭を巡る。その中で、ひとつ引っかかることがあった。
「皇帝ベクタが、異界から来たというのはどういうことだ? ベクタは暗黒神の再来で、暗黒界軍の総司令官だったんだぞ。それが、異界から? 自分の欲求って……」
「詳しいことは、私にもよくわからないの。キリトなら知っていると思うけど」
「そうか、わかった。なら、キリトに聞いてくる」
皇帝のことは、もっとよく知らなければならない。父さまと母さまを窮地に追い込んだ元凶を。総司令官の命令ならば仕方ないと思っていたが、それが私利私欲のためだとしたら……。
「いってらっしゃい。またね、シルヴィー」
ファナティオの言葉を背に受けならが、シルヴィーは部屋を出て行った。
「いた、キリト!」
セントラル・カセドラル中を探し回って、ようやくシルヴィーはキリトを見つけた。キリトは神出鬼没で、誰に聞いてもはっきりした所在がわからない。本当にこいつは、最高権力者なんだろうか。
「うおっ、シルヴィー。いきなりどうしたんだ?」
背中から声を掛けられて、キリトの首だけがこちらを向く。
「というか、今は神聖術のソネスさんの授業じゃないのか。おっかない授業だってアスナたちから聞いてるけど、出なくて大丈夫……」
「キリト、暗黒皇帝ベクタは異界から来たっていうのは本当か!?」
「はあっ!?」
思ってもいなかった言葉をぶつけられて、キリトの口がポカンと開く。
「ベクタって、何でいきなりそんな……」
「いいから答えろっ!」
シルヴィーの悲壮とも言える顔を見て、真剣に答えるべきだと判断したのだろう。キリトはシルヴィーの正面に向き直って答えた。
「君の言うとおり、ベクタは異界人だ。暗黒神ベクタの姿を借りて、この世界に来た」
キリトの目が遠くを見る。ここにはいない誰かを思うように。
「その目的は、《光の巫女》アリスを手に入れること。その、個人的な目的のために戦争を起こし、暗黒界と人界を滅亡の危機に陥れた」
「そんな……それじゃ、父さまと母さまが綱渡りをさせられたのって……」
「綱渡り……」
シルヴィーの言葉にキリトは目をつぶる。自分の記憶を探っているようだ。やがて何かに思い当たり、
「イスカーンから聞いたことがある。拳闘士や暗黒騎士が、無理な使命を与えられて捨て石にされたって」
「捨て石……個人的な欲求のために……そんなことのために」
そうかもしれないとは思っていた。だが、いざ本当にそうだと告げられると、やはりショックが大きかった。シルヴィーの両親も、暗黒騎士や拳闘士も、豊かな人界を手に入れるために戦った。人界人にとっては災厄かもしれないが、暗黒界にとっては遙か昔から伝えられてきた夢だ。だからこそ、命をかけて戦うことが出来たのに。
「シルヴィー、大丈夫か」
「……大丈夫」
ひとりだったら、また泣いていたかもしれない。だがキリトの……人界人の前では、そんな姿を見せたくなかった。
「教えてくれてありがとう」
「どういたしまして。でも、本当に大丈夫か」
「大丈夫だと言っている。それじゃ」
にじみそうになる涙を必死にこらえて、シルヴィーはキリトに答える。そして、唇を噛みながら、自分の部屋に戻った。
「ただいま」
シャーリーが部屋に戻ると、シルヴィーは両親からもらった剣を磨いていた。目が少し赤く腫れているように思えたが、決意に満ちた表情をしていた。
「元気になったみたいだな、シルヴィー」
「うん。心配かけてごめんね、シャーリー」
「別にいいよ。でも、ソネス先生は怖かったなー。明日の授業で怒られるぞ、きっと」
「しょうがないよ。休んじゃったし」
「そうだな、しょうがないな!」
そう言ってふたりは笑い合った。
「シャーリー」
「ん?」
「仇討ちは、しばらく保留にする。まだ、父さまと母さまの仇を討てるほど、私は強くないから。少なくとも、この剣を振れるようになってからにしようと思う」
「そっか。それじゃわたしと同じだな!」
「うん、同じだね」
「その剣、すごく立派だよなー。骨で出来てるみたいでかっこいいし。どこで手に入れたんだ?」
「これはね、父さまと母さまと一緒に……」
シルヴィーが話し始めると、シャーリーはシラル水をふたり分カップに入れて持ってきた。ふたりの部屋からは、夜遅くまで笑い合う声が聞こえてきていた。
「ほう……これはかなりの逸品だな」
シルヴィーの剣を一目見て、ソルティリーナ・セルルトは感嘆の声を漏らした。シルヴィーは誇らしげに胸を張る。そんなふたりを、キリトは微笑ましく見守っていた。
こうなったきっかけは、キリトがシルヴィーの持っている剣に目を留めたことだ。シルヴィーの実力はここ数週間でメキメキと強くなっているが、まだ骨の剣を振るうことは出来ない。ならば、もしかしたら名のある剣かもしれない、と武具に詳しいソルティリーナを呼び出したのだ。
「シャスター様からは、神器に近い武器だってお墨付きを頂いたんだ」
「ああ、神器級というのも決して間違いではない。獣の骨で出来た武器のようだが……残念ながら、私の知っている武具の中に、当てはまる物はないな」
「うーん、そうか。暗黒界で見つかった武器だから、かなあ」
「別に、わからなくてもいいけど」

ソルティリーナから剣を受け取ると、シルヴィーは大事そうに鞘に収めた。
「でも、不便じゃないか? 剣の銘がわからないのも……って、俺が言うのもなんだけど」
愛剣をずっと「黒いの」と呼んでいたキリトに、《夜空の剣》と名付けてくれたのはユージオだ。
「確かに、それはそうだけど……セルルト将軍、この骨は何の骨だかわかるか?」
「そうだな……おそらくは肉食獣で、四つ足の獣だな。巨大な虎か何かだと思う」
「虎……」
「虎で神獣といえば白虎だな」
「「びゃっこ?」」
聞き慣れない言葉に、ソルティリーナとシルヴィーが同時に首をかしげる。ソルティリーナは楽しそうに笑ったが、シルヴィーは気まずそうにそっぽを向いた。
「俺たちの世界には、世界を守る四体の神獣がいるっている伝説があるんだ。ま、ひとつの国の話だけど……」
世界の中にいくつも国があって、神話や伝説が異なる、と言ってもここではあまりわかってもらえなそうだ、とキリトは説明を省いた。
「その中に、白虎っていう虎の神獣がいるんだ。全ての獣を従えるって話」
「全ての獣の王様、か……」
シルヴィーは鞘を撫でながら、少し嬉しそうだ。
「《白虎の剣》か。それはいい銘だな」
「ま、まだそれにするって決めたわけじゃないから!」
むきになるシルヴィーに、ソルティリーナとキリトが笑う。その笑い声を聞きながら、確かに人界人も、悪い奴ばかりじゃないかもしれないな、とシルヴィーも笑った。