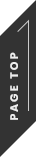ファナティオとベルクーリの死闘が繰り広げられていた頃。ロニエとティーゼは、アルダレスの呼び出したミニオン相手に苦戦していた。空中から攻撃してくる敵に対し、剣ではなかなか有効な一撃を与えられない。神聖術を使おうにも、詠唱の途中で空中から接近されると、中断して迎撃せざるを得なかった。
「ミニオンたちよ、この者たちを命ある限りここに足止めせよ」
ロニエたちの苦戦を見て、アルダレスはそう命令を下す。そしてアルダレスは、ロニエたちから離れ、セントラル・カセドラルの方へと向かった。
「ま、待ちなさいっ!」
ロニエが追いかけようとするが、その前にミニオンが立ちはだかった。だが、ティーゼを攻撃してくるのではなく、ロニエの動きを封じるように、右へ左へ飛び回る。
「くっ……」
「ほっほっほ、せいぜいコイツらと遊んでおるがいい。余は行かねばならぬところがあるからな」
ミニオンたちのけん制で動けぬロニエたちを尻目に、アルダレスはセントラル・カセドラルの中へと入っていった。
ミニオンたちに囲まれ、ロニエたちは背中合わせに剣を構える。一体ずつ倒していたのでは、時間がかかりすぎる。しかし、敵を一掃するような攻撃手段を、ふたりは持っていなかった。
「ティーゼ、このままじゃみんなが……」
背中越しに、相棒に話しかける。何とか、ふたりで突破する方法を考えなければならない。中にいるのは、アスナを除けば非戦闘員ばかりだ。
「ロニエ、ここはあたしが引き受ける。だからロニエは、カセドラルに向かって」
「えっ……」
予想もしなかったティーゼの言葉に、ロニエは思わず振り向いた。
「そっ、そんなことできるわけないよ! 私たちふたりでも、苦戦しているのに……」
「アルダレスは、行くところがあるって言ってた。それが何なのかは知らないけど、行かせちゃいけない気がする」
ティーゼの言葉に、ロニエはハッとなった。ここまで周到に準備してセントラル・カセドラルを襲ってきたのだから、まだ自分たちの思いもつかない策が張り巡らされているかもしれない。セントラル・カセドラルを死守することも大事だが、ティーゼの言うとおり、手遅れにならないうちにアルダレスを追うべきだ。
「だから行って、ロニエ。大丈夫、こいつらが足止めに徹してるなら、あたしだってそう簡単にはやられないよ」
ティーゼは敵から視線を外さず、決意した声で言う。その言葉に、ロニエは迷いを振り切った。
「わかった。絶対死なないでね、ティーゼ」
「もちろん」
その答えを聞くやいなや、セントラル・カセドラルへ向かって走り出した。ミニオンたちはロニエを止めようと、こちらへ向かってくる。その瞬間、振りかぶったロニエの持つ刀身が淡い水色の光を帯びた。リーゼッタを助けたときにも使った技、アインクラッド流高速突進技《ソニックリープ》。
「やああああーーーっ!!!」
ロニエの体が、弾かれたように加速し、進路を塞ごうとするミニオンとミニオンの隙間をすり抜けた。そのまま、カセドラルの正門を過ぎたところまでロニエは跳躍した。振り下ろした剣を当てる敵がいないため、体勢を崩して地面に転がる。
「行かせないよっ!」
ロニエを追いかけようとするミニオンを切りつけ、ミニオンの前に回り込む。先ほどまでとは逆に、ティーゼがミニオンたちの進路を塞ぐ形だ。
「あんたたちは、あたしの足止めが仕事でしょ? さあ、来なさい!」
ティーゼの気合いを背中に聞きながら、ロニエはセントラル・カセドラルの中に向かった。ティーゼの無事を祈りながら。
セントラル・カセドラルの入り口には、戦闘の形跡はなかった。フレニーカたちは、おそらく中層以上に避難しているのだろう。アルダレスの目的がなにかはわからないが、高層であることは間違いない。
「急がないと……」
ロニエは全速力で階段を駆け上がる。この階段を、アルダレスのような老人が上れるんだろうか、という考えが頭をよぎったが、そもそも相手は死んだはずの人間だ。そんな常識的な考えは、捨てた方がいいだろう。
三十階には飛竜発着場がある。今は、整合騎士たちの飛竜はすべて出払っており、いるのは成育中の月駆と霜月だけだ。その階へ向かう階段を上っているロニエの耳に、遠くから悲鳴と爆発音が聞こえてきた。やっと追いついた、とロニエは疲れた足にむち打って残りの階段を駆け上がった。
「ジェネレート・クライオゼニック・エレメント! フォーム・エレメント、アロー・シェイプ!」
フレニーカが放つ氷の矢が、飛びかかってくるミニオンに突き刺さる。ミニオンは痛みを感じるかのように体を震わせ、わずかに動きが鈍った。
「バースト・エレメント!」
そこへ、セルカの放った光素が炸裂する。ミニオンの体が光に包まれ、羽根の一部が弾け飛ぶ。だが、それでもミニオンはフラフラと飛び回り、かぎ爪で攻撃してくる。
「もう、いい加減に倒れなさいよ!」
セルカが荒い息を吐きながら文句を言った。もちろん、ミニオンにそれが通じるわけもなく、半分が崩れた体でセルカとフレニーカに迫ってくる。
「セルカ、そろそろ神聖力が……」
「うん……」
三十階に避難していた見習い術士たちは、アルダレスの呼び出した二体のミニオンと戦っていた。だが、ほとんどの術師にとってこれが初めての実戦であり、敵を目の前にして式句が唱えられなくなってしまった者もいた。そんな中、セルカとフレニーカが先頭に立って戦い、負傷者たちを下がらせた。かろうじて一体倒すことはできたが、残りの一体に苦戦し、近くで回復を行っていることもあり、セルカたちが使える空間神聖力も、そろそろ尽きようとしていた。自分たちも避難所へ逃げ込むか、それともここで踏みとどまるか……そう逡巡していたとき、廊下の向こうから人影が猛スピードで走ってきた。
「ロニエ!」
「やああああーーーっ!!!」
ロニエは走ってきた勢いのまま、羽根を失ったミニオンの体を両断する。断末魔の悲鳴を上げて、ミニオンは息絶えた。
「大丈夫だった!?」
「私もフレニーカも大丈夫」
「ほかのみんなも、避難してる。みんな無事だよ」
全員の無事を確認し、ロニエはほっと息を吐き出す。だが、すぐに表情を引き締めた。
「ここにアルダレスが来たはずだけど……」
「あいつのことね。そいつなら、私たちにミニオンをけしかけて、上に上がって行っちゃった」
「ごめんね、ロニエ。私たちも何とか食い止めようとしたんだけど……」
肩を落とすフレニーカ。セルカも悔しそうに唇を噛んでいる。ロニエはそんなふたりの肩に手を回して、ぎゅっと抱き寄せた。
「ううん、ふたりが無事でよかった。ミニオンを食い止めてくれただけでも、立派だよ」
「ロニエ……」
ロニエの言葉に励まされたセルカとフレニーカは、ふたりで顔を合わせ、決意したような顔で頷いた。
「アルダレスって人を止めなきゃいけないんだよね? それなら、ここのみんなは私たちに任せて、ロニエはあいつを追って上に行って」
「でも、もしまたミニオンが出てきたら……」
逡巡するロニエに対して、セルカとフレニーカはロニエの手をぎゅっと掴んだ。
「防御に徹すれば私たちでもなんとかできる。それよりもロニエは上に行って、あいつを止めるべきだよ」
フレニーカも、心配そうなロニエに、大丈夫、と頷いてみせる。
「わかった。セルカとフレニーカはみんなをお願い。私はアスナさまたちをお助けしないと」
そう言ってふたりから体を離すと、ロニエは一度深呼吸した。
「気をつけてね、ロニエ」
セルカに頷き返し、ロニエは上階を目指して再び走り始めた。
階段を駆け上がりながら、ロニエはアルダレスの目的を考える。オブシディア城の時と同じように、ベルチェを誘拐して、ファナティオを脅迫するつもりだろうか。それとも、創世神ステイシアの生まれ変わりとして、民衆から崇拝されているアスナが狙いか。どれもないとは言えないが、暗黒界・西帝国と二重の陽動を仕掛けてまで狙うとは少し考えにくい。異界戦争で見せたアスナの力を知らないとは思えないし、ベルチェを狙うのであれば、オブシディア城のように、隠密裏に事を運んだ方がいい気がする。
「だとすると、クルーガの事件と関係があるのかな……」
あの時、クルーガを倒すことは出来たが、いくつもの謎が残った。空を飛んでいった赤い宝石と、クルーガの遺体から出てきた徽章。徽章はキリトがアユハたち神聖術師と協力して解析を進めているが、まだ何の成果も得られていない。その徽章は、キリトとアスナしか知らない場所に保管してある――
「あっ! もしかしたら、あの徽章を……?」
クルーガが甦った秘密が、あの徽章に隠されているとしたら、アルダレスが狙う可能性は高い。もちろん、見つからない場所に保管してあるだろうが、元々皇帝たちが造り出したものだ。それを探す方法を持っていても不思議はない。
五十階に到着すると、ロニエは自動昇降盤へと向かった。思った通り、昇降盤は使用され、上階へと昇っている。一瞬、もしエアリーが昇降係をやってくれていたら……と思ったが、その場合はエアリーが害されていただろう。そうならなくてよかった、と思い直す。
「こうなったら、階段で……ううん、九十五階までなら、さすがに昇降盤を使った方が早いよね」
どこまで上がっているのだろうか、昇降盤を呼んでもなかなか下がってこない。ジリジリしながら昇降盤を待っていると、背後からこちらへ向かってくる足音がした。反射的に剣を構えて振り向くが、駆け寄ってくる姿を見てロニエの表情が明るくなる。
「ティーゼ!」
「ロニエ! やっと追いついた!」
ロニエの元まで辿り着くと、ティーゼは乱れた息を整えるために深呼吸をする。
「ティーゼ、正門の方は……?」
「うん、ファナティオ様がベルクーリ騎士長……のミニオンを倒した後、加勢してくれたの。それで、あっという間に倒しちゃった」
「そっか、よかった」
ロニエは、追っているアルダレスについて、自分の考えたことをティーゼに説明する。相手の狙いは徽章の可能性が高いが、その在処はキリトとアスナしか知らない。
「だから、九十五階に行ってアスナさまにお聞きしようかと思ってたんだけど……」
ロニエが説明している間に、昇降盤が降りてくる。
「ロニエ、それだと時間がかかりすぎるよ。直接アルダレスのところに行かないと」
「でも、居場所が……」
「この前やった《心意感知》なら、わかるんじゃない」
あっ、とロニエは声を上げた。《心意感知》は、心意の力で人間や生き物の場所を感知する技だ。ロニエとティーゼ、個人個人の力ではまだまだ感知範囲は低いが、ふたりの力を合わせる《身気合一》の法を使えば、広い範囲を探ることが出来る。それでも、以前クルーガの別荘で使った時は、せいぜい二階建ての屋敷を探るのがせいぜいだった。
「あたしたちだって、毎日特訓して、強くなってる。これで相手の気配を探ろう!」
「……うん!」
そうだ、自分たちはもう見習いじゃない。人界統一会議を、代表剣士キリトを支える一人前の整合騎士だ。キリトのように十キロル先の気配を感じるのは無理でも、数十メルの範囲なら――そう決意し、ロニエはティーゼと掌を合わせた。
ティーゼの呼吸が落ち着き、ロニエのそれに同調する。やがてふたりの感覚に境界がなくなってゆき、知覚の範囲が広がった。五十階から五十五階、六十階、七十階――
「――いた!」
その感覚が八十階に達したとき、ふたりは同時に声を上げた。八十階、《雲上庭園》に禍々しく、冷たい気配がある。それは、以前感じたクルーガとゼッポスの気配によく似ていた。ふたりは声もなく昇降盤に跳び乗り、風素を最大出力で送り込んだ。
《雲上庭園》――清らかな小川流れ、緑と花にあふれたこの階層は、整合騎士アリス・シンセシス・サーティが愛した場所だ。アリスがいなくなった後でも、キリトやアスナはよく訪れている。だが、今そこにあるのは、邪悪な気配をまき散らしながら、奇妙な式句を唱えるアルダレス・ウェスダラス五世の姿のみだ。ロニエとティーゼが駆けつけたときも詠唱を止めることはなく、ふたりの方を振り返ろうともしなかった。
「はあああっ!」
問答をしている余裕はない。過去にクルーガの儀式を目の当たりにしているふたりは、そう結論づけ、警告を発することなく斬り掛かる。その気配に気付いているのかいないのか、アルダレスはロニエたちに反応することはなく、ロニエの剣は胴体を半ば両断し、ティーゼは左腕を斬り落とした。
「………………」
胴を切り裂かれ、腕を失って、アルダレスの体がバランスを崩して倒れかかる。それでも、アルダレスは詠唱を止めない。
「やっぱり……人間じゃない!」
「詠唱を止めないと!」
ロニエとティーゼは、再び剣を振り上げる。そして、うっすらと笑みを浮かべながら詠唱を続けるアルダレスの首を斬り飛ばした。
「ぐふっ……」
地面に落ち、アルダレスの口から血とも泥ともつかない、ドロドロした粘液が吐き出された。ようやく詠唱が止まり、ホッとするロニエに向けて、ぎょろりとアルダレスの眼球が動いた。
「……遅かったな。形代は、すでに……」
「形代……?」
アルダレスの言葉にロニエが問い返すが、それに応えることなく、アルダレスの体は真っ黒な粘液へと変わっていく。終わった、と思ったロニエの胸に、不安が大きく広がっていく。
「ロニエ、あれを見て!」
ティーゼの声が、その不安を現実のものとした。ティーゼの指さす先――かつて、アリスが愛した金木犀があった場所――に、黒いぶよぶよとした塊が出現している。それは少しずつ人のような形になっていく。だが、その大きさは人間を遥かに超えて、みるみるうちに体長五メルにも届こうかという巨人になった。
「クルー、ガ……」
そして、その巨人の顔は、ロニエとキリトによって二度倒された、クルーガ・ノーランガルスにそっくりだった。
「形代……あの、徽章が」
そういえば、クルーガも言っていた。ホーザイカ・イスタバリエスは形代を失ったため、復活できないと。その時はどういうことかわからなかったが、今はわかる。あの徽章こそが、クルーガの《形代》なのだ。
「だったら――!」
あの体に核として存在するはずの、形代を壊してしまえばいい。そうすれば、二度と復活することは出来ない。ロニエは剣を振り上げ、《ソニックリープ》の構えを取る。一瞬、後、弾かれたように飛び出したロニエの剣が、クルーガの右脚を切り裂いた。
「……えっ!?」
だが、脚の半ばまで切り裂かれた傷が、みるみる塞がっていく。二度、三度とロニエは切りつけるが、その傷もあっという間に復元されてしまった。
「それならっ!」
剣の攻撃が効かないと見たティーゼが、熱素の矢をクルーガに飛ばす。爆発音がして、着弾した部分の肉が焼け焦げ、えぐり取られた。だが、それも剣の傷と同じように塞がってしまう。
「そ、そんな……剣も神聖術も効かないなんて!」
攻撃手段を失い、呆然となるふたり。そこへ、クルーガの巨大な手が襲いかかる。思った以上のスピードで迫る手をかわしきれず、ロニエとティーゼは吹き飛ばされ、外壁へとたたきつけられた。
「ぐっ……」
衝撃で、ロニエは一瞬呼吸が出来なくなる。そこへティーゼの体が飛んできて、ロニエはかろうじてそれを受け止める。そのまま、ふたりは絡まり合った状態で地面へと落下した。
「うっ……。てぃ、ティーゼ……大丈夫?」
「ロニエこそ……」
必死に呼吸を整え、立ち上がろうとする。だが、そこへクルーガの第二撃が迫った。
――避けられない!
ロニエは一瞬でそう判断し、せめてダメージを減らそうと、体を縮めて防御態勢を取る。だが、来るはずの衝撃は襲ってこなかった。その代わり、空気を切り裂くような音がして、迫り来るクルーガの手を切り落とした。
「い、今のは……」
「大丈夫、ロニエさん! ティーゼさん!」
ロニエの耳に届いたのは、九十五階にいるはずのアスナの声だった。左手にベルチェを抱き、右手にはレイピアを持っている。そのレイピアで、クルーガの腕を斬り飛ばしたのだ。
「アスナさま! はい、大丈夫です!」
「でも、ベルチェちゃんが……」
ティーゼの言葉に、アスナは少し困った顔で笑った。
「この階に巨大な気配を感じたから、来ちゃったの。でも、ベルチェちゃんを置いてはいけないから」
左手の中で眠るベルチェを、よいしょ、と抱き直す。
「大丈夫、この子もちゃんと守る。だから、あんまり無茶は出来ないけど……わたしも戦うわ」
「はいっ!」
ロニエとティーゼは剣を構え直す。クルーガの斬られた腕は、少しずつ復元しつつあった。
クルーガとロニエたち三人の戦いは、熾烈を極めた。巨大なクルーガの体に対して、普通の攻撃は効果がない。さらに、大きなダメージを与えても、時間を与えれば復元してしまう。だが、ロニエとティーゼの《アインクラッド流》剣技、それに赤ん坊を抱えているとは思えないアスナの細剣での連撃を合わせた攻撃で、クルーガの体は徐々に傷つき、回復が追いつかなくなっていった。
「これ以上……この場所を荒らさないでっ!」
体を削られ、体勢を崩すクルーガに、アスナはレイピアを向ける。時間がかかればまたクルーガは復活してしまうだろう。
「やああああーーーっ!!!」
歯を食いしばって、アスナはレイピアを振るった。切っ先は真っ直ぐクルーガの頭を狙っている。アスナの斬撃が、切り裂き音を伴ってクルーガの顔に迫った。それを防ぐように手をかざしたが、そこにロニエとティーゼが左右から《ソニックリープ》で斬り掛かった。それぞれの剣がズブリ、という鈍い音を立てて腕の半ばほどまで食い込み、クルーガの腕が斬り飛ばされた。腕を失い、無防備となったクルーガの顔へ、アスナの斬撃が迫る。
「――――――ッ!!!」
初めて、クルーガが声にならない悲鳴を上がる。その振動に、八十階全体がビリビリと揺れた。首の七割以上を切り裂かれ、クルーガの顔が不自然に前にかしぐ。そのまま、ゆっくりと首がちぎれ、ズシン、という大きな音を立てて体から落ちた。そのまま、嫌な匂いのする泥となって地面に広がる。
「や、やった!」
「あの怪物を、倒した!」
手に手を取って喜ぶロニエとティーゼ。アスナも、額に汗を光らせながら、安堵のため息をついた。その息を感じたのか、眠っているベルチェがムズムズと鼻を動かす。
「あ、ごめんねベルチェちゃん。でも、もう安心だからね」
雲上庭園は荒れちゃったけど……ベルチェと、みんなを守れた。これでキリトくんにも顔向けが出来る……アスナがそう思ったときだった。
「……え?」
ロニエの手を取っていたティーゼが、驚いて息を呑む。首を落とされ、一時は完全に動きを止めたはずのクルーガの体が、再びザワザワと動き始めたのだ。
「まだ、動くの……?」
絶望の声がアスナの口から漏れる。もう一度戦うため、緩めかけたレイピアを握る手に、再度力をこめ、今度はステイシアの力を使おうとすると、激しい頭痛が襲ってくる。
「ま、まだまだ……!」
脂汗を流し、痛みに耐えるアスナ。完全に復活する前に、今度は徹底的にやっつけないと。そう思って手を動かすが、自分が考える以上に消耗が激しく、痛みも強かった。
クルーガの体は崩れ落ち、黒い泥となった。だがその泥は、再び意志を持つかのように寄り集まり、形を変えながら徐々に大きくなっていく。ロニエたちは気力を振り絞って攻撃しようとするが、先ほどの戦いで負ったダメージは大きく、体が思うように動かない。やがてクルーガ――の泥――はアルダレスだった泥も飲み込み、膨れ上がっていく。やがて、天井まで届こうかという大きさに成長したそれは、姿もおぞましいものへと変わっていた。
それは、見ようによってはタコや、多足生物のように見えた。巨大な丸い頭に、何本もの触手が生えている。だが、大きく違うのは中央にある巨大な口だ。人間など一口に飲み込んでしまいそうなほど大きく開かれた口には、不揃いの牙が生えている。その怪物が触手を振り回すと、セントラル・カセドラルが大きく揺れた。
「ロニエさん、ティーゼさん、避難を!」
剣を構え、戦おうとするふたりを、アスナが引き留めた。
「ですが、アスナさま! このままではカセドラルが……」
「大丈夫。ここはわたしが守るから」
そう言って、アスナはロニエにベルチェを差し出した。一瞬でその意味を悟ったロニエは、激しく首を振る。
「いけません、アスナさま!」
「ロニエさんが心配しているようなことはないわ。ベルチェちゃんを抱いたままだと、本気で戦えないだけ」
「違いますっ! アスナさま、そんなに一気に力を使っては……」
アスナがステイシアの奇跡を使うと、体に負担がかかると聞いている。実際、セントリアで起こった殺人事件の調査で、アスナが過去視術を使った時。術後、アスナはぐったりとして動けなくなっていた。それを、こんな敵を相手に使っては、アスナの命が危ない。
「私もお供します。みんなで戦えば、きっと……」
「そうです! あたしたちだって、整合騎士なんです!」
「ダメよ。そうなったら、ベルチェちゃんを守る人がいなくなる」
そう言われ、ロニエは腕の中のベルチェを見る。こんな状況でも、ベルチェはすやすやと寝息を立てていた。確かに、この子を逃がす人間が必要だ。そして、少なくともその人物が逃げ切れるまで、誰かが時間を稼がなければならない。それを、自分たちが稼げるだろうか。
「……っ!」
自分たちが時間を稼ぐ、と言いきれない自分が情けなくて、言葉が出ない。
「さあ、早く……きゃっ!」
咆哮を上がながら暴れ回る怪物の触手が、ロニエたちがいる場所に振り下ろされた。間一髪直撃は避けられたが、ロニエとティーゼは外壁の方へ吹き飛ばされた。幸い――といえるかどうか――そこは、雲上庭園の出入り口がある場所だった。
「そのまま逃げて!」
それだけ言うと、アスナはレイピアを構える。もし自分が死んでも、それは本当の死ではない。この世界から消えるだけで、現実の肉体に戻るのだ。本当の死を迎えてしまうロニエとティーゼを戦わせるわけにはいかない。
「そうだよね、キリトくん」
きっと、キリトなら賛同してくれる。たくさん泣いちゃうかもしれないけど。だから先に謝っておくね、ごめん。
「さあ、来なさい! あなたの相手はわたしよ!」
アスナが怪物に戦いを挑むのを、ロニエは呆然と眺めていた。逃げなければ。でも、アスナを置いてはいけない。相反する気持ちで、ロニエは動くことが出来なかった。それは、ティーゼも同じなのだろう。体を出口に向けたまま、視線はアスナから外すことが出来ないでいた。
――キリト先輩!
――キリト先輩、アスナさまが危ないんです!
――キリト先輩、助けてください!
「キリト先輩っ!!!」
知らず知らずのうちに、ロニエは叫んでいた。暗黒界にいて、来てくれるはずはないのに。声が届くはずないのに。大きな声に驚いて、ベルチェがふえぇっと泣き声を上げる。ベルチェを守るようにぎゅっと抱きしめるロニエの目からも、大粒の涙が零れた。
――泣くなよ。
そんな声が聞こえた気がした。
――錯覚に決まってる。だってキリト先輩は、遠くにいるんだから。
そう思いながら、しかし一縷の希望を抱いて目を上がる。眼前に広がるのは、巨大な怪物の姿と、真っ白なセントラル・カセドラルの外壁。ああ、やっぱり……と再び涙があふれる。だが、怪物の触手の一本が吹き飛び、消滅するのを見て、ロニエは目を見開いた。
「うおおおおおっ!!!」
黒いコートを着た剣士が、両手の剣で次々と怪物の触手を斬り飛ばす。いつもの代表剣士の姿ではないが、それは確かにキリトだった。ロニエの目から、今度は安堵と歓喜の涙があふれ出す。巨大な口に二本の剣が突き立てられ、怪物が身の毛もよだつ咆哮を上げた。ロニエは身をすくめたが、それは怪物がキリトに倒されつつあるという証だった。
「そうだ、アスナさまは!?」
キリトに意識を取られて、アスナのことを失念していた。だが、片膝を突くアスナの元には、ティーゼが寄り添い、戦闘の余波を受けないよう守っている。さすがティーゼ、とロニエは嬉しくなった。
少し時間を遡る。
暗黒界から全速力で飛行するキリトは、途中、何か嫌な予感がして《心意感知》を行い、カセドラルに巨大な怪物が出現したことを知る。それは、先ほど倒したトルガシュや以前倒したクルーガとは比べものにならないほど禍々しく、危険だった。
「――アスナ!」
それまでの全力に輪をかけて、キリトはカセドラルへと急ぐ。そして、ようやく見えてきた時、カセドラルは全体が大きく揺れ、ピシピシと外壁に亀裂が走っていた。その亀裂へ向けて、キリトは速度を落とさずに突っ込む。眼前に迫る白亜の壁は心意の力で分解し、カセドラル内部に飛び込んで最初に目に入ったのは、怪物の触手に攻撃されるアスナだった。
「貴様あああぁぁぁっ!」
キリトは怪物へ向けて急降下した。その途中、代表剣士の姿から、かつて《黒の剣士》と呼ばれた頃のキリトへと変貌する。その手には、《エリュシデータ》と《ダークリパルサー》、二本の剣が握られていた。
「うおおおおおっ!!!」
キリトは怒りにまかせ、アスナに振り下ろされようとする触手を斬り飛ばす。そのまま、向かってくる触手をすべて切り伏せ、中央にある巨大な口に剣を突き立てた。
「グオオオォォォッ!!!」
空気の振動で吹き飛ばされるような怪物の悲鳴。だがキリトはひるむことなく、抜いた剣を再び怪物に突き刺した。暴れる触手の動きが徐々におとなしくなり、怪物の悲鳴も小さくなっていく。やがて、触手の先からボロボロと崩れ、乾いた砂となって散っていった。
「キリトくん……」
いつの間にか、代表剣士の姿に戻っていたキリトに、アスナは弱々しく微笑んだ。
「ごめん、わたしだけじゃあいつを倒せなかった」
「何言ってるんだよ。謝る必要なんかない。みんなを守ってくれたじゃないか」
「うん……何とか、守れたかな」
「ありがとう、アスナ。遅くなってごめんな」
「ううん、来てくれて嬉しかった。わたしがピンチの時は、いつも来てくれるね」
「ああ、必ず駆けつけるよ」
安心しきった表情で、アスナはキリトの胸にもたれる。キリトはアスナを抱き上げると、ロニエたちにも声をかけた。
「みんな、無事でよかった。ほかの人たちも大丈夫なのか?」
キリトに見とれていたロニエが、弾かれるように敬礼する。
「はいっ! ファナティオ様はじめ、カセドラルの職員たちもみんな無事です!」
「そうか、よかった。ありがとう、ロニエ」
「い、いえ……」
気が緩むと、泣きそうになってしまう。でも、ここで泣いたら、アスナを抱いているキリトが困ってしまうだろう。
「キリト先輩は、アスナさまを休ませてあげてください。わたしは、ファナティオさまたちの様子を見てきます!」
「わかった、頼んだぞロニエ」
「はいっ!」
もう一度敬礼をして、ロニエは駆け出す。やっぱり、キリトはロニエの英雄だ。どんなときでも、きっと助けに来てくれる。だから、もっと強くなろう。今度は、ロニエがキリトの危機に駆けつけられるように。
セントラル・カセドラル襲撃から、数日後。暗黒界、西帝国、セントリアの三カ所で同時発生した反乱は、すべて鎮圧された。カセドラル襲撃によって受けた被害は大きいが、幸い人的被害はほとんどない。外壁を修理するのは大変だが、もしかしたらそこで新しい技術が生まれるかもしれない。キリトはそんな期待も抱いていた。
暗黒界から帰ってきたシルヴィーは、キリト、シャーリー、そして人界軍将軍のソルティリーナの前で謝罪した。
「一時的とはいえ、人界軍として出陣したのに、裏切ってしまった。その罰は、何でも受ける覚悟だ」
「そう言っているけど、どうする? リーナ先輩」
「軍規違反を見過ごすわけにはいかないな」
そう言うソルティリーナに、キリトが慌てた様子で確認する。
「リーナ先輩、まさか……」
「信賞必罰は軍隊の基本だ。軍規違反を見過ごしては、人界軍の規律が乱れる」
「それはそうだけど……」
「だが、シルヴィーにはキリトと協力して敵将を討ったという武勲がある。信賞必罰の掟から言えば、その功績を無には出来ない」
そう言って、ソルティリーナは微笑んだ。
「今回は、その功績を持って夜間の離陣を不問とする。それでいいか、キリト」
もちろん、と頷くキリトだが、シルヴィーの方は納得いかない表情で
「で、でも、私は裏切って、向こうに忠誠を……」
と反論した。だがソルティリーナはすべてわかっている、という風情で答える。
「それは、敵の懐に入るための詭弁、と聞いているぞ」
「え……」
驚いてキリトを見ると、キリトはシルヴィーに頷いて見せた。
「シルヴィーのように強くて、暗黒界にも詳しい人材は貴重だ。出来れば、これからも力を貸して欲しい」
「……今は留学生だから、イヤでもそうなる」
シルヴィーは敢えてすました調子で答えた。それにキリトとソルティリーナが笑い、続いてシャーリーとイーディスも笑い出す。
「よかったな、シルヴィー! また人界で一緒に勉強しよう!」
シャーリーがシルヴィーの手を取って、ぶんぶん振り回す。困った顔をしながらもシルヴィーは頷いた。イーディスは微笑ましそうにふたりの様子を見ていたが、急にポンと手を叩いて、キリトに提案した。
「でもさ、本当に力を貸して欲しいなら、整合騎士になっちゃえば?」
「えっ!?」
思いもかけない言葉に、シルヴィーが素っ頓狂な声を上げた。
「整合騎士か。でもなあ……」
「そうすれば、あたしもシルヴィーと一緒にお仕事できるし。正騎士が早いって言うなら、見習いでも」
「見習いか。それなら……」
「ちょ、ちょっと待ってよ!」
どんどん進んでいく話に、シルヴィーは慌ててストップをかける。
「私は、整合騎士にはならないよ。だって暗黒騎士になるから」
「そうだよな、わたしたちは暗黒騎士になるんだ!」
「うん!」
「えー、残念だなあ……」
イーディスがあまりにも残念そうだったので、そこにいる全員がもう一度笑い出す。シルヴィーも笑いながら、こう思った。
――もう少しここで勉強して、人界のこと……そしてキリトのことを知りたいな。
セントラル・カセドラルの正門では、ファナティオがベルチェを抱いて、ベルクーリの体があった場所に立っていた。
「閣下……どのような形であっても、やっぱり私は、閣下に会えて嬉しいです。こんな風に言ったら、罰が当たるでしょうか……」
その言葉に応えるように、腕の中のベルチェがきゃっきゃと笑った。
カセドラルの内部では、先の戦闘の影響により少し荒れた教室で、ロニエたちがソネスの授業を受けていた。しばらく授業が空いてしまったので、その穴埋めだ。相変わらず厳しいソネスの授業だが、ロニエはいつにも増して真剣に臨んでいる。授業が始まる前、ティーゼと交わした会話を胸に秘めて。
「私、もっと強くならないと。キリト先輩の力になって、今度は先輩を守りたいから」
「あたしも、そう思う。そして、いつかこの《青薔薇の剣》を使えるようにならないと。そうじゃないと、先輩みたいに誰かを守れないから」
その日の夜。キリトとアスナは、少し歪んだ寝室のベッドで手を繋いでいた。
「改めて、大変だったよね、キリトくん」
「ああ、アスナにも苦労をかけちゃったよな」
「わたしは大丈夫だよ」
そう言って、アスナはキリトの手をキュッと握る。
「ありがとう。でも、まだ心配の種は尽きないんだ……」
「そうかもしれないね。でも、きっと大丈夫。みんながいるんだから」
「そうだな」
そう言って、キリトも手を握り返した。
「一番側に、一番頼れるアスナもいるしな」
「うん、頼ってくれていいよ」
そう言うと、おでこをくっつけて笑い合う。触れた場所から、相手の体温が伝わってくる。そのぬくもりは、これから何があっても大丈夫だろう、と思える温かさだった。